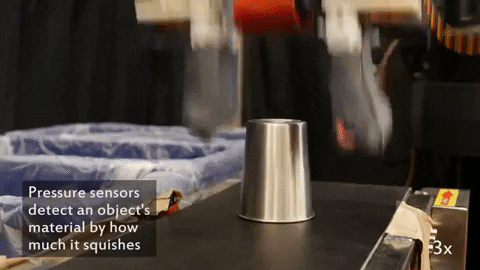iRobotのCEOはかつて筆者にいたずらっぽくこう言った。「掃除機のセールスマンになって初めて私はロボット技術者として成功した」と。いいセリフだし、ロボット業界の根本的な真実をさらけだしてもいる。ロボットは難しく、家庭用ロボットはさまざまな意味でさらに難しいのだ。
ルンバなどのロボット掃除機が収めた大成功を超える術を誰も解き明かしていないのは、挑戦していないからではない。これまで、主にAnkiやJiboなどスタートアップに分類される企業が取り組んできたし、珍しい例外としてはBoschが作ったKuriもある。ところが米国時間9月28日、Amazon(アマゾン)がこの問題に莫大なリソースを投入していることを明らかにした。

画像クレジット:Amazon
単にリソースを投入しているというだけではない。Amazonは同社初のロボット「Astro」を発表した。この製品はAmazonのDay One Editionプログラムの1つとして市場に第一歩を踏み出す。以前に同社はKickstarterやIndiegogoのように顧客が予約注文に投票できるこのプログラムを活用していた。新しいロボットには、アニメ「宇宙家族ジェットソン」の犬、The White Stripesのデビューアルバムに収録されている曲、ヒューストンのプロ野球チームと同じ名前が付けられ、2021年中に限定発売される。Day One Editionプログラムで発売された製品には小型プリンタやスマート鳩時計などがあったが、Astroはこのプログラムの中では飛び抜けて野心的なデバイスだ。999ドル(約11万円)と、このプログラムの中では最も高価でもある。
関連記事:アマゾンが予約注文で新しいAlexaデバイスの人気投票を実施、ラインナップにはスマート鳩時計も
ただしこの価格は早期購入者に限られる。Amazonの報道資料には以下のように書かれている。
Astroの価格は1,449.99ドル(約16万円)ですが、Day 1 Editionsプログラムの一環として999.99ドル(約11万円)の早期購入価格で提供します。Ring Protect Proの6カ月間無料試用が付属します。

画像クレジット:Brian Heater
発売時点のこのロボットには、主に3つの機能がある。
- ホームセキュリティ
- 大切な人の見守り
- 家でのAlexa体験のモバイルバージョン
Amazonはおよそ4年前からロボットに取り組み始め、社内のさまざまな部門を活用して完全に実現可能なホームロボットを開発した。
AmazonのバイスプレジデントであるCharlie Tritschler(チャーリー・トリッシュラー)氏はTechCrunchに対し「AI、コンピュータビジョン、処理能力について話し合い、そこで挙がったトピックの1つがロボットでした。消費者が利用できるようにするためにロボットはどう変化しているのでしょうか。我々にはもちろんフルフィルメントセンターでロボットを利用してきた経験は大いにありますが、家にいる消費者に利便性や安心を提供するために何ができるかを考えたのです。そこから考え始め、最終的には『ねえ、これから5年後か10年後に家にロボットがいないと思う人がいる?』ということになりました」と語った。

画像クレジット:Brian Heater
2012年にKiva Systemsを買収したことから始まったAmazon Roboticsが、コンシューマチームのアイデアに共鳴した。しかしAmazonのそれまでのロボット技術は業務用で、最短の時間で荷物を配送することに主眼が置かれている。最終的に同社はAstroのコンポーネントをゼロから作らざるを得なかった。その中には最も注目すべきものとして、家の中のマップを作り移動するために使われるSLAM(Simultaneous Localization And Mapping、自己位置推定と環境地図作成の同時実行)システムがある。
SLAMシステムは複雑な仕事を引き受けているだけでなく(これはiRobotが10年間かけて改良してきたことだ)、現在Amazonが有しているロボットテクノロジーをも考えると、筆者はこれには特に驚いた。Amazonは2019年に完全自律型倉庫用カートのスタートアップであるCanvasを買収した。しかしAmazonはこの新しいSLAMシステムはゼロから開発したもので、ロボット関連スタートアップの買収を検討したものの最終的にはAstroを作るための買収はしなかったと主張している。ただし、Ringのセキュリティ監視や、Alexaとホーム関連テクノロジーといった社内の技術は、Amazonのスマートアシスタントとなるこのロボットに組み込まれている。

画像クレジット:Brian Heater
筆者は発表の前週にAstroに触れる機会があり、このロボットはちょっと二重人格っぽいと感じた。このロボットのメインの人格は、R2-D2やBB-8、Wall-Eのようなものと表現するのが最も適切だ。顔は、実際には画面、あるいはタブレットと言えるもので、太い小文字のo(オー)が2つ並んでいるような極限までシンプルな目が表示されている。この目が時折まばたいたり動いたりするが、Ankiがピクサーやドリームワークスのアニメーターだった人材を雇って作ったCozmoほど表情豊かではない。
ときどき電子音が鳴って、前述したスター・ウォーズのR2-D2やBB-8をさらに思い起こさせる。ロボットに「Astro」と呼びかけることができるが、もっと直接的に会話をしたいときはどこかの段階で音声アシスタントでおなじみの「Alexa」と話しかける必要がある。
Astroの10インチタッチスクリーンの顔はちょっとした人格を表現することに加え、標準的なEcho Showのディスプレイとしても機能するので、動画を見たりビデオ通話をしたりスマートホームのコントロールをしたりすることができる。画面は自動で動くが、見やすいように手で60度傾けられる。この画面はAmazonの新しい顔認証であるVisual IDにも対応し、Astroは相手に合わせたやりとりをする。
スピーカーも2つ搭載されている。ロボット自体は驚くほど静かだ(ロボット掃除機ではないですからね)。Amazonが筆者に語ったところによると、実は家の中を動いていることがわかるように電気自動車のような音を付ける必要があったという。ただし車輪の向きを変えて方向転換をするときにはサーボ音が鳴る。
後方のスペースには4.4ポンド(約2キロ)まで物を積むことができる(オプションのカップホルダーがある)。内部にはUSB-Cポートがあり、携帯の充電に使える。Astro自体はルンバのようなドックを使用し、バッテリーが空の状態から1時間未満でフル充電される。

画像クレジット:Brian Heater
当然のことながら、多数のセンサーが搭載されている。例えば土台部分には近接センサーがある。カメラは2つ組み込まれている。顔である画面のベゼルには5メガピクセルのRGBカメラがあり、もう1つは驚くこと間違いなしだが頭の上から飛び出してくる。飛び出してくる方の12メガピクセルのRGBと赤外線のカメラは、ライブストリーミングのためのものだ。このカメラの土台は伸縮式で4フィート(約120センチ)の高さまで伸び、ロボットが周囲をよく見るための潜望鏡のような役割を果たす。

画像クレジット:Brian Heater
筆者はロボットや制作チームと1時間ほど一緒に過ごした結果、このチームが作ったものにかなり心をひかれた。もちろんどれほどの人がこれを所有することに関心を持つかはまったく別の問題だ。AmazonはAstroを「数千の」家庭でテストし、曲がり角で止まってしまうなどの不具合を解決したという。Day Oneプログラムはパブリックベータというよりは製品に対する顧客の関心を測定する手段だ。
トリッシュラー氏は次のように述べている。「私は、これは我々が取り組んでいるロボットシリーズの第1号だと思っています。これは招待制のみのプログラムです。家庭などいろいろな場所での難しさはあると思いますが、Astroを手に入れた人々がすばらしい体験をしてくれるよう願っています。長期的に消費者向けロボットを考えると、もちろんさまざまな価格帯や機能があり、その1つとしてわかりやすく主力となる製品が欲しいところです。しかしAstroは、我々が価値を作り出そうと開発当初から取り組んできたことを再確認し、我々のしてきたことが消費者にとって意味があると確かめる出発点としては良いものだと思います。2021年中にこの製品の出荷を開始し、フィードバックが寄せられることに期待しています」。
画像クレジット:Brian Heater
[原文へ]
(文:Brian Heater、翻訳:Kaori Koyama)





















































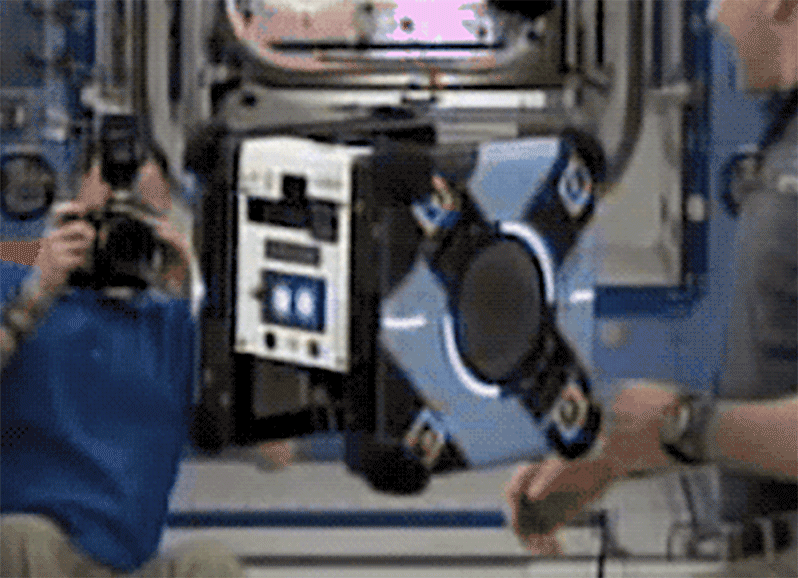










 もちろんドローンの下部に車輪を取り付けてもよかったわけだが、ベングリオン大学のチームのアイディアのほうがいくつも点で優れていた。まず第一に、ローターを駆動するモーターがそのまま車輪を駆動するのでメカニズムがはるかにシンプルで効率的だ。もちろん車輪駆動の場合にはローターの場合よりモーターの回転数を低くする必要があった。しかしアームを下向きに曲げる方式はホイールベースと地上最低高を大きくし、安定性と走破性をアップさせる。不整地を走行する場合に非常に有利になる。
もちろんドローンの下部に車輪を取り付けてもよかったわけだが、ベングリオン大学のチームのアイディアのほうがいくつも点で優れていた。まず第一に、ローターを駆動するモーターがそのまま車輪を駆動するのでメカニズムがはるかにシンプルで効率的だ。もちろん車輪駆動の場合にはローターの場合よりモーターの回転数を低くする必要があった。しかしアームを下向きに曲げる方式はホイールベースと地上最低高を大きくし、安定性と走破性をアップさせる。不整地を走行する場合に非常に有利になる。





 Walmartでは
Walmartでは