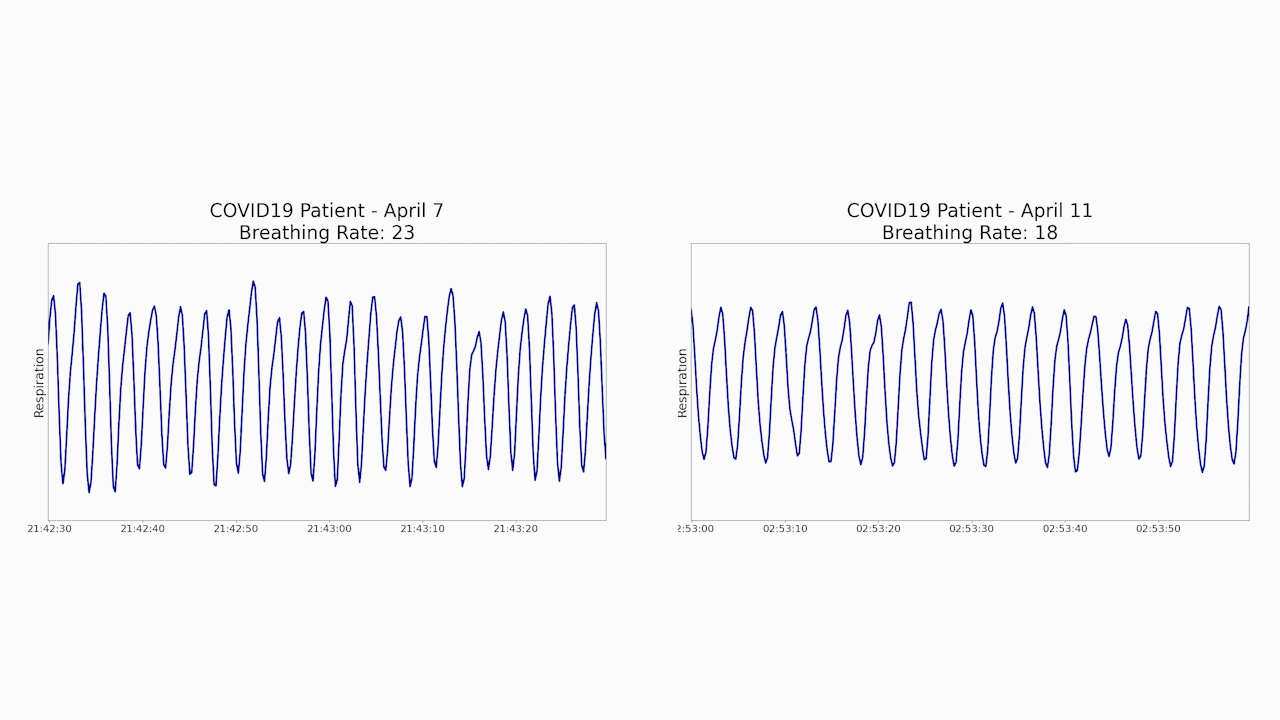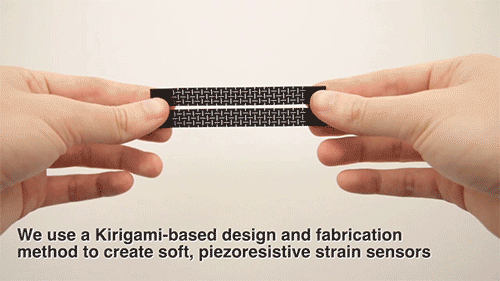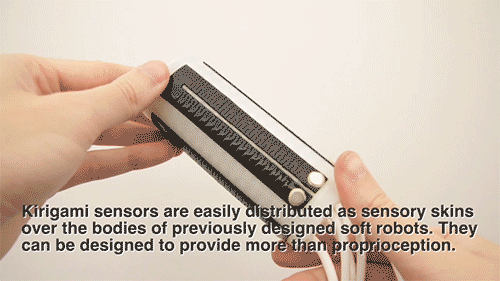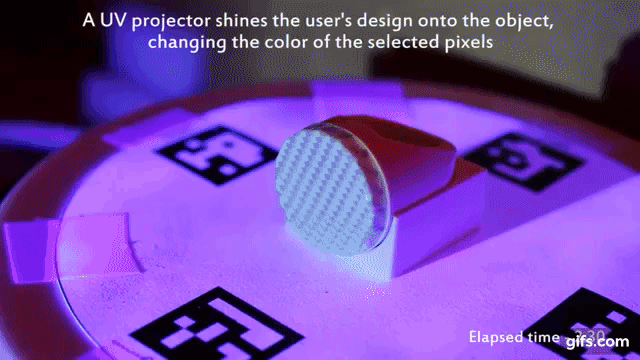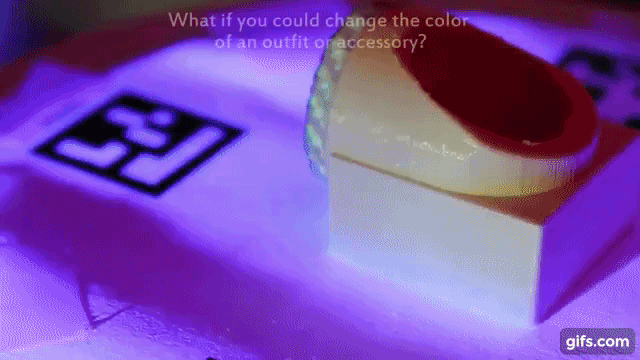自分の健康状態の全体像を把握するため、これからはApple Watchのようなデバイスを身につける必要はないかもしれない。MIT(マサチューセッツ工科大学)のコンピューター科学・人工知能研究所 (Computer Science and Artificial Intelligence Lab、CSAIL)の研究者が、ヘアドライヤー、ストーブ、電子レンジ、洗濯機などの家電製品がいつ、どこで使われているかを把握できる新しいシステムを開発した。研究者たちは、これらの情報を医療従事者に伝えることで、彼が介護を担当している人々の習慣や課題を知らせるのに役立つと信じている。
研究チームが考案した 「Sapple」 と呼ばれるシステムは、家に設置された2つのセンサーを使って、ストーブやヘアドライヤーなどの家電の使用パターンを測定する。位置センサーは、電磁波を利用して位置を特定し、ユーザーがその場所の境界を歩くだけでエリアをカバーするように調整できる。もう1つのセンサーは、家庭内のエネルギー使用量を測定し、そのデータを移動情報と組み合わせ、家で電化製品を使用しているときと、その使用時間を計測するため、エネルギー使用量と特定の人物の物理的位置とマッチングさせる。
研究者が「Sapple」と呼ぶそのシステムは、家の中に2つのセンサーを取り付け、デバイスの使用パターンを判定する。位置センサーはデバイスが発する電磁波からその場所を特定するが、検知範囲はユーザーが実際に歩くことによって指定できる。もう1つのセンサーは家全体のエネルギー消費を計測し、動きの情報と組み合わせてエネルギー利用のシグナルを人間の物理的な位置にマッチングし、家の中の誰かが器具を使っていることと、その使用時間を知る。
この方法では、スマートメーターなどを使う類似のシステムにある多くの問題を回避できる。家電にはそれぞれ特定の電力使用パターンがあるので、消費電力量によってどの家電が使われたのかはわかる。しかし、該当する家電がいつどのように使われたかを知るのは難しい。MITのシステムが提供する情報なら、医療従事者が患者が衛生に十分配慮しているか、食事を自分で作って食べているかなどを知ることができるわけだ。
このシステムにはプライバシーの落とし穴がたくさんありそうだが」、その使用目的が高齢者の介護など特定の用途に限られている。極めて省エネで、いま必要とされている疫病対策のための人と人の間の距離も維持できる。
IoTのスマートデバイスがまったく必要ない点でも巧妙なシステムで、単純なセンサーを2つ取り付けるだけなので、介護を受ける患者側に技術の知識も能力もいらない。
[原文へ]
(翻訳:iwatani、a.k.a. hiwa)