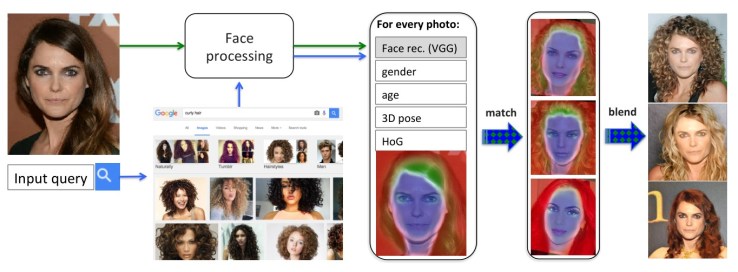飛ぶものを作ろうと思うと、いろんなトレードオフを克服しなければならない。大きければ燃料や電池を多く積めるが、しかし図体が大きすぎると必要な揚力が得られないかもしれない。小さければ必要な揚力も小さいが、小さすぎて必要な大きさの電池を詰めないかもしれない。昆虫サイズのドローンも、この問題に悩まされてきたが、しかしここでご紹介するRoboFlyは、レーザーの力で空に飛び立つ。
虫のように小さい空飛ぶロボットは前にもあったが、しかしRoboBeeなどのそれらは、ワイヤーをつけて電力を供給する必要があった。今の電池はどれも虫用には大きすぎる/重すぎるので、これまでのデモは、‘もっと大きくすれば…電池を積めれば…自力で飛べる’というものばかりだった。
でも、外部からワイヤーを使わずに電気を供給できたら、どうだろう? ワシントン大学のRoboFlyは、それに挑戦した。RoboBeeの精神を受け継いだ同機は、搭載した太陽電池セルとレーザーから動力を得る。

“重さを増やさずにRoboFlyに大量のパワーを素早く送るには、それがもっとも効率的な方法だった”、とペーパーの共著者Shyam Gollakotaが述べている。彼が電力効率をいちばん気にするのも当然だった。彼と仲間は先月、ビデオを従来より99%少ない電力で送信する方法を公開したばかりだ。
レーザーには、ロボットの翼を駆動するのに十分以上のパワーがある。正しい電圧に調節する回路があり、状況に応じてマイクロコントローラがパワーを翼に送る。こんなぐあいだ:
“ロボットの翼が素早く前へ羽ばたくために、一連のパルスを早い間隔で送り、その頂上近くになったらパルスを遅くする。それからまた逆方向に羽ばたいて別の方向へ行く”、とペーパーの主著者Johannes Jamesが説明している。
現状ではこのロボットは、とにかく離陸して、ごくわずかに飛行し、そして着陸するだけだ。でも昆虫ロボットをワイヤレス送電で飛ばせる概念実証としては、十分だ。次のステップは、オンボードのテレメトリー(遠隔測定)を改良して、自分をコントロールさせること。また、レーザーに操縦性を持たせて本物の虫を追わせ、その方向に向けて継続的にパワーを放射できるようにしなければならない。
チームは来週オーストラリアのブリスベンで行われるInternational Conference on Robotics and Automationで、RoboFlyをプレゼンする。
画像クレジット: Mark Stone/University of Washington