
さまざまなタイプのスタートアップが、さまざまな理由で失敗している。しかし、1つ変わらないことがある。それはスタートアップでの成功は、信じられないほど困難な仕事だということだ。会社を起ち上げて成功させることは、適切に人々を動かし、見つけることだけではない(もちろんどちらも重要だ)。この世界で成功するためには、無数の幸運の星が完璧に整列する必要がある。
2019年の「市場を去ったスタートアップ」をざっと見た限り、昨年、2018年のTheranos(セラノス)における大炎上のような派手なストーリーを持つ企業は見つからない。セラノスはベストセラー書籍やドキュメンタリー、ポッドキャストシリーズを生み出し、Adam McKay(アダム・マッケイ)氏とJennifer Lawrence(ジェニファー・ローレンス)氏の映画も近日公開される。ただし、MoviePassなどは近いとこまで行っているかもしれない。
どんな「セラノス」にも、有望な製品を擁する何十人もの勤勉なファウンダーがいて、ただただゴールテープを切れずにいる。さらに、どこがスタートアップで、どこがそうではないかにも議論の余地がある。ここでは、独立したスタートアップを対象にして、大企業で生まれたスピンアウトは含めないことにする。ただし、少なくとも1つ、廃業する前に大企業に買収されたスタートアップがある。
それでは本題に入ろう。2019年に店じまいしたスタートアップの中でも、特に大きくて興味深いものをいくつか紹介する。
調達総額:1.82億ドル(約200億円)

2013年、その若き有望なハードウェアスタートアップは新世代のスロットカー(溝のあるコースを走る模型自動車)をWWDC(Worldwide Developer Conference)の基調講演で披露した。新しい会社としてはかなりの栄誉だ。Appleは、iPhoneでOverdriveができることにより、その限界を押し広げたことに魅力を感じたに違いない。
3年後、Anki(アンキ)はCozmoを発売した。 その勇敢で小さなロボットは大々的な投資の賜物であり、元Pixarや元Dreamworksのアニメーターを雇い、ロボットの目に高度な感情を作り込んだ。2018年後半にはよく似ているが大人向けのロボットVectorを発売した。2019年4月、Ankiはそれまでに150万台のロボットと「数十万台」のCozmoモデルを販売していながら、会社をたたんだ。
調達総額:300万ドル(約3億3000万円)、2017年にフォードが買収

Chariot (チャリオット)はシャトルバスのスタートアップで、通勤用のワゴン車軍団で大量輸送を再発明しようとした。経路は「クラウドソーシング」による投票で決定することになっていた。
2年前にこのサービスを買収したフォードは、2019年初めには終了させた。フォードは詳しい内容には触れず、「今日の輸送業界景観と消費者や都市の需要と供給は急速に変化している」とだけ語った。
調達総額: 1.32億ドル(約145億円)

野心的で豊富な資金を得たARヘッドセットのスタートアップ、Daqri(ダクリ)は2019年9月に廃業し、在庫販売も完了した。大企業ユーザーの獲得に失敗したこの分野によく見られる会社の1つで、Magic LeapやMicrosoftなどのライバルとの競争にも敗れた。
一時、Daqriは将来のIPOに備えてある大規模な民間非公開株式投資会社と資金提供の交渉をしていたが、他のAR企業が直面する技術的課題が明らかになるにつれ、投資会社は手を引き交渉は決裂したとTechCrunchで報じた。悲しいかな、2019年に崩壊したAR企業はDaqriだけではない。
調達総額: 470万ドル(約5億1000万円)

HomeShare(ホームシェア)は、アパートの一室を分割した「マイクロルーム」のルームメイトをマッチングして急騰する住居費の問題に挑戦しようとした。同社によると3月時点で約1000人のアクティブな居住者がいた。
廃業にあたりHomeShareは、居住者に敷金は返却されないが、仕切りはそのまま持っていても、売ってもよいと語った。
調達総額:7270万ドル(約80億円)

AnkiとJibo(ジボ)を見れば、2019年はコンシューマー向けソーシャルロボットにとって苦難の年だったことがわかるだろう。もっとも、この分野にとってすばらしい年があったことはない。少なくとも今までは。最初のAiboの悲しい死と同じく、Jiboの最期は愛するロボットの友達が息を引き取るのを見るという、驚くほど気の滅入る人間性を強調するものだった。Jiboは、4月に「一緒にいられた時間を心から楽しんだことを伝えたい。近くに置いてくれたことを本当に心から感謝している」とユーザーに向けて語った。
Jiboが死んだのは厳密には2018年末だったが、あまりにもドラマチックな最期だったので例外を設けた。クラウドファンディングは成功し、ベンチャー資金も十分にあったにもかかわらず、終末はやってきた。会社はほとんどのスタッフを解雇するはめになった。
調達総額: 6870万ドル(約75億円)、2017年にHeliosとMathesonが買収
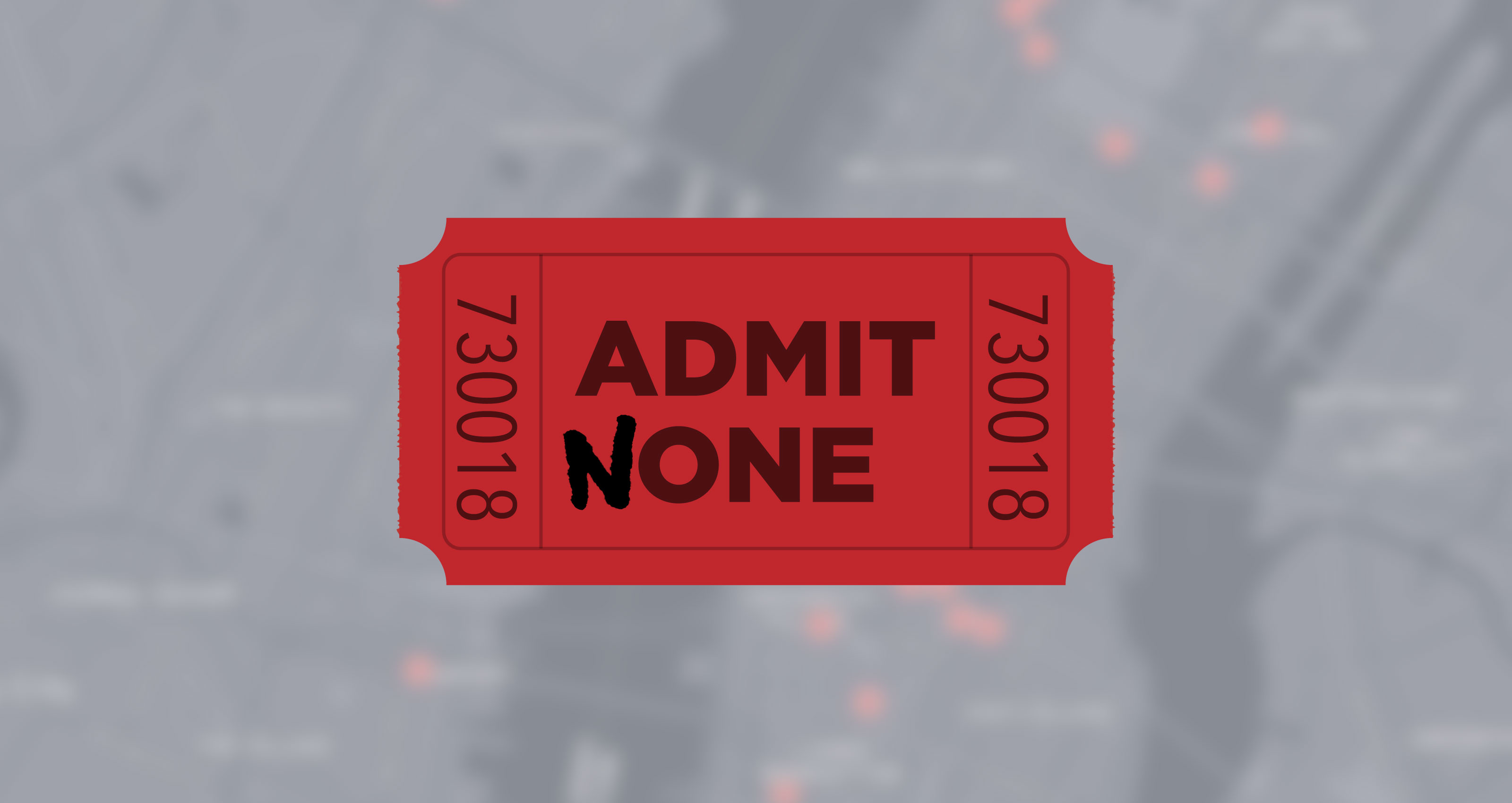
Image: Bryce Durbin / TechCrunch
なんともはや、こいつはどこから話を始めればいいのかもわからない。今回のリストを作っていたとき、あるテッククランチャーはMoviePass(ムービーパス)が潰れたのは何年も前だと言い張った。それは(一部の政治行事にも似て)チケット・サブスクリプションサービスの大規模な列車転覆事故がスローモーションのように何年にもわたって起きたように思えたからだった。 TechCrunhでも何度も何度も記事を掲載した。
実際、大惨事は毎週起きているように見えた。資金を垂れ流し、サービスを制限し、ダウンを繰り返し、さらに借金を余儀なくされたこの会社は一種のゾンビ状態に入り、大規模なデータ漏洩も起こした。そうそう、資金を投じたJohn Gotti(ジョン・ゴッティ)氏の映画はもっと酷かった。その結果、MoviePassの崩壊は慈悲深い行為のように感じた。
調達総額: 1.25億ドル(約137億円)
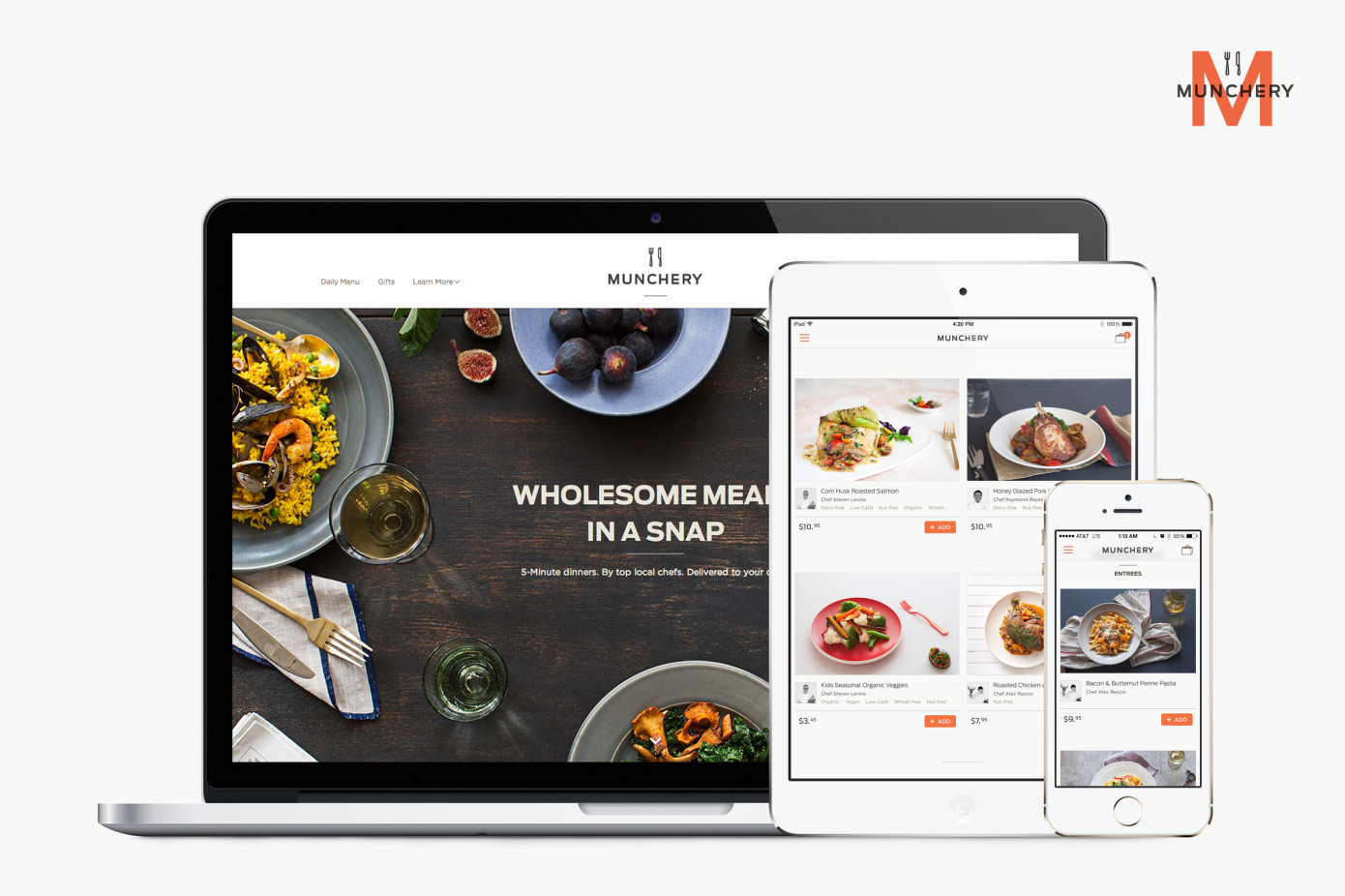
2019年最初のスタートアップスキャンダルには、かつてよく知られていたフードデリバリー会社、Munchery(マンチェリー)が関わっていた。同社が顧客に廃業が差し迫っていることを知らせるメールを送ったあと、契約メーカーの多くから糾弾された。Muncheryは終了寸前の時間を悪用し、支払うあてのない料理の配達を続けた。
同社による突然の崩壊をきっかけに、説明責任に関する議論が沸騰した。CEOと投資家が沈黙を続ける中、メーカーは説明を求めて泣き叫び、Muncheryの出資者の1つであるSherpa Capitalのオフィス前で回答と支払いを求める抗議運動まで起こした。
調達総額:14万5000ドル(約1600万円)

ベイエリアの調理器具スタートアップ、Nomiku(ノミク)は、12月に入って事業中止を発表した。同社は消費者向け真空調理器の分野を切り拓いたパイオニアだったが、市場がライバル製品の洪水になるのを見守ることになった。Kickstarterで複数のキャンペーンに成功して130万ドル(約1億4000万円)を集め、Samsung Venturesの出資を受け、レシピ事業への転換を図ったりもしたが、このスタートアップが生き残ることはできなかった。
「フードテック業界の様相は以前と大きく異なっている」とファウンダーでCEOのLisa Fetterman(リサ・フェッターマン)氏は、TechCrunchに語った。「フードテックとハードウェアがもっとホットで将来有望だった時期もあった。会社はいくつかの障害や課題を乗り越えることができると私は思っている。しかし、私の場合は破滅的な結果になってしまった」
調達総額: 5800万ドル(約63億円)

ARゴーグル分野のパイオニア、Osterhout Design Group(オステルハウト・デザイン・グループ、ODG)終了のニュースは1月第一週に訪れた。わずか数年前、この会社は5800万ドル(約63億円)の資金を調達した。それから1年もたたないうちに、同社は資金を燃やし尽くして社員に給料を払えなくなった。2018年初め、ODGは社員の半数を失い、社員に支払うための借金に走った。2019年初め、わずかに残った中心メンバーがFacebookとMagic Leapを含む大型IT企業数社による買収と特許の売却を待っていたが実現しなかった。
調達総額:3530万ドル(約39億円)

このスタートアップは物理的ストレージ会社としてスタートを切り、2019年5月にストレージ部門をライバルのClutter(クラッター)に売却して事業転換を図ったが失敗。リアル店舗が商品のレンタルと販売のビジネスを運用するためのソフトウェアプラットフォームを開発しようとしていた。
As part of the shutdown, roughly 10 Omni engineers were hired by Coinbase.
閉鎖にともない、約10人のOmni(オムニ)の技術者がCoinbaseに雇われた。
Scaled Inference (2014 – 2019)
調達総額: 1760万ドル(約19億円)

共にGoogle出身のOlcan Sercinoglu(オルカン・セルシノグル)氏とDmitry Lepikhin(ドミトリー・レピキン)氏が設立したScaled Inference(スケールド・インファレンス)は、2014年、Googleなどの企業が社内で利用しているものと同様の機械学習と人工知能技術を開発し、誰にでも使えるようにクラウドサービスで提供する計画を発表して話題を呼んだ。野望は大きくFelics VenturesやTencent、Khosla Venturesなどの投資家を呼び込んだ。
残念ながら同社は最近になって事業閉鎖を余儀なくされた。前CEOのセルシノグル氏はTechCrunchに、商品力の不足で資金調達ができなかったのが閉鎖の理由だと述べた。「最後の最後までいろいろな選択肢を探し、チームも維持してきたが良い結果は得られなかった。ここにいたるまでのプロセスを社内で可視化できたことはよかった」と同氏は語った。
調達総額:190万ドル(約1億1000万円)
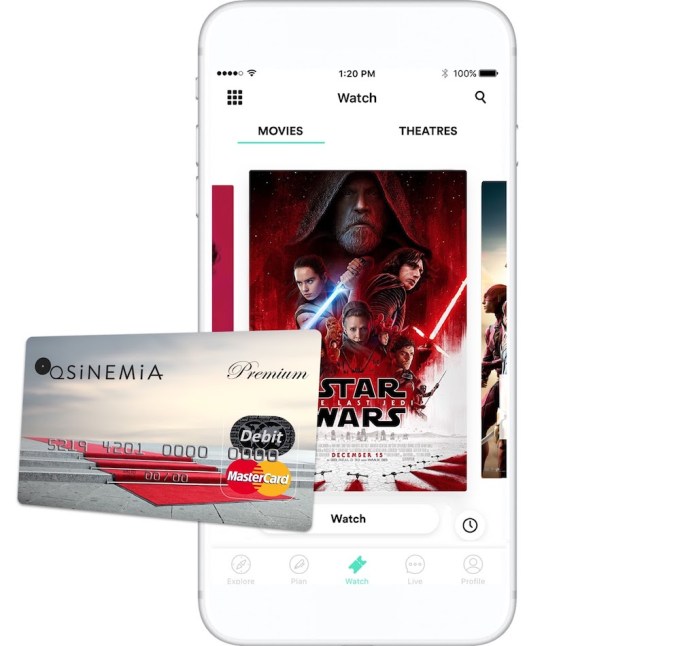
2019年はMoviePassスタイルのサブスクリプションサービス全般にとって厳しい1年だった。Sinemia(シナミーア)は最初の持続可能なライバルと見られていたが、アプリの問題や隠された費用、さらにはアカウント停止のポリシーにまつわるユーザーの苦情や訴訟に苦しめられていた。
そして4月、同社はアメリカでの事業終了を発表した。正確に表現すると、全事業を終了するとは言っていないが(スタッフの多くはトルコを拠点にしている)、同社はウェブサイトへはそれ以降、アクセスすることができない。
Unicorn Scooters (2018 – 2019)
調達総額:15万ドル(約1600万円)

Unicorn Scooters(ユニコーン・スクーター)は、2018年の熱狂的な電動スクーターブームで最初に死を迎えたスタートアップの1つだが、もちろん最後ではなかった。同社はFacebookとGoogleの広告に資金を投入しすぎたために、受注済みだった699ドル(約7万7000円)のスクーター300台以上の返金に充てる資金が残っていなかった。
あまり適切とはいえない名前のUnicornはY Combinator(Yコンビネータ)を卒業してからわずか数カ月後に会社をたたんだ。おそらくY Combinator出身者で最も速い卒業後の廃業だろう。「残念ながら広告費用は持続可能なビジネスを構築するには高すぎた」とUnicornのCEO Nick Evans(ニック・エバンス)氏が述べたとThe Vergeは報じた。「アメリカ全土で天候が寒くなったこと、そして他社のスクーターが数多く市場に出てきたことで、Unicornの販売はますます難しくなり、宣伝費がかさみ顧客は少なくなるという結果を招いた。
調達総額: 1500万ドル(約16億円)

via @VrealOfficial twitter
Vrealは野心的なゲームストリーミング・プラットフォームで、ライブストリーマーがプレイする世界をVRユーザーが探索できる仕組みの提供を目指していた。ユーザーはストリーマーの周辺をアバターになって散策したり、ストリーマーがゾンビを倒す音を聞きながらオブザーバーとして自ら探索することもできる。
「残念ながら、VR市場はみんなが期待したスピードで発展することはなかった。しかし、我々は間違いなく時代の先端を進んでいた」と同社はブログに書いた。「その結果、Vrealは事業を閉鎖し、我々のすばらしいチームメンバーは別の道へ進むことになった」という。
[原文へ]
(翻訳:Nob Takahashi / facebook)


