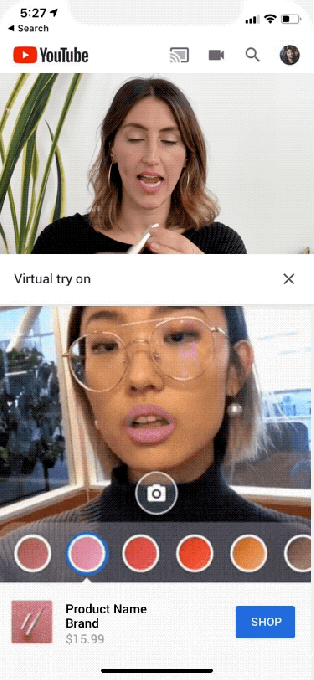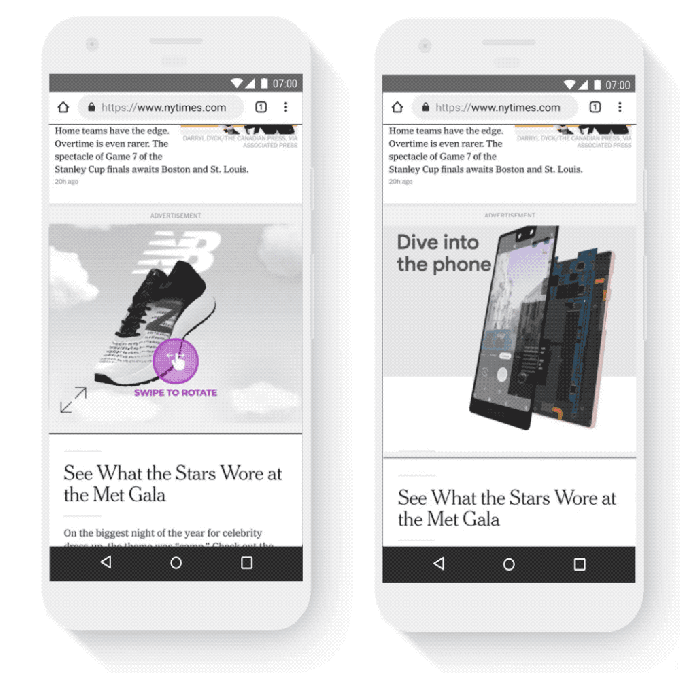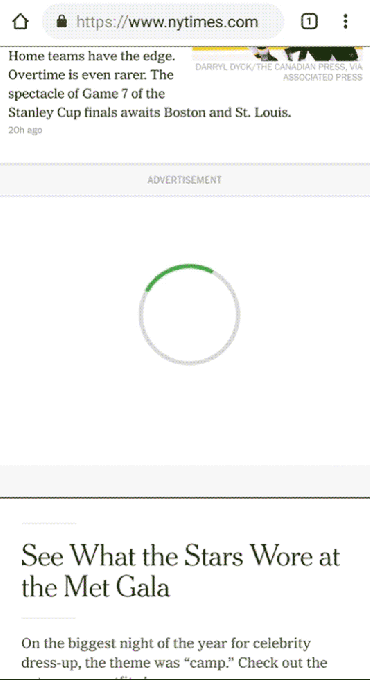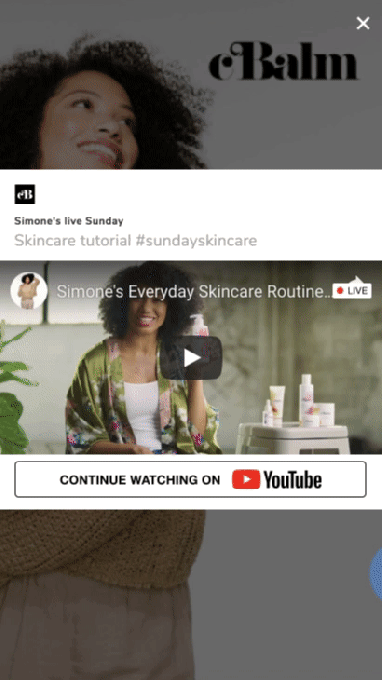ゲームのプレイヤー数が1億人を突破すれば、次は2倍の数を目指そうと思うのが自然な成り行き。それは、ゲームがそのまま商品カテゴリーにもなったMicrosoft(マイクロソフト)の「Minecraft」の開発者たち、というかむしろスチュワードも同じこと。このゲームは、さらなる大きな飛躍を遂げた。「ポケモンGO」の流れをくむ、拡張現実(AR)ゲーム「Minecraft Earth」(MCE)に進化したのだ。
米国時間5月18日に発表されたMCEは、iOS版とAndroid版の公式スタートが夏以降とのことだが、完全なMinecraftをモバイル用に、そしてARゲームとして再考したものだ。つまり、どういうこと? エグゼクティブプロデューサーJesse Merriamは、簡潔にこう説明している。「どこへ行ってもMinecraftがある。そしてどこへ行っても、Minecraftで遊べる」。
なるほど、で、どういうこと?もうちょっと詳しく言うと、MCEは他の現実をベースとしたARゲームと同じく、今いる場所の仮想版の中を歩き回り、アイテムを集めたりミニゲームに参加したりできるというものだ。他のARゲームと違うのは、Minecraft: Bedrock Editionが基礎になっているということ。派生版でも、課金を目的にした名前だけのインチキゲームでもない。本物のMinecraftだ。すべてのブロックが揃っていて、モンスターもいれば、レッドストーン回路も自由に作れる。ただそれが、ARになったというだけだ。アイテムを集めて、それを使って世界を作ってその小さなブロックの世界を友だちと共有できる。
このゲームでは、いくつかの楽しいチャンスが増えるのと同時に、ちょっと重要な制約が加えられる。そんなわけで、MCEがどんなゲームなのか、ざっと見ていこう。といっても、マイクロソフトはとてもケチんぼで、ゲーム内の大切な部分をなかなか見せてくれないので、言葉での説明になるけど。
もちろんマップがある
Minecraft Earthであるからには、現実世界の中の特別なMinecraftフィールドに暮らすことになる。ポケモンGoやハリー・ポッター:ウィザーズ・ユナイトと同じく、現実の街や風景の上にレイヤーを重ねるかたちだ。
もちろん外観はブロック状だが、目で見て何がなんだかわからないほどブロック化されているわけではない。地域、私有地、安全な場所、危険な場所などの注釈や推論情報が含まれたOpenStreetMapsデータを使用している。
この夢のマップの上にはタップできる物で満ちあふれている。そのままの表現だが、Tappable(タッパブル、タップできるもの)と呼ばれている。タッパブルはさまざまな形態を取ることができる。具体的には、チェスト、モブなどの形をした資源だ。
チェストにはブロックがたくさん入っていて、丸石やレンガなどに加えて、その他の種類のものも適度にレアな存在として現れる。

モブとは、Minecraftの自然の中で普通に出くわす、ブタやニワトリやイカなどの動物だ。アイテムと同じように取ることができる。モブにもレアなやつがいて、単なる飾りではないものもいる。開発チームは、彼らのお気に入りのモブを紹介していた。ひとつはMuddy pig(泥ブタ)だ。地面に置くと、何もないところで立ち止まり、ひたすら泥浴びをする。Cave Chiken(洞窟ニワトリ)は、タマゴの代わりにマッシュルームを産む。そう、繁殖が可能なのだ。
最後のタッパブルは冒険。資源を集めたり、モンスターと戦ったりできる小さなARインスタンスだ。たとえば、ときどき地面にひび割れがあり、そこを掘ると大量の溶岩が噴き出され、逃げなければならなくなる。溶岩が流れ出した跡には洞窟が現れ、その中でスケルトンが宝のチェストを守っているというような具合だ。こうした冒険を山ほど作ったと開発チームは話していた。
重要なのは、チェスト、Mod、冒険のいずれも、友だち同士で共有できるという点だ。私が見ているチェストは、みんなも見ることができる。そのチェストには、同じアイテムが入っている。冒険は、近くにいる人たちなら誰もが参加でき、みんなで協力して報酬を獲得することができる。
こうしたAR体験とあらゆる行動の土台となる「Build plate」(ビルドプレート)が、ゲームを輝かせている。
ARに関して
「Minecraft EarthをARなしでプレイしたければ、ゲームを止めるしかありません」と、このゲームのディレクターTorfi Olafssonは言う。このゲームのARはNianticのゲームと同様、オプションではない。ARネイティブなのだ。だから、スマートフォンを別の世界を覗き込む窓として使うのが、このゲームをプレイする唯一の方法となる。ただ、それが非常にうまく出来ているので安心できる。
まずは、ビルドプレートについて説明したい。アイテムやミニゲームで、どのようにMinecraftが構成されるのか疑問に思っていた人もいるだろう。構成はされていない。それらは生の素材に過ぎないのだ。
Minecraftで遊びたいと思ったら、開発チームがビルドプレートと呼ぶものを取り出す。これは特殊なアイテムで、テーブルや床などの現実世界の平面の上に仮想的に配置する平らな正方形だ。その上が、小さいながら完全な機能を持つMinecraftの世界となる。
この小さな世界の上に、なんでも好きなものが作れる。地面を掘って洞窟ニワトリのための地下宮殿や泥ブタの楽園を作ったりも自由自在だ。Minecraft自体がそうであるように、ビルドプレートも境界線がない。いや、この言い方は誤解を生むかな。実際、ビルドプレートには厳格な境界線がある。世界はビルドプレートの中だけに限定されるからだ。だが、その中は完全に自分の思い通りになる世界だ。
そこにも、通常のMinecraftのルールが存在する。これはMinecraft Liteとは違う。ただゲームの世界を小さくしただけだ。水も溶岩も物理法則に則って流れる。ブロックも、それぞれ素材に応じた性質を持ちModもごく普通に行動する。
このビルドプレートをミニサイズから実物大に変換したときに魔法が起きる。例えば、机の上で作った城を公園に持っていって3階建ての建造物にできる。廊下を歩けばブタたちは静かに私たちの存在に気付く。間違いなく自分が細部にこだわって作ったその内部に我ながら感心する。刺激的な体験だ。

本当はこんな風に見えるわけではないが、雰囲気だけでも感じとってほしい
他誌の記者といっしょに遊んだデモ版では、ビルドプレートをいくつか使って、実物大の冒険を体験した(正確には現実の4分の3のサイズだが、長さ1mのブロックにはちょっとばかり圧倒される)。それはまったくのカオスだった。みんながブロックを置いたり壊したり、水をあふれさせたり、ニワトリを置いたり。しかし、どれも正常に機能した。
これには、MicrosoftのAzure Spatial Anchorシステムが使われている。仮想空間内の自分の位置を素早く継続的に補正してくれる。更新は驚くほど早く、他のプレイヤーの位置と方向を、遅延なくリアルタイムで示してくれる。一方ゲームそのものは、その空間にしっかり固定される。そこに入って中を歩くときも滞りがない。バグも非常に少ない(それも起こっても仕方がない状況でのみ起きる)。このゲームがマルチプレイヤー体験を強く意識していることはうれしいニュースだ。
開発チームによれば、ARインスタンスとして同時に集まれるのは10人だという。技術的には無制限なのだが、冒険用に設定された舞台やテーブルの周囲など小さな空間に物理的に集まれる人数を考慮してのことだ。64人で大規模な襲撃なんてことは期待できないが、3人か4人の仲間とクモの大群を引き連れて歩くことは可能だ。
開発者の苦闘
開発チームは、これまでのMinecraftと同じ方法でこのゲームを作るにあたり、自然な流れとしていくつかの制限とリスクを設けた。例えば、高速道路の真ん中に冒険アイコンが現れても困る。
その目的のために、開発チームは長期間をかけて、きわめて強固なマップのメタデータを作り上げた。他人の家や庭に冒険が発生しないように。ただし、手で拾える簡単なアイテムは出現する可能性がある。70m先のものまで手が届くので、その人の玄関のドアをノックしてプールの中に洞窟ニワトリがいるので取らせてくれ、なんてお願いする必要はない。
さらに冒険は、道や到達困難な場所には現れないようになっている。例えば歩道や公園など、そこが一般に開放され地区であり、さらに安全で入りやすい場所であることをエンジンが認識できるようにするのに大変に苦労したと開発チームは話していた。
Nianticの『ハリー・ポッター:ウィザーズ・ユナイト』は、ポケモンGo世代の魔法バイキング(本文は英語)
もうひとつの制限は、ARゲームであるため、現実の世界を歩き回らなければならないことだ。しかし、Minecraftの命は仮想性だ。当然のことながら、現実世界にいる限り、仮想的に作られた階段を昇ったり、洞窟に潜ることはできない。プレイヤーである私たちは、二次元の平面上にいる。そこに関わることはできるのだが、その平面の上や下の空間を歩くのは不可能だ(だがビルドプレートには例外もある。ミニチュアモードのときは、スマホを動かして建物の周囲を自由に飛び回ることができる)。
自由に歩けない人には残念なのだが、それでもビルドプレートを回転させれば、別の面にアクセスできるようになる。武器も道具も有効距離は無限なので、遊びの邪魔になるものや障害物を取り除くことができる。
プレイヤーを飽きさせない要素は?
ポケモンGOには、プレイヤーを放さない誘因がある。ハリー・ポッター:ウィザーズ・ユナイトには物語や能力が発展する楽しみがある。Minecraft Earthの場合はどうだろう? そもそも、Minecraftの魅力とは何なのだろう?それは物を作ることだ。それが、スマホの中のARの世界でもできるようになった。
このゲームは物語を追うものではない。詳細は公表されていないもののキャラクターがある程度成長する機能はあるが、Minecraftの本来の遊び方は、物を使ったり作ったりすることだ。レゴで遊ぶのと同じように、ビルドプレートと永続性のある手持ちのアイテムが活気に満ちた砂場になってくれる。
たしかに、ポケモンほどの病みつきになるゲームには見えないかも知れないが、Minecraftが型破りなゲームであることは事実だ。数百万人ものプレイヤーが、物を作ったり、作った物を人に自慢するために、ずっとこれで遊んでいる。最初は、物を人に見せる方法に限りがあるが、将来的には人気の作品を見て回るための手段が提供されるはずだ。
しかし、これでどうやって儲けを出すのだろう?開発チームはこの質問に対して答えをはぐらかしたが、彼らは幸せなことに今はお金のことを心配しなくていい立場にある。Minecraftは歴史的な大ヒットゲームであり大きなドル箱なのだ。たぶん、Minecraftの世界に人々やコミュニティをつなぎとめるためのコストに見合うだけのものが、これにはあるのだろう。
私にとってMCEは素晴らしいものだが、このゲームには誰がどう言おうと、本質的に評価されるべき価値がある。スクリーンショットやゲーム中の動画を紹介できなかったため、それが伝わらないのはよくわかる。ここはひとつ、見た目も素晴らしいしプレイ感覚もよく、あらゆる年代にとって心底楽しめるものだという私の言葉を信じてもらうしかない。
その他、本題から外れた事実を列挙しておこう。対象地域は順次拡大されることになっているが、正式スタートの時点では、今のMinecraftと同じ対象地域で普通にプレイできるようになっているはずだ。
- スキンも使えるようになる(今のアカウントからスキンを読み込むことも可能にするとのこと)。
- ビルドプレートのサイズとタイプは数種類用意される。
- クラフトもできる。だが3×3のクラフト用グリッドがない(?)
- 荒らしを通報できるが、ゲームの構造上、荒らしが大きな問題になることは少ない。
- ARエンジンはポイントクラウドを生成し利用するが、寝室の写真を撮るようなことはしない。
- コンテンツはマップに動的に追加される。ホットスポットもあるが、寂しい場所ではプレイヤーがいるときにコンテンツで満たされるようになる。
- 当然、AR CoreとAR Kitが使われている。
- 少し前に見たMinecraftのHoloLens版は、「技術よりも気持ち」を優先させた前任者だ。
- 知的機能に困難を抱える子どもには冒険は怖すぎるかも。
- ビルドプレートのブロックを「フレンド」が盗むことができる(寄付もできる)。
- 面白そう?それならベータ版に登録しよう。
[原文へ]
(翻訳:金井哲夫)



 このハイブリッドポータブルゲームシステムは、マリオとルイージのカートに搭載されたカメラを利用して、画面上で一人称視点のレース体験を提供する。現在、このゲームを紹介するティザービデオが公開されている。
このハイブリッドポータブルゲームシステムは、マリオとルイージのカートに搭載されたカメラを利用して、画面上で一人称視点のレース体験を提供する。現在、このゲームを紹介するティザービデオが公開されている。 動画を見る限りでは、雪のレベルやピラニアプラントだらけのジャングルなど、現実世界の障害物とおなじみのキャラクターや環境を組み合わせて、箱から出してすぐにかなりリッチな体験ができるように見える。
動画を見る限りでは、雪のレベルやピラニアプラントだらけのジャングルなど、現実世界の障害物とおなじみのキャラクターや環境を組み合わせて、箱から出してすぐにかなりリッチな体験ができるように見える。