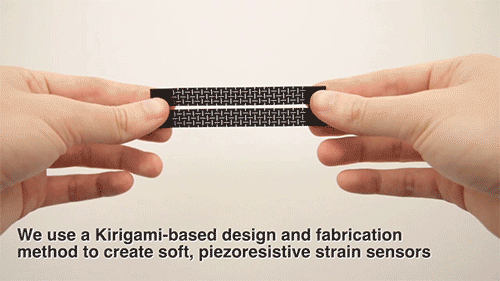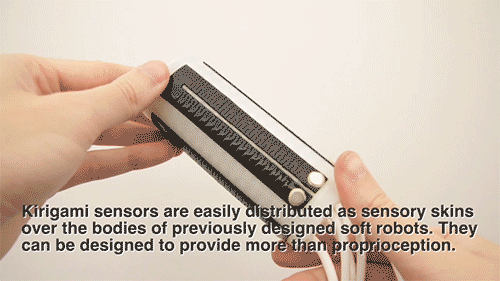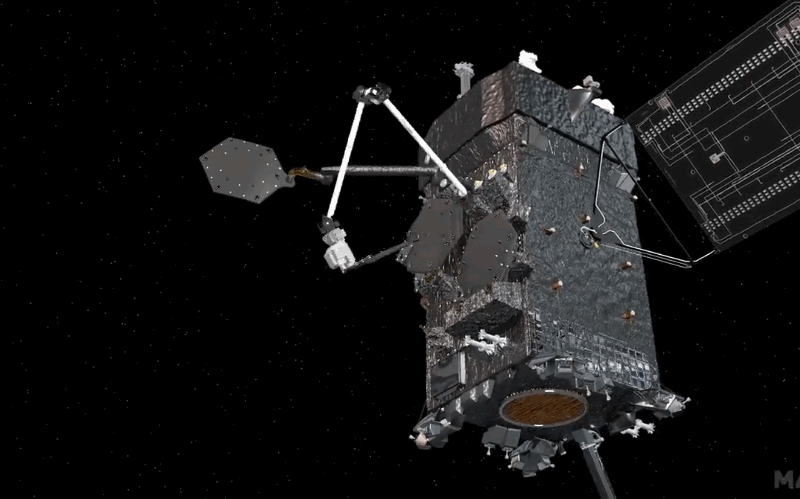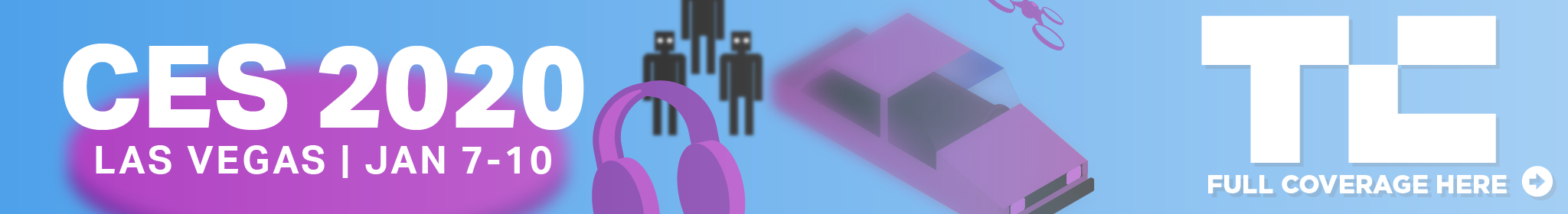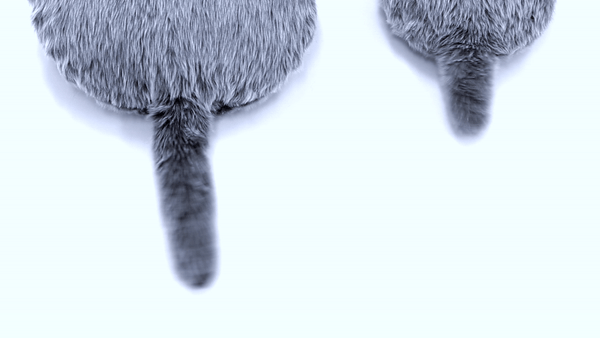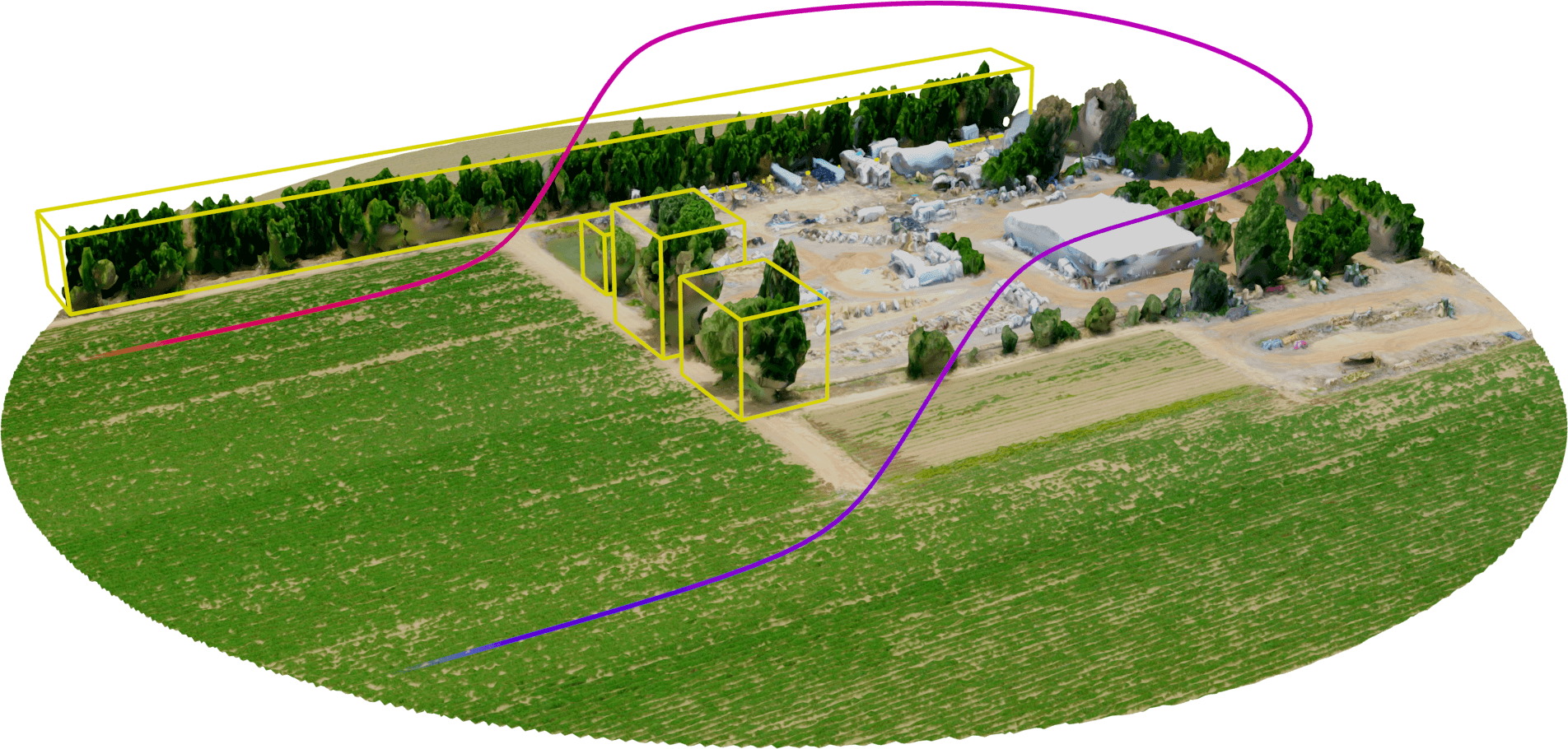新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックは、多くの企業が前進する手段として自動化に目を向ける中、ロボット工学にも大きな影響を与えるだろう。大規模な自動化は避けられないと以前から考えられてきたが、企業が人間的な要素を排除するプロセスを模索する中で、このパンデミックはその動きを加速させようとしている。
Locus Roboticsはこれまで、資金調達で大きな問題を抱えていなかった。米国マサチューセッツ州を拠点とするこのスタートアップは、昨年4月に2600万ドル(約28億円)を調達(未訳記事)しており、今回のシリーズDラウンドで4000万ドル(約43億円)を調達した。これで総額は1億500万ドル(約110億円)以上になる。Zebra Technologiesが主導した今回の最新ラウンドは、Locus Roboticsがヨーロッパ本社の立ち上げで事業を拡大しようとしている同社にとっては、非常に重要なものとなっている。
「今回の資金調達により、Locusはグローバル市場への展開を加速させることが可能になる」とCEOのRick Faulk(リック・フォーク)氏はリリースの中で述べている。「世界中の小売業、産業、ヘルスケア、3PL(サード・パーティー・ロジスティクス)事業が新型コロナウイルスのパンデミックを乗り切る上でのサポートを強固にし、より立場を強化することを保証する」。
Locusは、米国ではビンを運搬するロボットですでに好評を得ている。2月には、同社のロボットが1億ユニットのピッキングを達成したことが明らかになった。これは、ペンシルバニア州にあるDHLの施設での出来事だ。その翌月、DHLは2020年に同社のロボット1000台を配備することで合意。4月には、UPSが自社施設でLocusロボットを試験的に導入することを発表した。
[原文へ]
(翻訳:塚本直樹 Twitter)



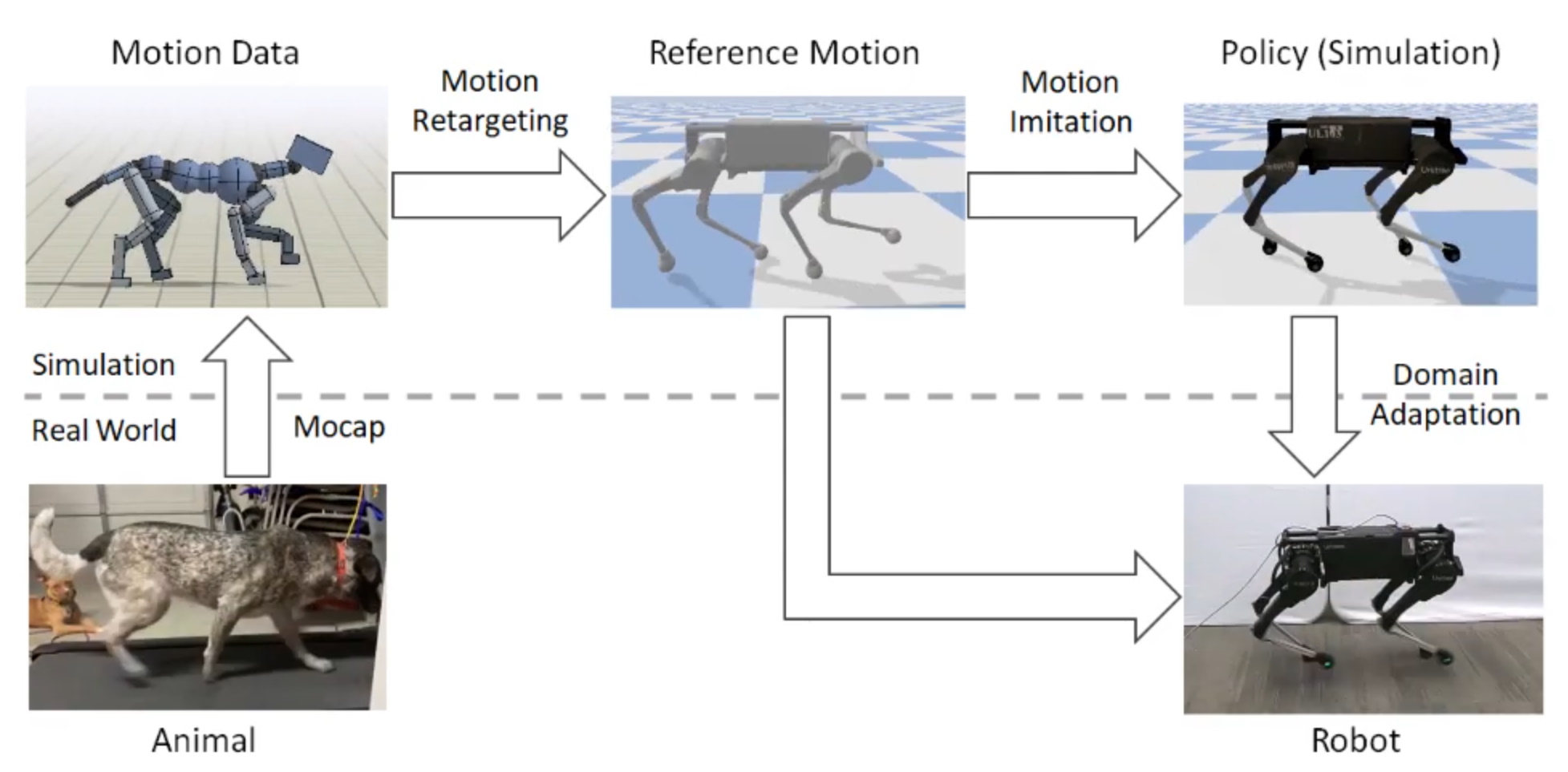
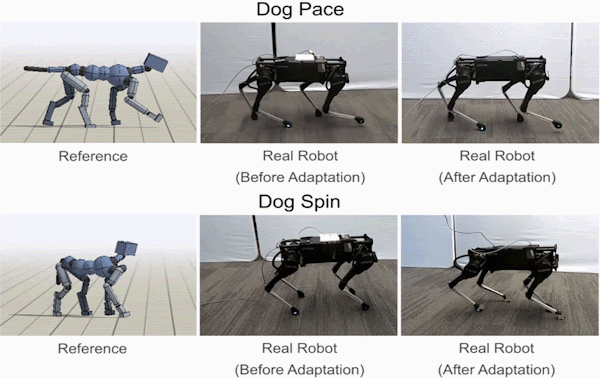



 三菱電機との提携のもと、現在のところ25万ドル(約2800万円)のシステムをデザインしている。サービスセンターやディーラー、その他のアウトレットに貸し付けることを想定し、パイロット事業では、早く試したい人のために、同社はタイヤ1本あたり5〜7ドル(約550〜780円)でサービスを提供する。最終的にプロダクトを本格展開するときには10〜15ドル(約1100〜1700円)になる見込みだ。
三菱電機との提携のもと、現在のところ25万ドル(約2800万円)のシステムをデザインしている。サービスセンターやディーラー、その他のアウトレットに貸し付けることを想定し、パイロット事業では、早く試したい人のために、同社はタイヤ1本あたり5〜7ドル(約550〜780円)でサービスを提供する。最終的にプロダクトを本格展開するときには10〜15ドル(約1100〜1700円)になる見込みだ。