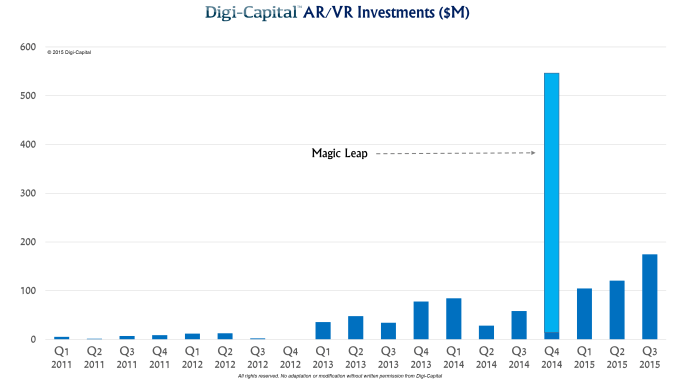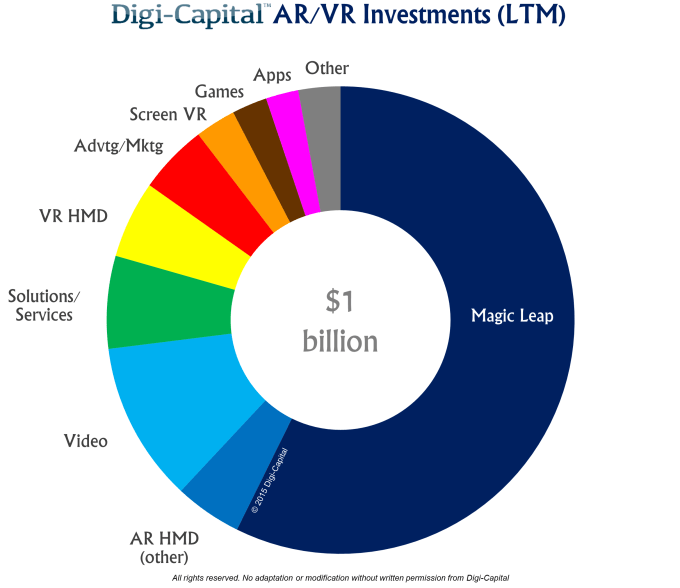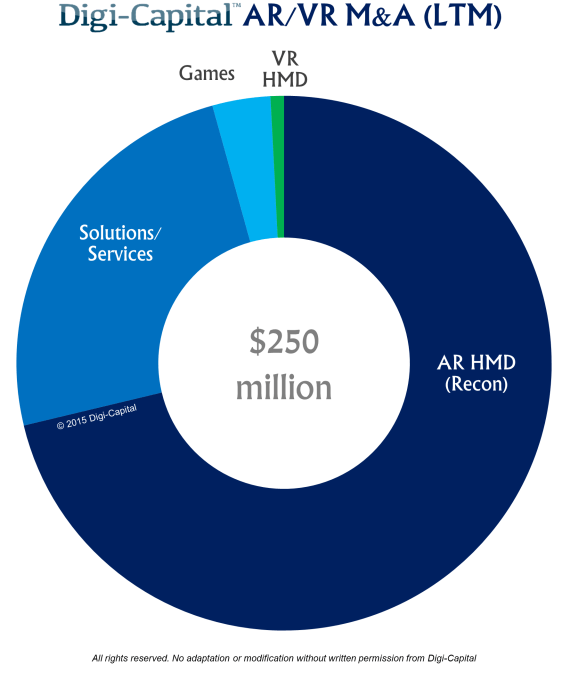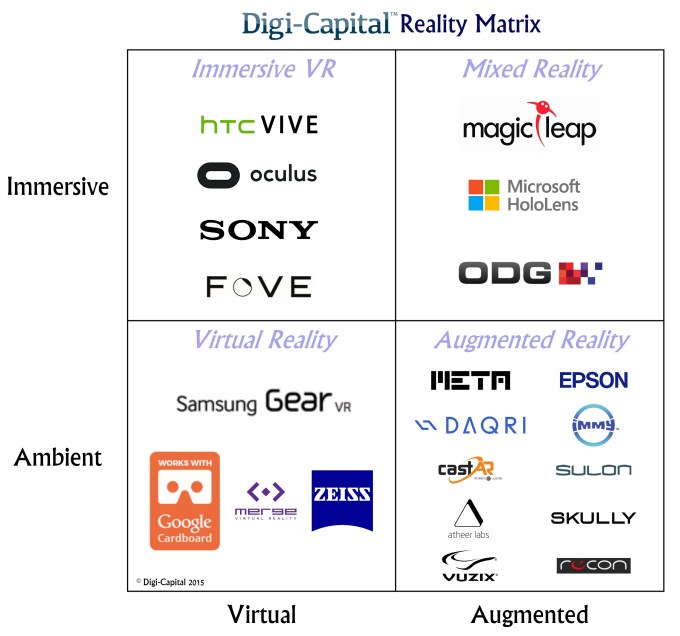リクルートホールディングが主催する日本最大級のWebアプリ開発コンテスト「Mashup Awards 」が11月に開催された。2006年に始まったこのコンテストは今年で11回目。8月20日から10月19日までに応募された431作品から12作品が11月17〜18日に開催された「TechCrunch Tokyo 2015」内のイベント「MashupBattle Final Stage」に登壇。サービスのプレゼンを繰り広げた。
MashupAwardsの審査基準は「アイデア」「完成度」「デザイン」の3つで、ビジネスモデルやマネタイズなどは評価の対象に入らない。「モノづくり自由型」というテーマで応募者が集まった決勝では、弓や天秤がでてきたり、ゲーム「ストリートファイター2」の対戦がはじまったり、ベッドをステージに置いて寝転がるとうなデモがはじまったりと、本当に自由な発想で作られた作品が発表された。
このレポートでは、決勝で発表された12作品の中から、上位3作品と、記者が個人的に面白いと感じた4作品の合計7作品を紹介する。
MashupBattle FinalStage(決勝)で発表された作品
最優秀賞「 参式電子弓 」: 本物の弓を使ったスタンドアローンARゲームシステム
コンセプトは「身体的没入感」。といってもVRのようにヘッドマウントディスプレイを装着して体験するようなプロダクトではない。本物のアーチェリーの弓に、コンピュータ、バッテリ、プロジェクタ、センサが入った、全方位対応のARシステムだ。内蔵したプロジェクタで弓を向けた方向の壁に疑似的なスクリーンを作ることで、周囲の360度すべてをAR空間にすることができるのだという。
(1)モノ感(2)世界が周囲に広がっている(3)仮想の能力=現実の能力—という3点をコンセプトを持っているそうで、実際に弓の弦を引いて矢を放つ動作をすると、仮想世界上に矢が飛んでいく。弦を引いた強さによって、矢の飛んでいく強さが変わり、実際の弓を扱っているのと同じ感触でゲームをプレイができる。また、弓の傾き(構え方)によって炎の矢やラピッドショットなども打ち方も変えられる。
第2位「 CliMix (クライミックス) 」: 漫画の各シーンの雰囲気に合わせて最適な曲を流す電子書籍アプリ
電子書籍での購読時に、漫画にマッチしたBGMを自動で再生し、読書体験をより盛り上げ、漫画への没入感を高めるアプリ。
BGM再生の仕組みは、漫画の書籍情報APIを利用してジャンル検索し、GracenoteAPIからジャンルに応じた曲を取得。そして、Spotifyからインストゥルメンタル曲を取得し、漫画にあったBGMを流すというもの。
クライマックスシーンの判定は、コマ中のセリフや人間の大きさなど、複合的に判断しスコアリング。クライマックスが来るタイミングに楽曲のサビが流れるように1ページをめくる時間を逆算してタイミングを調整している。クライマックスに音楽がどのように融合されるのかはこちらの動画をご覧いただきたい。
第3位「なりきり2.0 」:身振り手振りでものを操ったり、ゲームのキャラクターになりきったりできる作品
センサー、認識技術、WebAPIを組み合わせて、ゲームのキャラクターやヒーローに「なりきる」作品。例えば腕の動きを検出して電気をつけたり、TVのチャンネルを変えたり、手を振れば連動するゲームのキャラクターが稲妻を出したり——そんな世界を実現する。
腕時計型のウェアラブルデバイスを手足に装着し、モーションをリアルタイム検出。 機械学習を併用することで、多用な動作を認識可能にしている。デモでは家庭用ゲームのコントローラーをハックし、「ストリート・ファイター2」をなりきり 2.0で操作。仮想世界で手から稲妻を出す…ならぬ波動拳を出すというプレーを実現した。実際に対戦している様子は以下をご覧いただきたい。
インタラクティブ・デザイン部門賞「 gの天秤 」: 人間の価値を図る言葉の重さを図る天秤
リアルタイムに取得される検索ヒット数1件を1グラムに置き換え、ことばの重みをフィジカルな天秤の傾きによって視覚化した作品。仕組みはProcessingで作成し、言葉をGoogleでリアルタイム検索、皿の上にのったスマホに言葉とヒット数を表示している。 天秤の動きはラックアンドピニオン構造という造りによって音がなく有機的なゆらめきを実現している。(動画参照)
コンセプトは、「人間の価値を測ることのできる天秤」で、 左右の皿にのったスマホには人を評価する言葉と数字を表示。言葉は「イケメン」「性格がいい」など様々で、数字は語をGoogleで検索した時のヒット数。この作品では現代の情報の重みを計り、異なる価値観を一意に序列する現代の神が「Google」であると定義づけ、その検索結果を判断基準においた。
VIDEO おばかアプリ部門賞「 寝返りブロックくずし 」: 寝返りでプレイするブロック崩し
ベッドにシリコンキーボードを2枚並べて敷き、押した(というか寝返りを打った側の)キーの位置に応じてブロック崩しのバーが移動、そのバーでボールを打ち返すという「寝ゲー」。ブロック崩しを楽しむだけではなく、睡眠時のライフログを安価かつ高精度で取得するという狙いから生まれた作品だ。
ゲーム部分はenchant.jsを利用してJavaScriptで、キーボードのキー取得は別PC(Raspberry Pi)で行っている。複数キーボードのキー押下の情報を取得するために、libusbを使ってRubyプログラムでキー押下情報を取得し、node.jsのサーバを経由してsocket.ioでブラウザに渡している。
優秀賞「 PINCH 」: はさむ、かわかす、天気よむ。自動で洗濯物をはさむことができる洗濯バサミ
洗濯バサミにフォトリフレクタとサーボモーターを取り付け、洗濯物を近づけると自動で開き、挟むと閉じる優れもの。また、カゴに超音波センサーを着け、かごを近づけると自動で洗濯物が離されるので、面倒な洗濯干しが楽になる。
さらに、天気情報ともMashupしており、天気に応じてハンガーの周りにあるカーテンを自動で開閉したり、ゲリラ豪雨があった時などには、スマホから取り込み指示を遠隔操作できる。
Mashup部門賞「 Openness-adjustable Headset:開放度を調整可能なヘッドセット 」: モータ制御によりクローズ型とオープン型に変形可能なヘッドセット
クローズ型は没入できるが、外の音が聞こえない。オープン型は外の音が聞こえるが、音漏れがする——そんなヘッドフォン・ヘッドセットにまつわる課題を解決するのがこの作品だ。付属しているフタを、ボタンとスライドで開閉することで、クローズ型、オープン型2つのタイプのいいとこどりをしている。
開閉パターンは、タイマーを設定することで徐々にフタが閉まっていき、じわじわ没入するというパターン、音楽のサビが来た時に素早く閉まるパターン、自分の名前が呼ばれたらオープンになるパターンなどさまざま。また、聴きたくない番組をシャットアウトする放送局ブロック機能や、素早く動くと開く(自転車対策)などの遊び心あふれる機能も搭載。こちらの動画をみていただくとより分かりやすい。
VIDEO 決勝では合計12作品が発表されたが、そのうちの7作品を紹介した。残り5作品も、電気刺激で心の叫びを強制的に言語化するデバイス や、靴の中敷きデバイスをつかったIoT鬼ごっこ など、今回紹介した作品に劣らず面白いアイデアがつまっているので、是非Mashup Awards公式ブログ を参照いただければと思う。
クリエイターの技術とアイデアの祭典
MashupAwardsはクリエイターのお祭り。冒頭にも書いたが、審査基準に「ビジネスモデル」や「マネタイズ」は関係ない。2015年のテーマは「モノづくり自由型」とし、クリエイターの作りたいものを作ってほしいという想いから、さらに自由度を許容している。
企業の中にいると、事業性やマーケット需要といった話になりがちで、画期的なアイデアはなかなか生まれないように思う。起業家を対象としたイベントも、事業性がないと高い評価は得られないケースが多いため、突き抜けた発想だけで勝負をするのは難しい。
だが、MashupAwardsは審査基準に「事業性」という点が入っていないため、発想に制限がなく「おもしろいアイデア」「未来を先取りするようなサービス」が生み出される可能性がとても高いイベントになっているように思う。
面白いアイデアを思いついたけれど、事業性がないな…といったアイデアがあれば、まずは作り、MashupAwardsに応募してみるといいと思う。自分では思いつかなかった何かを発見できるかもしれないし、仲間が見つかるかもしれない。また、アイデアが事業に繋がるきっけに出会うかもしれない。MashupAwardsをきっかけに人生が変わった人は多い(今回、審査員で参加した、はてな代表取締役社長の栗栖義臣氏もMA2の受賞者とのこと)。
作らされているのではなく、作りたいものを作っている作品の発表は、とにかく見ていて面白い。今年見ることができなかった人は、是非来年は会場に来て、生のプレゼンテーションを見ていただきたい。