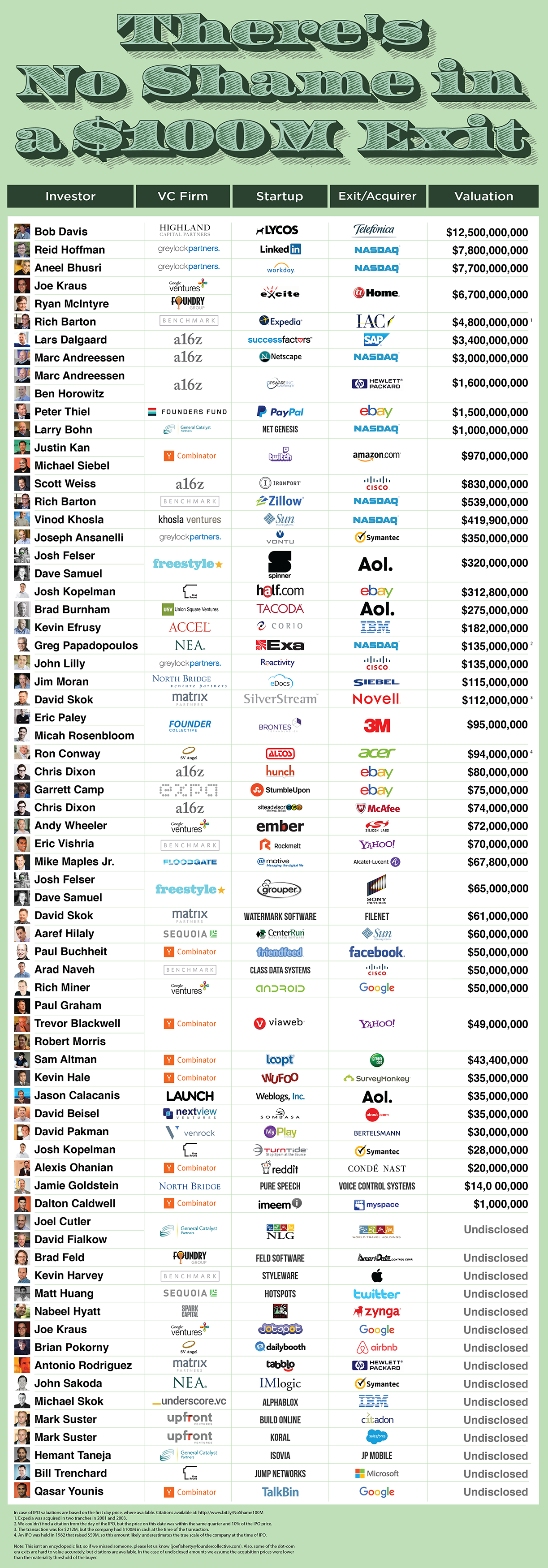私たちは2017年のことを、”ブロックチェーンが爆発的に発展した年”と記憶するのかもしれない。
多くの人々に受け入れられて十分に発展するまでに長らくの時間を要したビットコインなどの暗号通貨。その多くは今、史上最高値を更新している。さらに、イーサリアムなどの新しいプラットフォームが誕生し、世界最大級の企業もこの技術を利用するようになった今、ブロックチェーン技術が成熟する準備は整ったのかもしれない。
そのことを何よりも明確に表しているのが、ブロックチェーン・コンソーシアムを運営するR3が発表したばかりの新たな資金調達だ。今回の資金調達で1億700万ドルを手に入れたR3のコンソーシアムは、世界中の金融機関やテクノロジー企業が参加する団体だ。
R3が発表したプレスリリースによれば、本ラウンドをリードしたのはSBIグループで、その他にもBank of America、Merrill Lynch、HSBC、Intel、Temasekなどが出資に参加している。
世界中の金融機関が参加するR3コンソーシアムでは、ブロックチェーン技術の根幹ともいえる分散型台帳技術(DLT)をビジネスへ適用する方法を模索している。
調達金額の大部分を出資した金融業界のビッグネームたちの他にも、ING、Banco Bradesco、Itaü Unibanco、Natixis、Barclays、UBS、Wells Fargoなども今回の出資に参加している。
コンソーシアムの参加企業から合計で2億ドルを調達することを目指し、今回その第1弾を実施したR3は、ブロックチェーン技術のメインストリーム化を推進する旗手のような存在だ。
実際、R3はすでにシンガポール政府やカナダ中央銀行などの国営金融機関を顧客として獲得している。
同社は今回調達した資金を利用して、テクノロジー開発の加速と戦略的パートナーの拡大を目指すとしている。R3は独自の台帳技術を保有しており、その技術を利用して新しいアプリケーションを開発することができる。また、それにより金融機関などの企業が台帳技術をベースとした独自のアプリケーションやサービスを開発することが可能だ。
”まだ幼少期とも呼べる段階ではありますが、分散型台帳技術が誕生したタイミングは、金融機関が新しい技術を受け入れて効率性を手に入れるための体制を整えたタイミングと重なっています”と話すのは、Wells Fargo Securitiesでマネージングディレクターなどを務めるC. Thomas Richardson氏だ。
R3コンソーシアムに参加する他の金融機関のメンバーも、彼と同じような感想を述べている。
BarclaysのマネージングディレクターであるAndrew Challis氏は、「デジタル技術におけるイノベーションによって銀行ビジネスは生まれ変わりつつあります。今回の出資は、分散型台帳技術やスマートコントラクトが金融マーケットのインフラストラクチャーを大いに強化する可能性があると私たちが信じている証拠です。R3のコラボレーティブなアプローチは、この技術が発展するための鍵となるものです」と語る。
すべての金融機関がR3を受け入れているわけではない。Goldman SachsとSantanderの両社はこのコンソーシアムから脱退している。おそらく、彼ら自身のやり方で事を進めたかったのだろう。
R3の特筆すべき功績とは、政府にブロックチェーンベースのアプリケーションを受け入れさせたことだ。銀行や他の金融機関をプロジェクトに参加させるという彼らのアプローチは、より破壊的な考え方をもつビットコイン開発者のアプローチとは大きく異なっている。
多くの投資家や起業家たちが考えるように、コミュニティによって開発され、プライベートな性質をもつビットコインやイーサリアムのようなブロックチェーン技術と、R3などが中心となって開発する台帳技術の両方が入り込むスペースはこのマーケットにはまだ残されている。
今のところ、R3がフォーカスするのは台帳技術のビジネスへの応用だ。銀行間取引の認証や、ロンドン銀行間取引金利のオートメーション化などがそれに含まれる。
将来的には、コンシューマー向けマーケットでもR3の技術が直接的に利用される可能性がある――デジタルな不換紙幣を通して。
それが実現するまでには、まだ時間がかかるかもしれない。でも、R3が銀行や政府機関などと手を組んでいることを考えれば、それは遠い将来の話ではないだろう。
[原文]