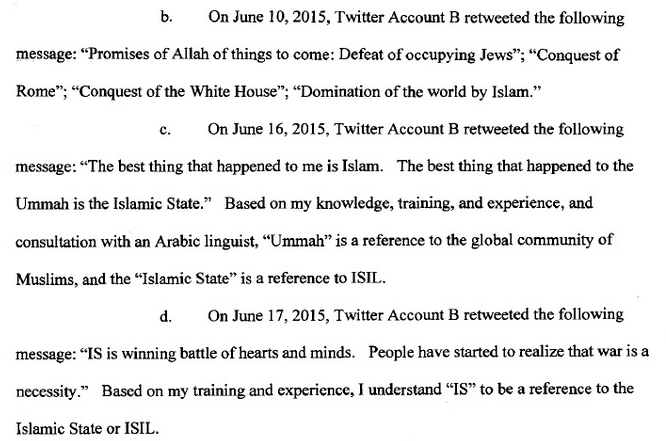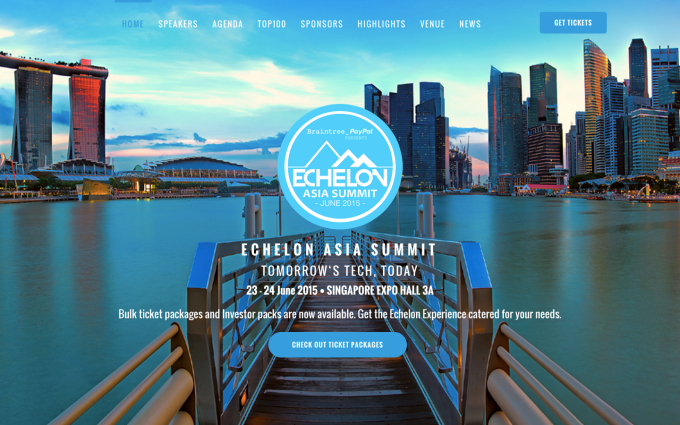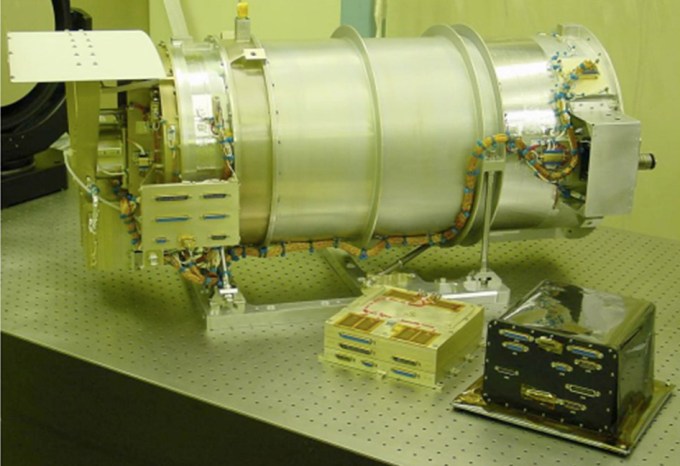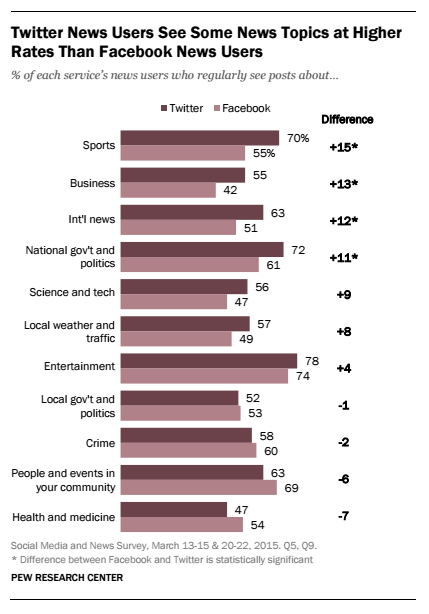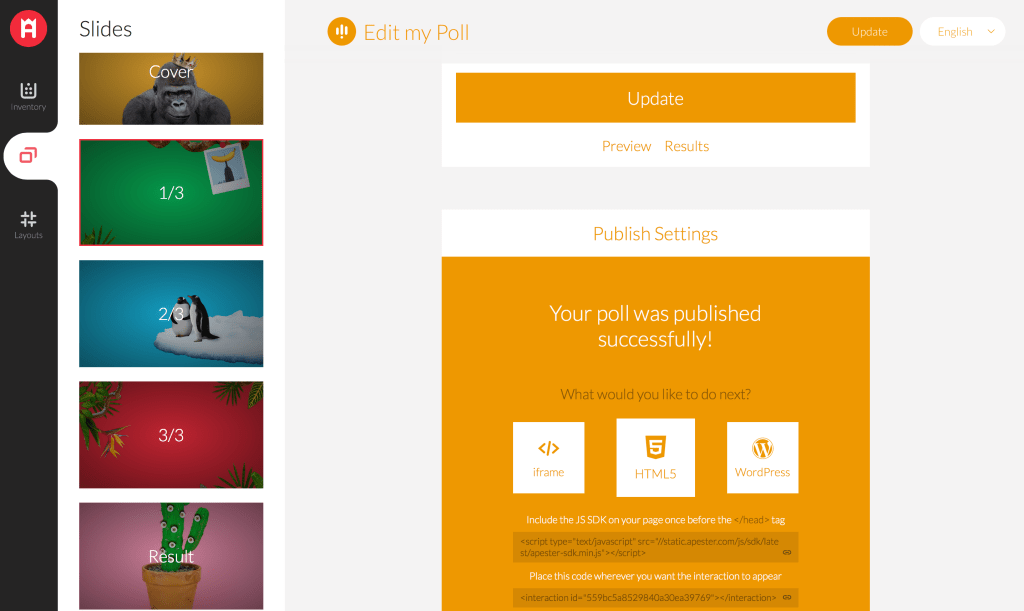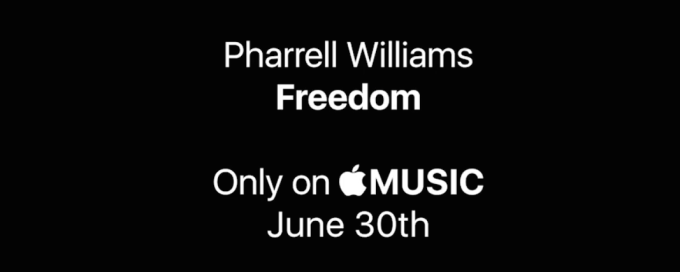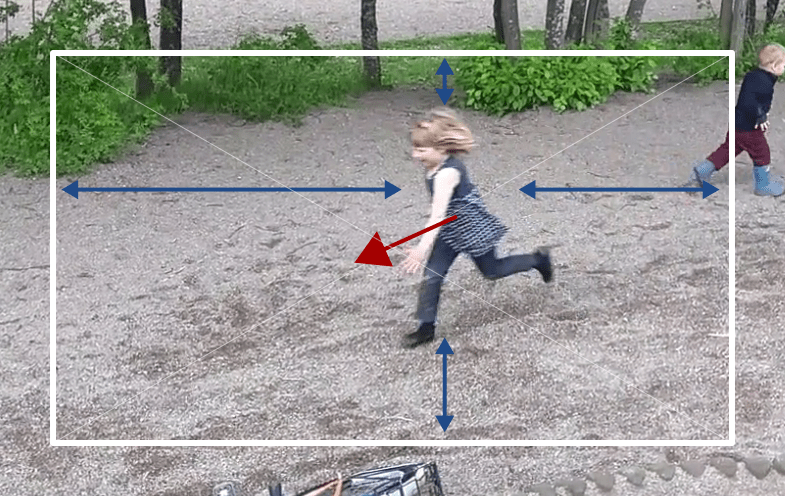アトコレ(現:マイナースタジオ)の石田健氏(中央)、サムライインキュベートの榊原健太郎氏(右)、玉木諒氏(左)
2011年9月に設立された学生スタートアップのアトコレ(9月に社名をマイナースタジオに変更)。同社をメンバーズが買収することが明らかになった。買収額は非公開。関係者によると数億円程度になるという。
創業間もなくメンバーが会社を離れることに
同社は創業時にはサムライインキュベートからシードマネーを調達。アート作品に特化したまとめサイト「みんなの美術館 アトコレ(現:MUSEY)」を提供していた。だが1年ほど経った頃、当時の代表をはじめとしたメンバーが会社を離れ、サービスを企画した石田健氏だけが代表取締役として会社に残ることとなった。ちなみに当時の代表は、現在クラウドソーシングサービス運営のクラウドワークス取締役副社長兼COOを務める成田修造氏。ほかのメンバーは、女性向けメディア「MERY」運営のペロリ代表取締役・中川綾太郎氏、同社取締役の河合真吾氏。それぞれ新しい場所で活躍をしている。
創業から間もないタイミングでの挫折。「みんなで『互いのキャラが濃すぎるとダメなのか』ということまで話し合った。個人的な視点だが、オペレーションを回すのが得意な人間や市場の方向性に明るい人間がいて個性も違う。一方で僕は研究員をやりたいようなタイプ。みんながひと通り事業を経験した今ならまた違うのかも知れないが、それぞれの(事業への)体重のかけ方が違っていた」——石田氏は当時をそう振り返る。
結局アトコレは石田氏を残して実質的に活動を停止。石田氏も大学院に進学し、その一方で個人プロジェクトとしてニュース解説メディア「The New Classic」をスタートした。この反響が大きかったことからサービスをアトコレに移管して運営することになったが、「広告で月の売上が数十万円程度、それ以外は2年間ほとんど何もしていなかった」(石田氏)のだという。
サムライ榊原氏「環境をリセットしてもう一度挑戦を」
そんな状況だが、石田氏には会社をたたむという選択肢はなかった。「当時は学生起業ブーム。だからといって『学生は勝手』と言われるようなことはしたくなかった。榊原さん(株主であるサムライインキュベートの代表取締役・榊原健太郎氏)にも『自由にやりなよ』と言われたので、すぐにではなくても、勝負できるマーケットを見つけて結果を出そうと思った」(石田氏)。榊原氏も当時を振り返って「全員環境をリセットして、もう一度挑戦してもらうべきだと思った」と語る。
一念発起したのは2014年の春。新たに社内にメンバーを迎え、メディア事業を強化。おでかけをテーマにしたキュレーションメディア「Banq」をはじめとした複数の特化型メディアを立ち上げた。Banq、THE NEW CLSSICは、それぞれ現在MAU(月間アクティブユーザー)数百万人のサイトに成長している。

「Banq」のスクリーンショット
メディア運営を通じて、オウンドメディアの運用支援事業にも進出した。「単純にコンテンツを作って納品するのではなく、メディア運営ノウハウをもとにSEOなども支援する。ライターに価値に置くよりも、コンバージョンに価値を置いたメディア作りをしている」(石田氏)。売上高などは非公開だが、メディア運営とオウンドメディア運用支援で黒字化は達成しているという。
アトコレでは、メンバーズの買収に合わせて社名をマイナースタジオに変更している。今後はメンバーズのクライアントをターゲットにしたオウンドメディア運用支援・コンテンツマーケティングを行うほか、新たにインバウンド向けのメディアを立ち上げる予定だという。「Banqはただのキュレーションメディアに見えるかもしれないが、実は裏側で各記事にスポット情報が紐付いている。このスポット情報を生かして、新しい『シティガイド』を作っていきたい」(石田氏)