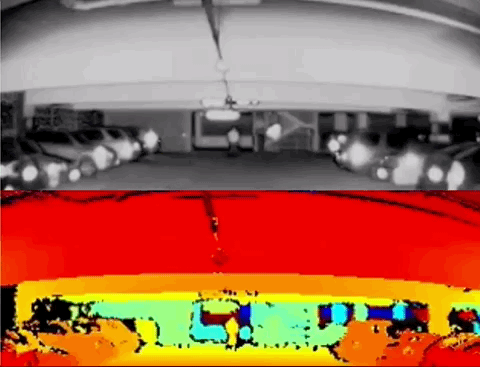考古学は、最新テクノロジーとは縁遠い分野のように思われる。AIやロボットは、実地調査の過酷な現場ではまだ心もとない。しかし、ライダー(Lidar)は画期的な技術であることが実証された。とは言え、数千平方キロメートルにおよぶ古代の数百万都市を、レーザーを使った画像化処理技術でマッピングするという最新の調査で、やはり経験と眼識にとって代わるものはないことを、研究者たちは実感した。
Pecunamライダー・イニシアチブは2年前に発足した。研究者と地元自治体が手を組み、グアテマラで長年研究対象となってきた保護区域での最大級の調査を行うことを目的にしている。この調査では、ペテン県マヤ生物圏保護区の、およそ2144平方キロメートルがスキャンされたが、その周辺の、開発されて人が住んでいる地域や、その他の重要と思われる場所もこれに含まれている。
プロジェクトの成功を示す試験的な画像とデータが、今年の初めに発表されたが、研究者たちはその後、本格的なデータ解析を行い、その広範にわたる結果を要約した論文をScienceに掲載した。

イニシアチブが調査した区域。見てわかるとおり、国の5分の1にも及んでいる。
「これほど広範囲な古代の風景を一度に見ることは、これまで不可能でした。このようなデータセットは存在しなかったのです。2月の段階では解析は、実際の量的な意味において、まだひとつも行われていませんでした」と、共同著者でチューレン大学のFrancisco Estrada-Belliは私に話してくれた。彼は、チューレン大学で、Marcello Canutoを含む他の同僚研究者たちとプロジェクトを進めている。「基本的に私たちは、不規則に広がる巨大な都市圏と、農業に関する広大な地物を発見したと発表しました。それから9カ月におよぶ作業で、そのすべてを数量化し、私たちが得た痕跡の一部を、数値的に確認しました」
「私たちの主張がすべて正しかったと知るのは、嬉しいことです」と彼は言う。「一部には、誇張して伝わっていたようですが」
ライダーのデータは無人運転車両で集められたわけではない。聞いた限りでは、たった1台の車で行われている。ドローンすらなく、普通の飛行機が使われた。非効率なように思われるだろうが、調査区域の広さと地形の事情のために、それ以外の方法はとれなかったのだ。
「ドローンは使い物にならなかったでしょう。あれだけの範囲をドローンでカバーするのは不可能です」とEstrada-Belliは説明する。「私たちは、テキサスから飛んできた双発の飛行機を使いました」
飛行機は、ひとつの「ポリゴン」、つまり、おそらく長さ30キロメートル、幅20キロメートルの区画の上空を何十回と飛行している。機体の下部には「多波長、多チャンネル、多スペクトル、狭パルス幅ライダーシステム、Teledyne Optech Titan製Titan」が装備されている。読んで字の如しの装置で、冷蔵庫ほどもある大型の極めて頑丈な機械だ。森の木々を透かして地面の映像を撮影するには、これだけのシステムが必要になる。
何枚もの重複する画像をつなぎ合わせ、補正して、1枚の驚くほど高精細な地面のデジタル画像が作られた。

「私が、それこそ何百回も歩いていた場所の地物を特定してくれたんです」と彼は笑う。「大きな土手道のようなところで、その上を歩いていたのです。しかし、とてもわかりづらい。大量の下生えやら樹木やらで覆われている。つまりジャングルですよ。あと20年歩いていても、気が付かなかったでしょうね」
しかし、そうした構造物は自動的に発見されるわけではない。3Dモデルを見ただけで「これはピラミッド、これは壁」などと具合に識別できるコンピューター・ラベリング・システムは存在しない。それは、考古学者にのみ可能な作業だ。
「実際には、地表データの手作業から始めます」とEstrada-Belliは言う。「私たちは、自然の地形の地表モデルを作りました。画像の中のピクセルは、基本的に高度情報です。そして、いろいろな方向から光をあてて起伏を強調させる照明をシミュレートするフィルターを何重にもかけて、その画像を半透明にして、いろいろな方法を使ってシャープにしたり強調したりして、つなぎ合わせていきました。長時間コンピューターの画面を見つめるという作業を終えた後、それをデジタイズします」
「最初のステップは、視覚的に地物を特定することです。もちろん、ピラミッドはすぐにわかりますが、微妙な地物もあります。識別できたとしても、それがなんであるか、わからないのです」

ライダーの画像から、たとえば、低い線上構造物が浮かび上がる。それは人工物であるかも知れないし、天然の地形かも知れない。それを見分けるのはとても難しいが、周囲の状況や学者としての知識がそれを補う。
「そして、すべての地物をデジタイズする作業に移りました。全部で6万1000個の構造物があります。すべてを手作業で行わなければなりません」とEstrada-Belli。なぜ9カ月もかかったのかと疑問に思われた方のために、彼はこう説明している。「デジタイズは経験に基づいて行われる作業なので、自動化はできないのです。AIにも期待しました。近い将来、それを利用できるときが来るでしょうが、今は経験を積んだ考古学者の目のほうが、コンピューターよりも確実に地物を見分けることができます」
注釈の密度がマップから見てとれると思う。その地物の多くは、今の時点で現地調査によって確認されたものであることに注目して欲しい。既存の地図を見ながら、人間が実際にその土地に行く。そして、その地物が錯覚であったり、期待の産物であったりしないことを確認する。「すべてはそこに存在していると、私たちは確信を持っています」と彼は言う。
-
pyramid_lidar
-
pyramid_uncovered
-
temple_real
-
temple_lidar
-
flightlines
「次のステップは数量化です」と彼は説明を続ける。「長さと面積を測定して、ひとつにまとめます。それを、普通にデータセットの解析を行うときと同じように、解析します。地域ごとの構造物の密度、都市や畑の広がりなどです。さらに、農産物の収穫量を推測する方法も編み出しました」
そこが、画像が単なる点の集まりから学術研究に移行するポイントだ。マヤのこの地域には大きな都市があると広く知られていて、何十年間にもわたり熱心な調査が続けられてきたのだが、Fundación Pacunam(Patrimonio Cultural y Natural Maya:マヤの文化及び自然遺産財団)の研究は、これまで使われてきた従来型の調査方法を進化させるものとなった。
「これは膨大なデータセットです。膨大なマヤの低地の断面図です」ととEstrada-Belliは話す。「今はビッグデータが流行り言葉になっているでしょ? 一度に一箇所を見るだけで、これまで決して見られなかったものが、実際に見えるようになるのです。ライダーがなければ、これだけ膨大なパターンの統合はできなかったでしょう」
「たとえば、私の地域では、47平方キロメートルをマッピングするのに15年かかりました」と彼は少し悔しそうに言った。「それが、ライダーを使えば2週間で308平方キロメートルをマッピングできます。私にはまったく太刀打ちできない精細さでね」
その結果、論文には、非常に多くの新理論や結論が書かれることになった。人口と経済の規模の推測、文化的、工学的な知識、隣国との紛争の時代や内容などだ。

この論文は、単にマヤの文化と技術に関する知識を高めたばかりでなく、考古学という学問そのものを進歩させるものとなった。もちろん、何事もそうだが、こうしたことが繰り返される。Estrada-Belliは、ベリーズとカンボジアで同僚が実行した調査から刺激を受けたと話している。彼らの研究は、広大な領域と膨大なデータセットの新しい処理方法の実例を示すという点で貢献してくれた。
実験と現場の作業を重ねることで、その方法はより確かなものになる。そしてそれが広く受け入れられ、人々が模倣するようになる。彼らはすでに、その方法が有効であることを実証した。この研究は、おそらく、考古学でのライダーの可能性を示す、最良の実例となるだろう。
いまさら聞けないライダー(Lidar)入門
「はっきり言って、これほど強力な技術は見たことがありません。地表にあるものですら、その詳細はまだほとんどわかっていないのです。ライダーは、人工の地物のほとんどを、明瞭に、一貫性をもって、わかりやすく特定してくれます」と、共同著者のStephen Houston(ボストン大学)は電子メールで話してくれた。「AIやパターン認識は、地物の発見の精度を高めてくれるでしょう。ドローンも、こうした技術のコストダウンに役立つと期待しています」
「こうした技術は、発見だけでなく、保護にも役立ちます」と、共同著者でイサカ大学のThomas Garrisonは電子メールで指摘した。「遺跡や人工物を3Dスキャンすれば、詳細な記録が残せます。3Dプリントでレプリカを作ることも可能です」
ライダーの画像処理技術は、略奪の程度を知ることにも役立つと、彼は書いている。文化担当の行政機関も、略奪者より前に、遺品や遺跡の存在を知ることができる。

研究者たちは、すでに次の調査を計画している。最初の実験が成功したことで資金を獲得し、二回目はさらに多くの航空調査を増やす予定だ。おそらく、最初の実作業が終わることには、この数年間に流行ったツールが使えるようになっているだろう。
「今後、飛行機の利用料が安くなるとは思えませんが、機材はもっとパワフルになります」とEstrada-Belliは話す。「もうひとつの方向性としては、プロジェクトをスピードアップできる人工知能の発達があります。少なくとも、調査の必要のない場所を除外して、時間の節約を図ると同時に、もっとも可能性の高い場所に狙いを定めることが可能になるでしょう」
また彼は、そのアイデアをインターネットで公開することにより、アマチュアの市民考古学者たちが一緒に考えてくれるようになることを大いに期待している。「私たちと同じ体験をすることはできないでしょうが、人工知能と同じく、短期間に大量の上質なデータを生み出せることは確実です」と彼は言う。
しかし、彼の同僚たちが指摘するように、この数年間のライダーを使った作業は、下準備に過ぎない。
「これは最初のステップであり、数えきれないほどのアイデアの実験、何十もの博士論文につながるものであることを、強調しなければなりません」とHoustonは書いている。「それでも、地表の下に何があるのかを調べる採掘や、廃墟から明確な年代を推論する作業は必要です」
「社会科学や人文科学など数々の学問分野と同様に、考古学もデジタル技術を採り入れています。レイダーはそのほんの一例に過ぎません」とGarrisonは書いている。「同時に私たちは、デジタル・アーカイブに関する問題(とくに古いファイル形式によるトラブル)を意識する必要があります。そして、テクノロジーは、何世紀にもわたり試され、正しいと証明された情報管理方法に取って代わるのではなく、それを補うものとして使うことが重要です」
彼らの論文は9月28日にScienceに掲載されているので、研究の結果を詳しく知ることができる(考古学者や人類学者なら、いっそう楽しめる内容だ)。Pacunamの今後の活動については、このサイトを見ていただきたい。
[原文]
(翻訳:金井哲夫)