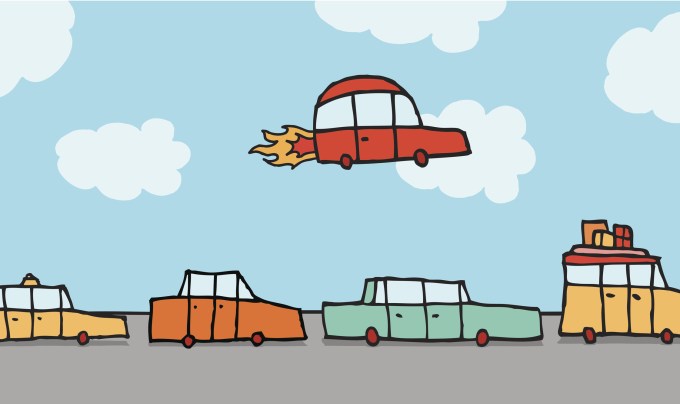【編集部注】執筆者のAdam SingoldaはTaboolaのCEO。
車が発明される前の時代の人に何が欲しいか聞いたら、”車”ではなく”速い馬”が欲しいと言っただろうというHenry Fordの有名な言葉がある。
私は今日の自動運転車が当時の速い馬にあたるのではないかと考えている。つまり自動運転車は現存するものの延長線上にあるものであって、決して新しいカテゴリーを生み出すものではない。想定の範囲内で革命的とは言えない。
こんなことを考えているとElon Muskという、おそらく自動運転車界でもっとも有名で情熱のある男に行き着く。
同じ車好きとして、私は彼を高く評価しているし、テック界の起業家としても彼を尊敬している。さらにElonは、ほとんどの場合において正しいというのも間違いない(Solar Cityに関してはもう少し時間をおく必要があるが、私は彼のことを信じている)。
そのため私は自動運転車のビジョンについて、彼と違った意見を持っていることを心苦しく思っている。将来的に人間が運転しなくなるというのは間違いないだろう。そして機械が運転手の役割を担うという意見にも賛同している。しかしその機械は、私たちの頭上から地上を見下ろしながら、州間高速道路を走っているだろう。
私たちは自動運転車をスキップして、自律飛行ドローンに乗ることになると私は考えているのだ。
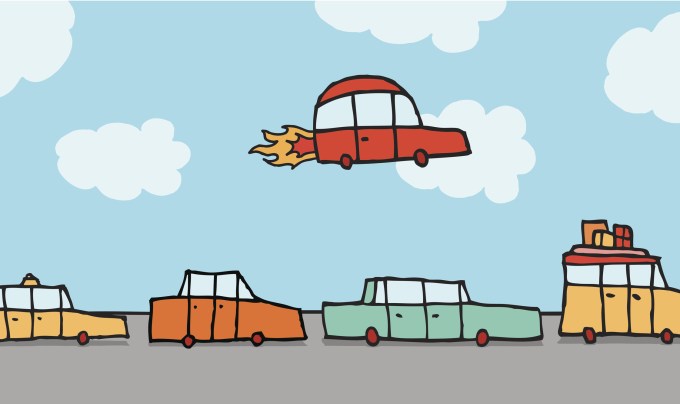
地上の車を飛び越えていく空飛ぶ車のイラスト
誤解しないでほしいのが、私は自動運転車のメリット自体はきちんと認識している。具体的には事故の減少、移動コストの減少、そして何より自由に使える時間の増加だ。
アメリカだけでも、車を利用した場合の通勤時間の平均は片道24分だ。つまり通勤に車を使っている人は、平均して最大20万分もの時間を会社への行き帰りだけに費やしていることになる。ここに買い物やほかの用事、旅行の際の移動時間、そして何かクリエイティブなことをする代わりに運転に脳を使っている時間を足し合わせると、膨大な量になる。
しかし自動運転車をスキップして自律飛行ドローンを採用することで、上記のような個人の問題だけでなく、社会的な課題も解決できる可能性があるのだ。
もしも自動運転車の代わりに、自律飛行ドローンで地上500メートルの高さに浮かべるとすれば、空中にドローンを停めて、いつでも好きな場所へ移動できるようになる。
一旦ここで一息ついて、私の意見に潜むバイアスを認識しておいてほしい。
私は車も好きだが、それ以上のドローン狂だ。私は自分が空を飛んでいるような気分になって、今まで見たこともないような景色を4Kで見るのが大好きだ。以前はDJI Phantom 3を使っていたが、その後4を購入し、今はMavicが到着するのを待っている(そして素晴らしいものは全てそうであるように、Mavicの到着はもちろん遅れている)。
しかしどうやらドローンに執着しているのは私だけではないようだ。Taboolaがアメリカのネットワークから抽出したデータによれば、人は1日に25万回もドローンに関する文章を読んでいる。
このあたりで話を元に戻すと、自律飛行ドローンの開発は、技術的には地上を走る自動運転車を開発するよりも簡単だ。というのも、自動運転車を開発するときには、歩行者や路面の悪い道路、突然あらわれるものなどを考慮しなければならない。
さらに自律飛行ドローンの方が安全性も高い上、そこまで高度な技術を必要としないため大量生産時のコストも恐らく自動運転車より低い。私は自律飛行ドローンが、水平に移動するエレベーターのように、ただボタンを押せば目的地に向かって飛んでいくようなシンプルなものになると考えている。将来的にはUberも、何台もの自律飛行ドローンを予め空に飛ばしておいて、ユーザーが”オンデマンド”でドローンを使えるようなビジネスをはじめるかもしれない(Wazeは乱気流レポートに差し替えなければいけないが)。

自律飛行ドローンが誕生すれば、突然地上から500メートルの空間を自由に使えるようになる。それに対し、私たちホモ・サピエンスはこれまで20万年もの間、地上から1.5メートルの空間に全てを詰め込んできた。その結果発生した、駐車スペースの問題や渋滞、道路建設などは、自律飛行ドローンのもと、すぐに過去のものとなるだろう。
法規制も私の味方についている。ドローンを買うと、ほとんどの場合地上から500メートルより上には飛べないように予め設定されているが、500メートルもあれば十分だ。
今年に入ってから、私は実際に人用ドローンに乗ったことがある。正直少し怖かったが、未来の一部を見ることができ、とても感動する体験だった。
そろそろもっと高みを目指して考えて羽を広げ、自動運転車(速い馬)をスキップして自律飛行ドローンの考えにのっても良い頃だろう。
もしかしたら、宇宙家族ジェットソンはずっと前からそれに気づいていたのかもしれない。
[原文へ]
(翻訳:Atsushi Yukutake/ Twitter)