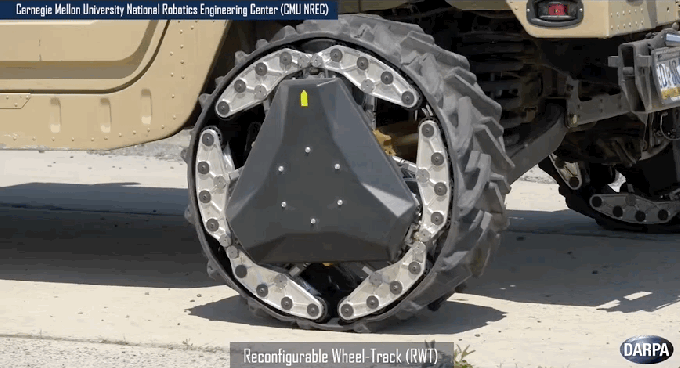【編集部注】筆者のHugh Harsonoは元金融アナリストで、現在はアメリカ陸軍に所属している。
近年オリジナルコンテンツ市場が賑わいを見せており、その主役は制作スタジオをはじめとする従来の主要コンテンツプロバイダーから、インターネット時代のスタートアップへと移行しつつある。彼らはオリジナルコンテンツを制作することで、事業ポートフォリオの拡大や限定コンテンツの配信を通じた有料会員数の増加を狙っているようだ。
アメリカでは、同市場の覇権を握るAmazonやNetflix、Huluが『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』『高い城の男』『侍女の物語』など評論家も絶賛するシリーズを投入しており、他の大手テック企業も彼らに必死で追いつこうとしている。たとえばAppleはスティーブン・スピルバーグ監督と契約を結び、『世にも不思議なアメージング・ストーリー』のリニューアル版の制作を予定しているほか、Facebookはオリジナルコンテンツの制作に最大10億ドルを投入。Googleは将来的にTVシリーズの1エピソードあたりの制作費を最大300万ドルまで引き上げると発表しており、Disneyも独自のストリーミングサービス向けにオリジナルコンテンツを制作しようとしている。
同様に中国のオリジナルコンテンツ市場も、ネット大手のBaidu、Alibaba、Tencentが支配権を握っている。欧米諸国に住む人は、これらの企業名や彼らが制作しているテレビシリーズにあまり馴染みがないかもしれないが、徐々に中国産のコンテンツも世界に向けて配信されはじめていることを考えると、この状況は近いうちに変わってくるだろう。
中国とアジア諸国の違い
世界はもとよりアジアの他の国々と比べても、中国には数々のユニークな点がある。たとえばモバイルデバイス上でのメディア消費量の増加や、テレビの視聴ボリュームの増大、爆発的な成長を遂げつつある映画・テレビ業界の存在などがその一例だ。
eMarketerによれば、近いうちに中国の成人は1日あたり約3時間をモバイルデバイス上で過ごすようになるとされている。これは1日あたりのメディア消費時間の41.6%にあたり、さらに彼らはもう40%にあたる時間をテレビの視聴に費やしているのだ。このモバイル中心の生活スタイルが今後数年のうちに視聴時間が急増するであろうとされているデジタル動画と組み合わさることで、人口と同じように動画の消費量も増えていくだろう。
さらに中国のテレビ業界もここ数年で前例がないほどの成長を遂げた。実際のところ、国内の映画業界とテレビ業界を合わせると350億ドル以上の規模に達すると言われるなか、テレビ関連の売上がその88%を占めているのだ。中国ではIP放送の利用者も増えており、2017年には利用者数が1億人を突破。オリジナルコンテンツ市場の盛り上がりをさらに後押ししている。ほかにも、昨年12月には国内のスタジオが集結しChinese TV Drama Export Allianceという団体が立ち上げられ、グローバル市場でのプレゼンス向上やNetflixなどのストリーミング企業に対する中国語コンテンツの売り込みに今後力を入れていくようだ。
中国オリジナルコンテンツ界の巨人
ネット系コングロマリットのBaiduは中国のオリジナルコンテンツ市場を支える一社。特に同社の傘下でストリーミングサービスを運営するiQiyiはひときわ存在感を放っている。国内のストリーミングサービスとしては最大級のiQiyiは、アメリカでのIPOを通して22.5億ドル以上を調達しており、その月間ユーザー数は4億2100万人、デイリーユーザー数は1億2600万人を超える。そして規模やリーチを背景に、同社のオリジナルコンテンツは国内で大きな人気を呼んでいる。
同社が制作したリアリティ番組『Rap of China』『Street Dance of China』『Hot Blood Dance Crew』は、中国政府によるヒップホップカルチャーやタトゥーに関するメディア規制をものともせず、何百万人もの視聴者を熱狂させた。なかでも『Rap of China』は、最近アメリカのヒップホップトリオMigosとパートナーシップを締結しており、今後欧米の人々の目に触れる機会もでてくるだろう。
リアリティ番組以外のオリジナルコンテンツも負けてはいない。推理ドラマの『Burning Ice』や『Tientsin Mystic』はセカンドシーズンの制作が決まったと同時に、今年Netflixを通じてアメリカでも放送されることになった。ほかにも『The Lost Tomb』『Evil Minds』『Unforgiven』などの人気シリーズはいずれも何百万人以上もの視聴者を抱えている(注:『The Lost Tomb』と『Evil Minds』は政府の検閲によりiQiyiのウェブサイトから削除された)。
特に中国では、オリジナルコンテンツ市場の成長に伴い、仮想現実(VR)や人工知能(AI)など関連分野にも大きな影響が出てくるだろう。
Baiduと並んでこの市場で活躍するのが、ストリーミングサービスYoukuを展開するAlibabaだ。Youkuはタブレットやルータ、テレビボックスなどYoukuブランドのハードウェアを含む強固な流通ネットワークを通して、5億人以上のユニークユーザーにコンテンツを届けている。Youkuのサービスはすでに消費者の生活の一部となっていることから、彼らのオリジナルコンテンツも国中の視聴者にリーチできるのだ。
人気シリーズ『Day and Night』に関連し、Youkuは2017年終わりにNetflixと契約を結び、同番組は中国語のテレビシリーズとしては初めて世界中に配信されることとなった。ほかにも有名なコンテンツとしては、歴史ドラマの『The Advisors Alliance』『Oh My General』、人気コミックが原作のファンタジードラマ『Rakshasa Street』などがある。Youkuは短いビデオクリップとオリジナルコンテンツのどちらでも人気作品を生み出していることから、中国のオリジナルテレビコンテンツの制作においてはマーケットリーダー的な存在だと言える。
そして最後がネット界の巨人Tencentだ。WeChatの成功で知られる同社だが、Tencent Videoの平均デイリーアクティブユーザー数は1億3700万人以上と言われており、Tencentのオリジナルコンテンツも市場での重要度が増してきている。
Tencent Videoの人気シリーズとしては、1日で2億回もの再生数を叩き出し、これまでに何十億回も再生されたアクションアドベンチャードラマ『Candle in the Tomb』や、同名の人気小説がベースの歴史ロマンス『Rule the World』がある上、同社は『The Tomorrow Children』のようなバラエティ番組の制作も手がけている。さらに直近では、小説『The Tibet Code』や『Mystery of the Antiques』、日本ではおなじみのマンガ『テニスの王子様』を原作としたテレビシリーズの制作が予定されている。Tencentは今後もオリジナルコンテンツへの投資を拡大していこうとしており、向こう数年で同社のポートフォリオはさらに拡大していくだろう。
中国にはこれまでに名前が挙がったiQiyi、Youku、Tencent Video以外のプレイヤーももちろん存在する。たとえば人気コンテンツプロバイダーのSohu TVもオリジナルコンテンツ市場に参入し、人気ドラマ『Indelible Designation』や推理シリーズの『Medical Examiner Dr. Qin』の制作に携わっているほか、『Saturday Night Live』風の番組の制作も予定されている。
人気動画プラットフォームのMango TVも、コメディ番組の『Fashion Rivers』やドラマ『Gold Matchmaker』、インタラクティブな『Big Brother』風の番組『Perfect Holiday』などさまざまな番組を制作している。SohuやMango、そして彼らが提供するコンテンツからも、中国のデジタル化を推進する上で、オリジナルテレビ番組がどのくらい大きな役割を担っているかがわかる。
一方、その他のアジア諸国では……
規模では差がありつつも、オリジナルコンテンツ市場が盛り上がっているのは中国だけではない。アジアの他の国々もインターネットを普及させるにあたり、モバイルファーストなアプローチをとってきたため、モバイルデバイス上でテレビを視聴する人の数は増え続けている。
タイではLINEが運営するLINE TVがモバイルテレビ市場を席巻しており、自社のストリーミングプラットフォーム向けにオリジナルコンテンツの制作も計画している。さらにLINE TVはすでに現地のテレビ番組制作会社とパートナーシップを結んでおり、もともとの出発点であるYouTubeのようなサービスから、Netflix、Huluのようなサービスへと変化つつある。
インドネシアでは、ライドシェアのGo-Jekがオリジナルコンテンツ市場への参入を画策している。先日、同社は制作会社Go-Studioの立ち上げを発表。Go-StudioはサブスクリプションサービスGo-Play向けのコンテンツを制作していくとのこと。さらにGo-JekはVICE Mediaともパートナーシップを締結し、2019年を目標にオリジナル映画『When We Dance』(監督:Joko Anwar)の制作を予定している。
オリジナルコンテンツ市場がスタートアップに与える影響
特に中国では、オリジナルコンテンツ市場の成長に伴い、仮想現実(VR)や人工知能(AI)など関連分野にも大きな影響が出てくるだろう。Baidu、Alibaba、TencentはいずれもVRやAI分野へ積極的に投資しており、今後ハードとソフトが上手く絡み合ったテレビ番組が一般家庭でも楽しめるようになってもおかしくない。たとえば、VRヘッドセットを使ってテレビ番組内のキャラクターの視点で物語を楽しめるようになったり、ユーザーの視聴傾向をもとにAIがオススメのハロウィーンのコスチュームを提案してくれたりといったこともありえるだろう。
このような未来を実現するにあたり、オリジナルコンテンツ市場の成長はその第一歩と言え、国内の巨大企業のリーチや影響力、そして成長を続けるテレビ業界は今後さらに重要な役割を担うことになるだろう。
まとめ
オリジナルのテレビ番組制作には計り知れないほどの可能性がある。というのも、オリジナルコンテンツ市場自体の成長もさることながら、先述の通りアジアではモバイルデバイス上でテレビ番組を楽しむ人の数は急増しつつあるのだ。その結果、中国のトップ企業も単に同市場に目を向けるだけでなく、自らオリジナルコンテンツの制作に乗り出し、視聴者獲得のために高品質なシリーズをリリースするまでになった。
オンライン限定シリーズや視聴者の数はかなりのスピードで増加し、今では年に何百という数の番組が公開され、何十億回も再生されている。中国のコンテンツが海外でも同じように評価されるかどうかはまだわからないが、今のところ中国のオリジナルコンテンツ市場が減速する様子はなく、中国企業にとってはグローバル市場への飛躍もありえる有力な収益源として今後も注目されることだろう。
Image Credits: Kevin Thrash / Getty Images
[原文へ]
(翻訳:Atsushi Yukutake)