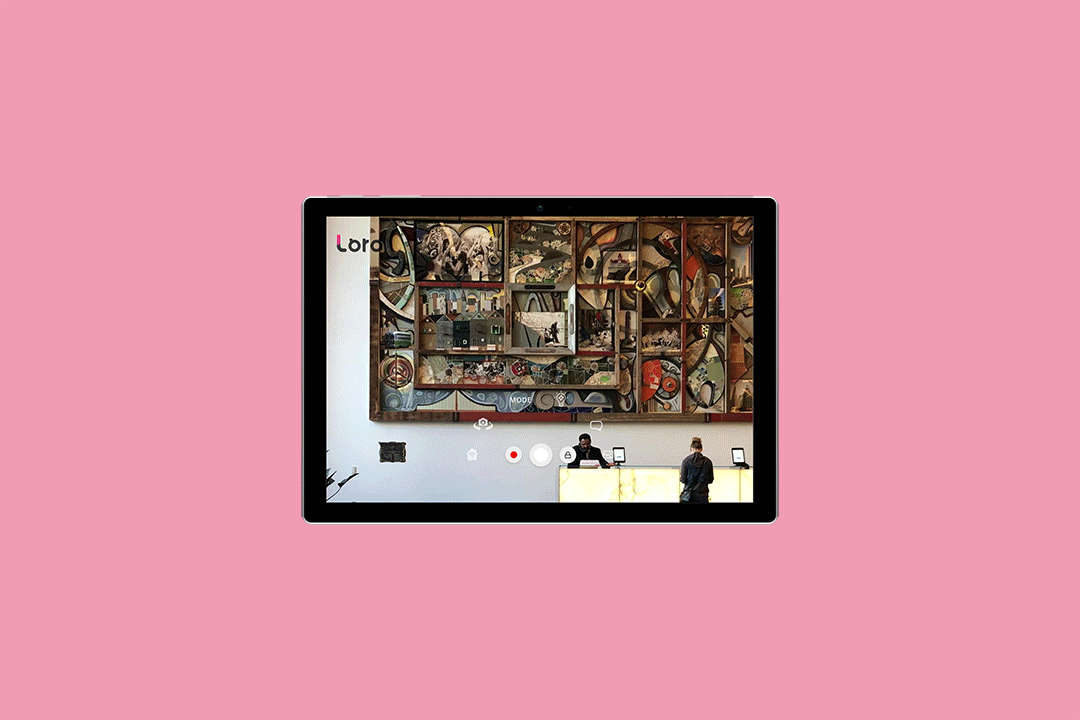身体障碍を持つ人は、障碍を持たない人と同じようには世界とやりとりすることはできないが、そのギャップを埋めるためにハイテクを使えない理由はない。Loroは車椅子に装着されて、その持ち主に対して周囲の人や物を見たり対話したりする能力を提供する強力なデバイスだ。
Loroのカメラとアプリは協調して動作し、ユーザーが遠くを見たり、書き物を読んだり翻訳したり、人物を識別したり、レーザーポインターで意思表示をしたりといった動作を行わせてくれる。TechCrunch Disrupt Berlinの中で行われているStartup Battlefieldの舞台上で、本日(米国時間11月29日)彼らはその技術を披露した。
 Loroは、その大部分がハーバード大学のイノベーションラボに集まった学生たちで構成されたチームによって発明された。最初は障碍者が周囲をもっと簡単に見ることができるようするための簡単なカメラとしてスタートした。
Loroは、その大部分がハーバード大学のイノベーションラボに集まった学生たちで構成されたチームによって発明された。最初は障碍者が周囲をもっと簡単に見ることができるようするための簡単なカメラとしてスタートした。
「私たちはこのプロジェクトを、友人であるSteveのために始めました」と語るのはLoroの共同創業者でありクリエィティブディレクターのJohae Songだ。Johaeや友人グループの人たちと同様に、デザイナーだったSteveは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断された。これは罹患者の筋肉を麻痺させる神経変性疾患である。「そこで私たちは、モビリティの課題を持つ人を助けるアイデアを考え出すことにしたのです」。
「私たちはまず車椅子に装着されたカメラというアイデアから始めました。パノラマ視覚を提供することで、移動をしやすくしようと考えたのです」と説明するのは共同創業者のDavid Hojahである。「そのアイデアから始めて、メンターや専門家たちと議論を重ね、私たちは何度も開発を繰り返しました。そしてよりスマートにするアイデアを考え出し、いまや様々な要求に応えることのできるプラットフォームとなりました」。
ALS患者やその他の運動障碍のある人たちのために、責任を持ってデザインを行うことは簡単ではない。そうした人たちが日々の生活の中で抱えている問題は、必ずしも他者が想像できるものとは限らず、またその解決策も自明なものではないからだ。そこで、Loroチームは、多くの情報源にアプローチし、そして愚直な観察に多くの時間を費やすことに決めたのだ。
「とても基本的な観察 ―― 単に座って見続けることですが」とHojahは語る「そうした観察を続けることで、特定の質問を相手に投げかけなくても、相手が求めているものに対するアイデアを得ることができるのです」。
「ユーザーがカメラインターフェースを介して操作できる懐中電灯が欲しい」といった具体的な解決策を示唆するのではなく、ただ特定の懸念を口にするひともいる。
「人びとは『懐中電灯が欲しい』とは言わないのです、彼らは『暗いところでは移動できない』と言っていました。そこで私たちはブレーンストーミングを行い、懐中電灯を思いつきました」と彼は言う。ある意味明白な解決策だが、観察と理解を重ねることだけが、それを上手く実装させてくれるのだ。
注力する観点は常にコミュニケーションと自立だとSongは言う。そして何が含まれるかを決めるのはユーザー自身なのだ。
「私たちは一緒にブレインストーミングを行い、それからユーザーテストを行います。私たちはうまくいく機能、うまくいかない機能を観察します。私たちはともあれ、相手にそれを使ってもらい、どの機能を皆が一番使うかを観察しているのです」。
すでに、移動に障碍を抱えたひとたちのためのデバイスが世の中にあることは、SongとHojahも認めているが、そうしたデバイスは一般的に高価で扱いにくく、適切にデザインされていない。Hojahのバックグランドは医療機器デザインなので、彼は自分の語るべきことをよく知っている。
その結果、Loroは可能な限り使いやすくなるようにデザインされている。タブレットインターフェイスを通して(Tobiiカメラを使った)視線追跡や、ジョイスティックや息操作チューブなどの入力を使って、ナビゲーションを行うことができるのだ。
例えば、カメラは車椅子の背後を見るように向けることが可能で、このことでユーザは安全に後退することができる。または、ユーザーの視点から見るのが難しいメニューにズームインし、項目を読むことができる。レーザーポインターは、商品ケースのなかのパンを指さして選ぶといった、私たちが当然のように行っていることを、体を動かすことのできないユーザーができるようにする。テキスト読み上げ機能は組み込まれているので、読み上げのために別途アプリを導入する必要はない。
またカメラは顔を追跡し、対話相手の追跡の手助けを必要とする人のために、個人データベース(現段階ではクラウドでホストされている)を使った認識が行われる。どんな人にも、相手の名前や顔を思い出せないことがある ―― 正直な話、私もイベントの際に、肩の上にLoroを載せておきたい位だ。
現在チームは、ハードウェアの最終仕上げに専念している。アプリと機能はほとんど確定されているが、外装などが製品化のためのさらなる洗練を必要としているのだ。同社はまだ非常に初期段階にあり、数ヶ月前に法人化し、プロトタイプを作るための10万ドルのプレシードファンディングで作業してきた。次に控えているのは商品製造のためのシードラウンドだ。
「チーム全体が本当に、困っている人たちに、ただ手助けをして貰うことを待つのではなく、自立できるパワーを与えることに情熱を持っているのです」とHojahは語る。彼らを突き動かすものは、彼が明らかにしたように、相手への共感なのだ。
[原文へ]
(翻訳:sako)