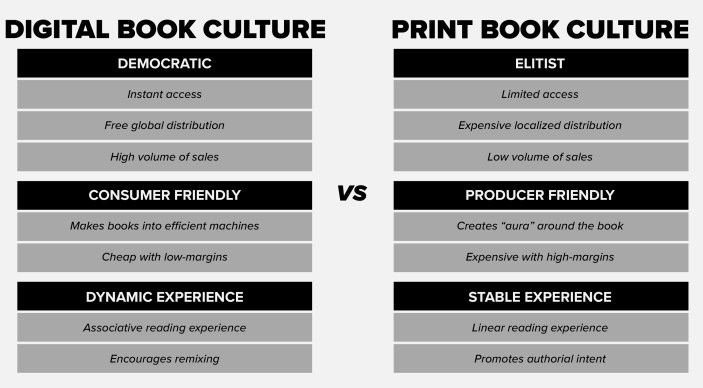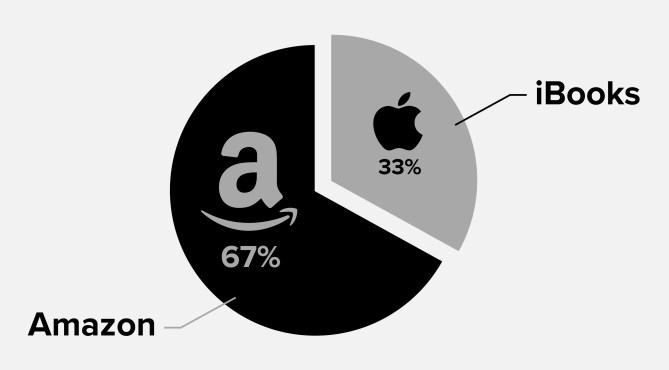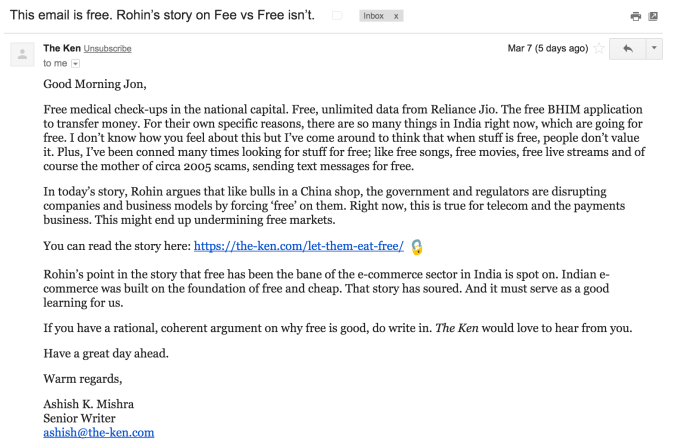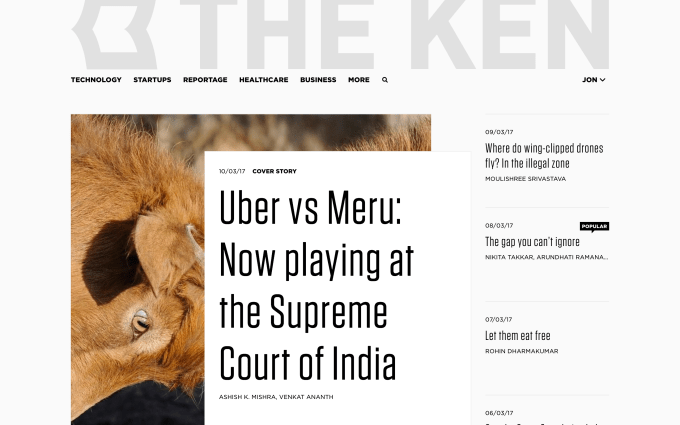ガーナ発のメディアスタートアップで「アフリカ版BuzzFeed」とも呼ばれているOMG Digitalが、シードラウンドで110万ドルを調達したと本日発表した。メインのサイトであるOMG Voiceは、既にガーナ以外にもナイジェリアとケニアに進出しており、今回調達した資金はさらなる市場拡大に使われる予定だ。
今回のラウンドには、Kima VenturesやSoma Capital、Comcast Ventures Catalyst Fund、Social Capital、M&Y Growth Partners、Macro Venturesのほか、Mino GamesのJosh BuckleyやWill Sternlicht、エンターテイメント分野で活躍する弁護士のKenneth Hertz、Off-Grid ElectricファウンダーのFrances Xavier Helgesenなど、エンジェル投資家も参加していた。ちなみにOMG Digitalについては、彼らが昨夏Y Combinatorのアクセラレータープログラムに参加した際にTechCrunchでも紹介していた。
OMG Voiceは、Jesse Arhin Ghansah、Prince Boakye Boampong、Dominic Mensahの3人によって2016年2月にローンチされ、現在の月間ユニークユーザー数は450万人にのぼる。25人のチームに成長した彼らは、現在南アフリカ、ウガンダ、ザンビア、タンザニアへの進出を計画しおり、シード資金は市場拡大や動画コンテンツの制作、広告・マーケティング部門の増強に使われるという。
Ghansahとふたりの共同ファウンダーは、大学在学中の2012年にOMG Ghanaを立ち上げた。当時スマートフォンが一般に普及し始めていたものの、Ghansahはネット上に面白いコンテンツがあまりないと感じていた。
「インターネットをチェックしても、つまらないニュースや政治に関するコンテンツばかりだったので、かなりフラストレーションが溜まったのを覚えています。その経験から、リスティクル(まとめ記事)や軽めな内容の記事のように、私たちの世代に合った何かをつくりたいと思ったんです。その頃、スマートフォンが一般に広まり、Facebookがかなりの人気を呼んでいたこともあり、私たちはOMGを立ち上げることにしました」とGhansahは話す。
「その頃インターネットを利用していたのは、私たちのような若者ばかりでした。BuzzFeedやMashableはミレニアル世代に向けたコンテンツを発信していましたが、私たちは彼らのコンテンツにあまり共感できなかったので、自分たちで別のものを作ろうと考えたんです」
当初共同ファウンダーの3人は、OMG Ghanaをメインのプロジェクトとは考えておらず、マイクロレンディングプラットフォームを立ち上げようとしていた。しかし資金調達が上手くいかず、その一方でOMG Ghanaの読者は増え、収益も発生し始めていた。そこで彼らはメディア企業を設立することに決め、Y Combinatorのアクセラレータープログラムに参加したのだ。Ghansahは、昨年参加した同プログラムで「超大胆」になる方法を学んだと話す。
「まずはガーナから始めようと思っていたんですが、YCでは外国に進出しろと言われました。参加者は自分の限界を超えて大きなリスクをとるよう彼らに促されるんです」
さらにGhansahは、アフリカの人口の3分の1以上がミレニアル世代にあたるため、OMG Digitalの潜在的な読者はかなりいると付け加える。その一方で、BuzzFeedにはない問題として、彼らはアフリカ各国の文化や言語の違いという課題に取り組んでいかなければならない。
ほとんどのコンテンツは各国のサイトで共有できるような内容だが、それぞれのサイトオリジナルのコンテンツもたくさんある。例えば、ガーナのサイトでは「『Bye Felicia』というフレーズがピッタリな14場面」や「6人のかっこよすぎるガーナ戦士」といったオリジナル記事があり、ケニア版だと「ケニヤ人が『Game of Thrones』を好きな10個の理由」や「今後ケニアではプラスチック袋を持っているだけで刑務所送りに」といった見出しがサイトを飾っている。
「種々の文化的な違いやニュアンスが存在する一方で、中には共通点が見られる国もあります」とGhansahは言う。「例えばガーナとナイジェリアは文化的に近いため、この2国をターゲットにしたコンテンツをつくるのは比較的簡単です。ケニヤとタンザニアも似た文化を持っています。つまり、私たちは(市場拡大にあたって)既存の市場からできるだけ文化的に近い国へ進出しようとしているんです」
OMG Digitalは英語圏をカバーした後にフランス語や他の言語が公用語となっている国へと進出するつもりで、最終的にはアフリカ大陸の全ての国でメディアを運営したいと考えている。また、OMG Voiceの下には既にServePotと名付けられた料理関連のメディアブランドも存在し、今後はテクノロジーやライフスタイル関連のメディアも創刊される予定のようだ。彼らはほかにも、ミートアップイベントやスタートアップカンファレンスなどを開催するイベント業に取り組もうとしている。
BuzzFeedやその他のウェブメディアのように、OMG Digitalはデジタル広告から主な収益をあげている。現在は同社の売上の80%をバナー広告が占めているが、アフリカ以外の市場と同じように、広告主は投資に対する十分なリターンを得られていないと感じており、もっとモバイル端末に合った広告形態を求めているようだ(OMG Digitalのユーザーの90%がモバイル端末から同サイトにアクセスしており、特にAndroidユーザーの比率が高い)。
ユーザーの60%が18〜24歳の若者というOMG Digitalは、それぞれの市場でアフリカの若者にどうリーチすればよいか(国によってはFacebookよりもTwitterの方が人気のため、国ごとに戦略を考えなければならない)考えあぐねている海外企業にとっては魅力的な存在だ。既に同社は、Coca ColaやHuawei、KFC、Philips、Pringlesのほか、MTNを含むアフリカの大手通信会社数社とマーケティングキャンペーンやスポンサードコンテンツに関するパートナーシップを結んでいる。
「私たちは有名ブランドとタッグを組んで、アフリカのデジタル広告ビジネスのパイオニアになりたいと考えています。今のところいい感じにきています」とGhansahは話す。「ブランドも私たちの価値に気づき始めたようなので、これから2年間が大きな勝負になると思います」
[原文へ]
(翻訳:Atsushi Yukutake/ Twitter)