
マサチューセッツ工科大学(MIT)出身の友人が「メディアラボは再建できるのかどうかわからない」と書いてきた。これは例のNew Yorkerに掲載された暴露記事を指している。この記事で自殺した富豪のジェフリー・エプスタイン氏とラボのディレクターである伊藤穰一氏が、それまで認めていた内容よりさらに密接な関係があったことが発覚した。伊藤氏はただちに辞任し、メディアラボを巡っては大揺れが続いている。
メディアラボはテクノロジー世界で長い間、奇妙な位置を占めてきた。 自身のパンフレットによれば「それぞれ無関係な分野と考えられてきた研究を非伝統的なやり方で大胆にミックスことにより学際的文化を積極的に追求し、さまざまな境界を超越していく」と述べている。最初期にはメディアラボは社会的不適合者の集まりと見られることもあった。メディアラボのモットーは「デモか死か」であり、なにか動くものを作ることに最大の重点が置かれていた。
もちろん「社会的不適合者の集まり」だという考え方はすぐに改められた。スーパーエリートの集まるプレステージの高い組織とみなされるようになった。カウンターカルチャーと貴族主義の最高の人材が奇妙な具合に入り交じっていた。予算も2009年の2500万ドルから2019年の7500万ドルへと3倍に増えた。インフレ調整済みドル平価で計算すると1986年の創立以来10億ドルが投じられたとみてよい。
メディアラボはアカデミズムの組織でありながら同時にビジネス志向でもあると主張していた。しかし次のような点を考えてみよう。
- 創立は1986年であり、ムーアの法則がフルに威力を発揮し始めた時期だ。テクノロジービジネスは指数関数的な急激な成長を始めた。
- テクノロジーで世界最高のアカデミズムと自他ともに認める大学に設置された。
- ベスト・アンド・ブライテストな人材をよりどり集めることができた。
- この30年で10億ドルの予算を使った。
こうした要素を考えればメディアラボは…正直に言おう。「はるかに大きな成果を挙げてもよかった」のではないか?
メディアラボが達成した成果は驚くほど乏しい。こちらはスピンオフ企業のリストだ。トリビアクイズをしてみよう。この33年間のメディアラボの歴史で買収、合併なしに自力で株式を上場したスピンオフ企業は何社あるだろうか? 私が調べたかぎりでは、たった1社だ。しかも成功したのかというと、その判断にはかなりの疑問符がつく。Art Technology Groupが実際にソフトウェアを発表し始めたのはスピンオフ後6年もたってからだった(当初はコンサルタント企業だった)。株式公開は最初のドットコム・バブル時代で、後にOracleに買収されている。
もちろん自力上場に至らなくてもよく知られた企業はBuzzFeedなど何社かある。ビデオゲームのHarmonix、後にUpworkになってから消滅したElanceはギグエコノミーのパイオニアと考えられないこともない。 Jana、Formlabsk、Otherlab、Echo Nestというのもあった。それぞれに優れた着目の会社だと思うが、個人的な知り合いが関係していたという場合を除けばメディアで評判を聞いた記憶がない。
OLPC(すべての子供にラップトップパソコンを)は10年前に評判になったが今は誰も覚えていない。メディアラボの決定的な成功はE Inkだったが、1996年のことだ。
もちろんそれぞれ「なかなか優れた業績」には違いない。しかしメディアラボに対する我々の期待と比較すると乏しい成果だ。ベル研でもXerox PARCでもないのは言うまでもないが、Y Combinatorでさえない。しかも私はシリコンバレーの大半の人間とくらべてYCには冷淡なほうだ。
オーケー、なるほどスピンオフ企業が成功したかどうかは適切な判断基準ではないかもしれない。問題はメディアラボそのものの業績だという議論はあり得る。ではメディアラボ自身によるトップ30の業績 (PDF)を検討してみよう。E Inkが23年前の話だというのはすでに書いたが、これを別にすれば、テクノロジー世界に決定的な影響を与えた事例は見当たらない。すべてニッチな発明だ。世界に与えた影響はどこにあったのか?
我々の期待が高すぎたのか?
メディアラボは地道な業績よりカッコよさと派手なシズル感ばかり狙っているという批判は以前から出ていたし、最近も出ている。この記事は「パーソナル・フード・コンピュータは農業に革命をもたらすという触れ込みだが、実態は煙と鏡(手品)だ」と評している。この記事は初代ディレクター、ニコラス・ネグロポンテ氏を皮肉ったパロディーで、1990年代に書かれたものだ。しかし実際に読んでみれば、メディアラボの問題が非常に根深いことに気づくだろう。
お仲間支配の金権政治が実態だったという元メディアラボの研究者の証言が当たっているのかもしれない。建前にとどまらず、本当に能力が高くイノベーティブな人々を出身やコネを無視して集めていたら事態は違っていたかもしれない。そうであるフリをしていた目標にもっと近い成果を挙げられたのではないだろうか。
[原文へ]
(翻訳:滑川海彦@Facebook)



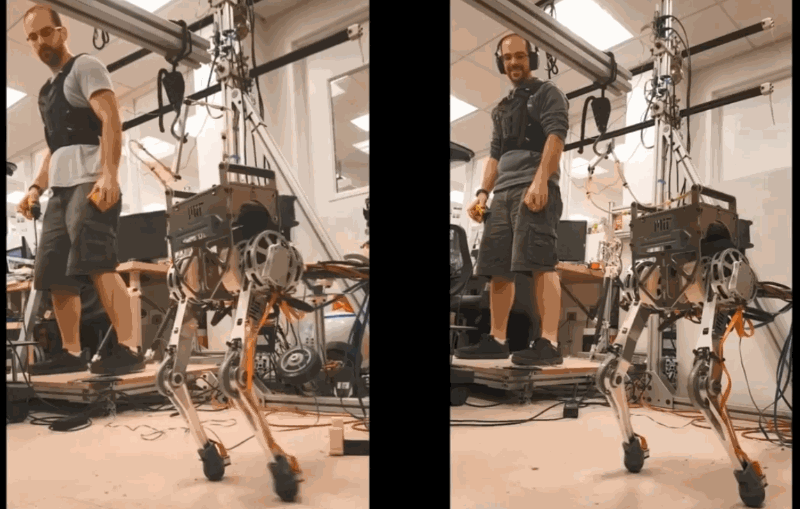 ロボットの動作は操縦者の動きに従うが、必ずしも人間の動作に1対1に対応しない。ロボットは人間よりも小く、重心の動き方も異なるからだ。しかし力学的に動作を解釈するとほぼリアルタイムで求められた動作をする。下のビデオとMITの記事でもう少し詳しくわかるはずだ。
ロボットの動作は操縦者の動きに従うが、必ずしも人間の動作に1対1に対応しない。ロボットは人間よりも小く、重心の動き方も異なるからだ。しかし力学的に動作を解釈するとほぼリアルタイムで求められた動作をする。下のビデオとMITの記事でもう少し詳しくわかるはずだ。
