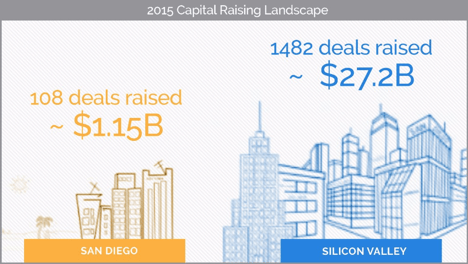世界のデジタル化が進むと、生身の付き合いがより渇望されるようになる。Squad(スクワッド)は、Z世代やミレニアル世代のための密接な人間関係をキュレートすることにより、招待者専用のコミュニティーとアプリで、オフラインでのつながりを満たそうとしている。
「リアルな人生で人間関係を築く方法を模倣しています」と創設者でCEOのIsa Watson(イーサ・ワトソン)氏は言う。
このアイデアには、すでに投資家のバックアップがついている。Squadは350万ドル(約3億8000万円)のシード投資を手にし、2020年の初めにはシリーズA投資が確定する予定だ。ポッドキャスト「How I Raised It」(私はいかにしてそれを調達したか)で、ワトソン氏は、苦難の末に資金調達を実現した独特な方法の話を聞かせてくれた。
資金調達の前に数年間かけて信頼関係を築く
彼女は、家族からの支援も含めた自己資金を元手に事業を立ち上げた。そして、公式にシードラウンドを開始する前の段階で、シリコンバレーで200回を超えるミーティングを行い、企業創設者としての信用を積み重ねていった。そこが何よりも重要だと彼女は強調する。
「MITを卒業していても、JPモルガン・チェイスで10億ドル規模のプロジェクトのマネージャーを務めていても、巨大なデジテル製品を作り上げていても、私はまだシリコンバレーではよそ者でした」とワトソン氏は話す。
米国の一流大学の卒業生なら、シリコンバレーに行けば即座に受け入れられると考る人もいるが、実際にはそんなことはないとワトソン氏は言う。
「苦労に苦労を重ねて高い信用を築かなければなりません」と彼女。「公式にシードラウンドを始める前の数年間に、私たちが実際に行ったことです。シードラウンドを始めるときには、すでに私の評判が、いわば私に先回りしていて、すっかりおなじみになっていたんです」。

SquadのCEOであるイーサ・ワトソン氏
冷たい売り込みはしない、必ず温かい紹介を通す
シリコンバレーに割って入るためのに200回以上ものミーティングを重ねたワトソン氏だが、血の通わないミーティングは一度もなかった。「多くの企業創設者は、無機的な売り込みを戦略にしているようですが」と彼女。「有効な関係は、人と人のつながりから生まれます」と語る。
自分で築いた人脈が、ワトソン氏が実際の投資家たちとのつながりを得る上で決定的な役割を果たした。「みんなが、次に会うべき3人を紹介してくれます」とワトソン氏。「それが木の枝のように広がって、人脈が乗法的に成長するのです」
Squadに最初に投資したのは、当時GoDaddy(ゴーダディー)で最高製品責任者を務めていたSteven Aldrich(スティーブン・アルドリッチ)氏だった。アルドリッチ氏もワトソン氏も、ともに北カリフォルニアで子ども時代を過ごしていて、アルドリッチ氏の父親が、彼女と同じ街の出身だった。それが最初のつながりを作るきっかけとなった。
「そうした人脈作りを、私はずっと続けてきました」と彼女は話す。「スティーブンは3人の人に私を紹介してくれました。そしてその3人は、それぞれ2人の人に私を紹介してくれました。基本的にそうやって私はボールを回してきたのです」。
すべてのミーティングがコーヒーやランチを必要としていたわけではない。ワトソン氏は電話も大いに活用してネットワークを広げていった。しかし重要なのは、まずそのような人に出会う段階だ。そのため最初の2年間は「まさに粉骨砕身で突き進みました」という。
助言を求めるときは可能な限り具体的に
シリコンバレーの人たちに会ったり、投資してくれそうな人たちの人脈を広げようとするとき、ワトソン氏は投資をねだったり、目的のあやふやな会合を求めたりはしなかった。
ネットワーク作りでは、彼女はまず、鍵となる2つの要素のリサーチを心がけた。本当に強力な製品を作るために必要となる人は誰か、そして、安定した供給とグロースマーケティングを実現するために必要となる人は誰かだ。そのような人を特定すると、個人的に接触し、その人たちの専門分野の具体的な助言を求める。
「『お金が欲しいときは助言を求めろ、助言が欲しいときはお金を要求しろ』とよく言われます」とワトソン氏は話す。「非常に重要となる彼らの時間と頭脳の利用方法を、実にわかりやすく説明した言葉」であり、「ちょっとお知恵を拝借」などという曖昧な要求に付き合っていられるほど、彼らは暇ではないということだ。
誰かとつながりが持てたなら、グロースマーケティングや製品など特定分野の専門家への推薦を必ず依頼する。何人かの名前を挙げてもらえたら電子メールを送るので、紹介状を添えてその人たちに転送してくれないかと頼む。
紹介をもらっても、それで一件落着ではないと彼女は言う。紹介をもらって、その人に会えたなら必ず相手にミーティングの感想と感謝の気持ちを伝える。
「これは本当に本当に親密な人間関係のマネージメントなのです。そしてこれは、心の知能指数がとても高い人たちが得意とすることです」とワトソン氏。「私は、必要なことを特定して具体的な質問をします。そして、力になってくれそうな私たちがやっていることに興味を強く持ってくれそうな3人を紹介してもらえなかったとき、必ずはっきりと聞きます」
秘密兵器は資金調達のクォーターバック
Squadの資金調達を開始する時期だと感じたとき、彼女の最初の一手は資金調達のクォーターバック(司令塔)を見つけることだった。同社の場合は、Precursor Ventures(プレカーサー・ベンチャーズ)のCharles Hudson(チャールズ・ハドソン)氏がその役を担った。 ワトソン氏によれば「キッチンには料理人は多すぎないほうがいい」という。意見が多すぎて収集が付かなくなるからだ。
その当時、ハドソン氏はすでに同社に少額の投資をしていたが、それからすぐにワトソン氏は、自分のピッチの感想をハドソン氏に聞くようになった。ハドソン氏は、プロセス実行に関するさまざまな側面で彼女にアドバイスしてきた。
「資金調達について、そのときチャールズが教えてくれたのは、成功を目標の核心に据えることで成功に近づくということでした」とワトソン氏。「受け身ではできないことです」。
そこでハドソン氏とワトソン氏は、ターゲットとする35人のベンチャー投資家のリストを作成した。彼は、話が合わないと彼女が考えていた5人の投資家を紹介した。彼らはまず、その完璧な組み合わせにはなりそうもない投資家たちに会った。スクワットが実際に投資対象として準備ができているかどうかを見極めるために、その投資家たちの意見を参考にしようとしたのだ。
この最初の5つのミーティングでは、1人か2人は「ぜんぜんダメだった」という。あからさまにSquadは拒絶された。しかしワトソン氏は、残る3人とのミーティングを、パートナーミーティングにすることができた。その投資家たちが同社を真剣に考えてくれた証だ。
そのフィードバックをもとに、ハドソン氏はワトソン氏に10人のベンチャー投資家を紹介した。その直後に、シードラウンドを主導したHarrison Metal(ハリソン・メタル)のMichael Dearing(マイケル・ディアリング)氏と出会った。
シード投資家は慎重に選べ
ディアリング氏が300万ドル(約3億3000万円)の条件規約書を提示すると、すぐさま他の投資家からもオファーが届くようになった。
「おかしいですよね。私は2か月半ほど、資金調達で市場を必死に走りまわって、やっとマイケルからイエスを引き出せたんです。それまでお金の話は一切なかったのに」と彼女。「それで、300万ドルの条件規約書を受け取ったと人に話してからほんの数日後に、600万ドルとかの話が来たんです。ベンチャー投資家って、ほんとうに追随型なんですね」。
ディアリング氏に続いて数多くのオファーが出そろうと、彼女はまさにシードラウンドに参加する投資家を選ぶ側になった。どうやって選んだのだろう?
「まずは付加価値です」とワトソン氏は言う。彼女はこう自問した。「必要とする価値はきちんと揃っているだろうか。製品にものすごく強い人が欲しくなるかもしれない。グロースハックに、マーケティングにすごく強い人が欲しくなるかもしれない」。
選択のための2つめの基準は、レジュメから少し離れることだった。単純に、自分の感覚を信じることだ。「投資家たちが、本当に本当に軽視しているのは、その人が人間として善良であるか? ということです。私は、いちばん気持ちよくやっていける人たちを選ぶことにしました。人間関係を通して信頼できると感じられる人たちです。いつでも力になってくれる人たちです」。
【編集部注】著者のNathan Beckord(ネイサン・ベコード)氏は2016年より20億ドル以上の資金調達を行った起業家のための資本調達と投資家管理のためのプラットフォームFoundersuite.com(ファウンダースイートコム)のCEO。また、ファウンダースイートのポッドキャスト『How I Raised It』のホストも務めている。
[原文へ]
(翻訳:金井哲夫)