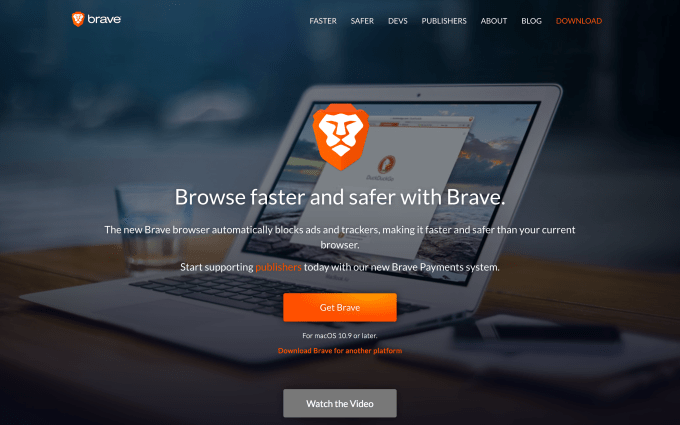仮想通貨取引所を運営するQUOINEは、11月6日より同社が発行する仮想通貨「QASH」を仮想通貨建てで販売し資金調達するICO(Initial Coin Offering)を実施する(発表資料)。1QASHあたり0.001ETHで販売し最大5億QASHを発行する。最大枚数を販売した場合の調達額は約174億円相当(記事執筆時点のETH時価で換算)と大型のICOとなる。
調達した資金は、同社が今後開発する仮想通貨取引所および機関投資家向けプラットフォームLIQUIDの開発、後述するQASHブロックチェーンの開発、それに流動性確保のために複数の仮想通貨取引所に置くデポジット(前払い金)に充てる。またICOで販売するQASHは、ICO終了後はただちにQUOINEほか複数の仮想通貨取引所に上場し、取引可能となる予定だ。「上場の日程は12月1日にしたいが、11月にビットコインの再度の分岐が発生する可能性があり、その対策でICOの時期が伸び縮みする可能性がある」とのことだ。
同社CEOの栢森加里矢氏は「自分達の取引所に上場するだけでなく、すでに提携を発表している香港の大手仮想通貨取引所Bitfinexのほか、複数の仮想通貨取引所にQASHを上場する予定だ」と話している。
同社が発表文で強調するのは「金融庁登録の仮想通貨交換業者として世界で初めて法令を遵守した形でICOを実施する」という点である。栢森氏によれば「今回ICOで発行するデジタルトークンQASHを取引所QUOINEに上場することに関して、法律事務所立ち会いのもと金融庁に説明し、口頭で了解をもらった」とのことだ。今までの日本のICOの法的解釈は、デジタルトークン販売の時点では仮想通貨扱いではなく、販売したデジタルトークンが仮想通貨取引所に上場されて広く一般に売買できるようになった時点で「仮想通貨」になる。また日本の取引所に上場するにあたっては金融庁がそれを認める必要がある。QUOINEが強調する今回のICOのポイントは、日本の仮想通貨取引所に仮想通貨として上場することで金融庁も了解している、ということになる。ただし口頭での了解ということなので、第三者が確認できるエビデンスがある訳ではない。
同社のICOホワイトペーパーから開発ロードマップの図を引用した。ICOの終了後、QUOINEの取引エンジンを中核として資金流動性や機関投資家向け各種サービスを提供する新プラットフォームLIQUIDを構築する(なお、米BlockstreamもLiquidと呼ぶ製品を提供しているが両者の関係はない)。
LIQUIDの狙いは、機関投資家が仮想通貨分野に参入してきたときに、それに耐えられる流動性とサービスを提供することだ。「今後、投資銀行やヘッジファンドのような機関投資家が仮想通貨に参入する。そこで求められるのは、現状の仮想通貨取引所では処理できない大きな単位の取引や、資金移動やレバレッジなど機関投資家向けのサービスだ。そこで、複数の仮想通貨取引所を束ねて流動性を提供し、サービスを提供する」(栢森氏)。
QASHは、当初はERC20トークン(Ethereum上で発行するデジタルトークンの仕様で、多数の仮想通貨発行に使われた実績がある)として発行する。今後開発する「QASHブロックチェーン」が立ち上がった後は、そちらに移行する予定だ。金融機関向けシステムに実績があるウルシステムズがQASHブロックチェーンの開発に参加する。なおウルシステムズの持ち株会社ULSグループは、2016年9月にQUOINE株を引き受け資本提携を結んでいる。
ところでQASHブロックチェーンとは何なのだろうか? 栢森氏は「大手銀行ではなくFinTechスタートアップを主な利用層とする、金融向けのパブリックブロックチェーンだ」と説明する。
背景として、今の金融サービスのニーズと、既存のブロックチェーン技術との相性は良くないと栢森氏は考えている。例えば最大の仮想通貨でありパブリックブロックチェーンであるビットコインは、金融機関から見ると誰が責任を負うのかが見えにくい。またマイナーが中国に偏っていることにカントリーリスクがあると考える人もいる。金融分野向けというとRippleやR3の名前が思い浮かぶが、彼らは大手銀行向けのプライベートなインフラ技術を提供しようとしている。「大手銀行向けのビジネスは時間とコストがかかる。一方、金融サービスと親和性があるパブリックブロックチェーンはエアポケット。まだ誰も手を付けていない」と栢森氏は説明する。
栢森氏の説明によれば、QASHブロックチェーンは、金融機関が求める処理性能、AML/KYC(アンチマネーロンダリング/本人確認)の機能を備え、またノードが特定の地域に偏らないようにする管理機能を設ける方向だ。具体的な開発はQASHのICO終了後に始まる。QASHブロックチェーンは2019年2Qにローンチする計画である。