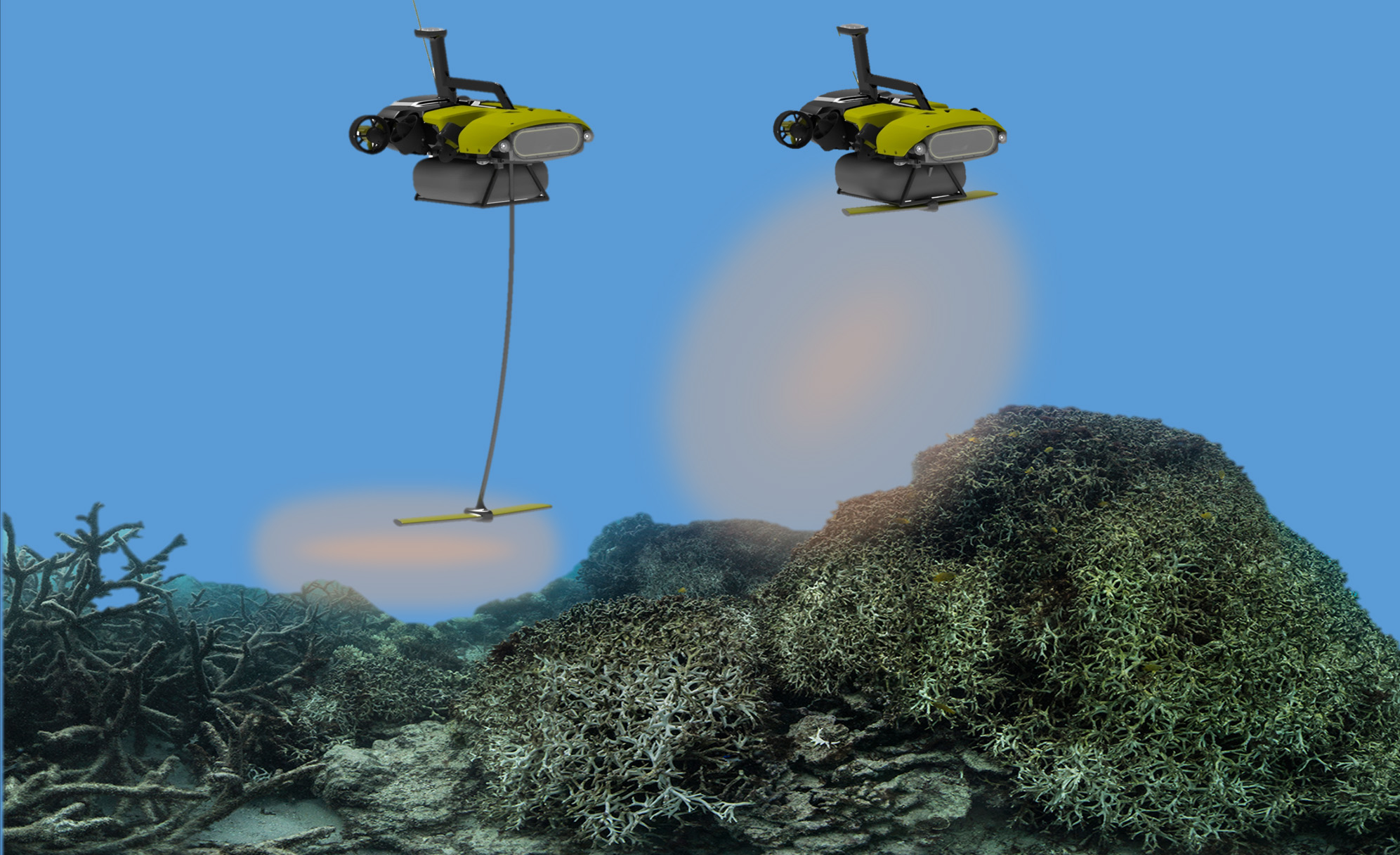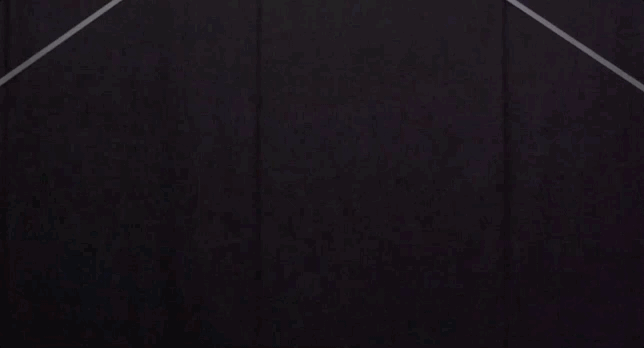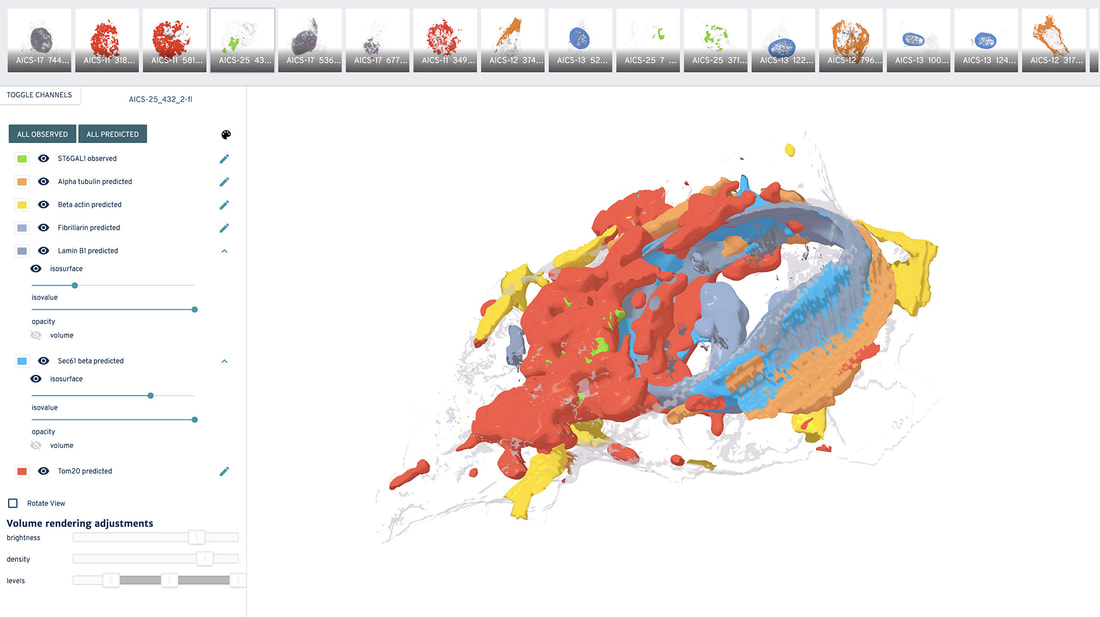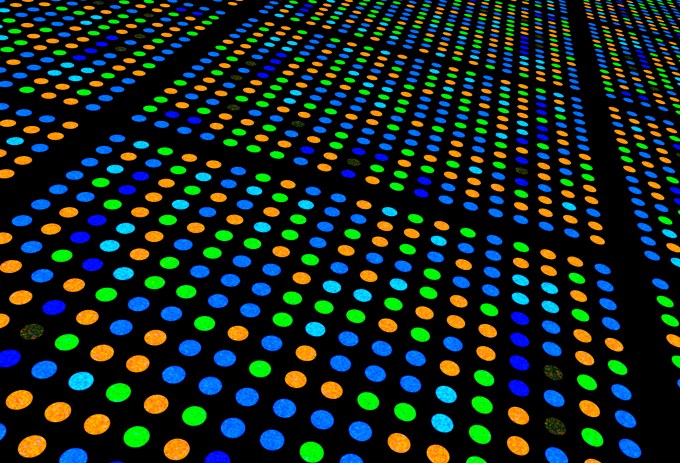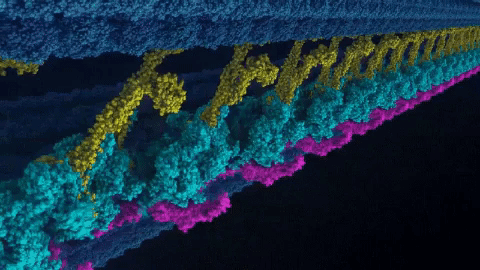[筆者: Paul Shapiro](”Clean Meat: How Growing Meat Without Animals Will Revolutionize Dinner and the World“の著者)
古代食といえば、われわれ人類の農業以前の遠い祖先たちが食べていた、と考えられる食物による、一種の食養生や食餌療法を指すことが多い。しかしながら、祖先たちが本当に何を食べていたのか、に関する議論や研究は未だに乏しい。でもシリコンバレーのVCたちが支援するサンリアンドロのスタートアップGeltorにとっては、合成生物学(synthethic biology)が、そのような古代食の、その文字通りの理解〔==本物の古代の食べ物〕を作り出すための手段になった。
人類が初めて北アメリカへ来たとき、われわれが目にしたのは巨大な動物たちがたくさんいる大陸だった。マストトドンが最大の動物だったと思われるが、しかしこれらの、アジア象の牙の長い親戚たちは、ホモ・サピエンスが登場するころまで進化を続けることができず、したがってわれわれの獲物になることもなかった。きわめて急速に、彼らやそのほかのいわゆる大型動物相(megafauna)は絶滅危惧種となり、そして完全に絶滅した。しかし、その消滅した四足獣たちの一部は、氷の墓地に閉じ込められ、その肉体は数千年を経た今でも腐敗変質せずに保存されている。
そして、古代の有機体がみなそうであるように、彼らの肉体にタンパク質がまだあれば、それらはおそらくコラーゲンの形で残っている。それはわれわれの肉体にも豊富にある分子だ。いや、それどころか、人類は今や、遠い昔の動物たちのタンパク質をシークエンシングすることにより、われわれの祖先たちが満喫した巨大生物の、少なくとも分子レベルでの採掘に向かう第一歩を踏み出したばかりなのだ。インターネットに接続できる人なら誰でも、ほんの数秒で、マストドンのタンパク質のシークエンス(アミノ酸配列)に無料でアクセスできる。
そこでGeltorだが、同社は基本的には、発酵を利用してバクテリアのような微生物からコラーゲンを逆行分析(reverse engineer)し、またその副産物としてゼラチンを得ている。パン屋さんのイースト菌がCO2を作ってパンを膨らまし、醸造所のイースト菌がアルコールを作るように、Geltorは微生物を使って本物のコラーゲンのストランドを作り出している。協同ファウンダーのAlex LorestaniとNick Ouzounovが遺伝子コードをプログラミングしてそれを微生物中に植えることにより、目的とするタンパク質を大量に作り始める。
LorestaniとOuzounovは、地球上に現存する動物のDNAシークエンスでこの能力をマスターしたあと、2015年の終わりごろ、彼らの実験を先史時代に適用する決心をした。Geltor はDNAをプリントしてくれる企業に注文して、マストドンのコラーゲンをエンコードしているDNAのバイアルを入手した。それらを確保した二人の科学者は、マストドンのゼラチンの現物を作り出す(微生物利用の)プロセスを開始した。
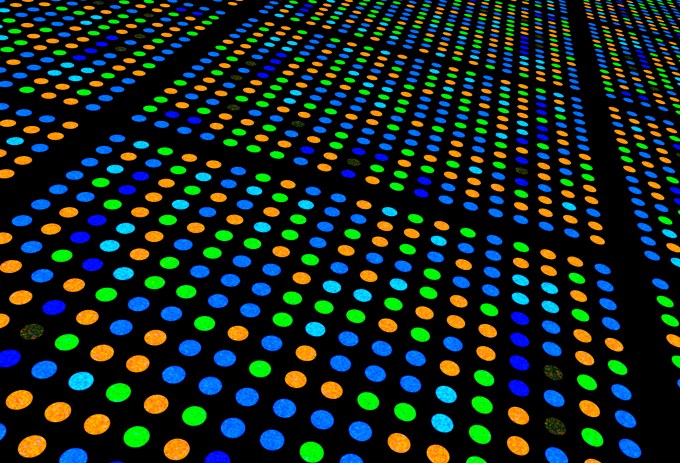
画像提供: PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images
LorestaniとOuzounovはグミベアを作ることもできたかもしれないが、しかし二人の協同ファウンダーはEtsyで象の抜き型を買った方がクールだ、と考えた。さすがにマストドンの抜き型は見つからなかったが、ふつうの象さんでも同じだ、と彼らは考えた。グミエレファントで十分じゃないか。すぐさま、彼らのゼラチンに砂糖とペクチンを混ぜ、世界初のマストドンのゼラチン・キャンデー〔いわゆるグミ菓子〕が完成した。その小さなグミエレファントをOuzounovが自分の口に運ぶのを見たLorestaniは思った: “おいおい、人類がマストドンのタンパク質を食べるのは、ものすごく年月が経って、今がやっと初めてだな”。
別の言葉で言えば、それが今日の世界では唯一の、本物の古代食だ。
その後同社は数百万ドルの資金を調達して、化粧品などにも使われている今のふつうの動物のDNAから本物のコラーゲンを作り出す研究開発を開始した。そのコラーゲンを、本物の革に成長させることもできた…もちろん、牛を一頭も使わずに。そして、世界で初めての、実験室で育てた皮革を使った革表紙の本まで作った。
Geltorは、クリーン・アニマル・プロダクトの分野を開拓しているスタートアップたちのグループに属する。それは、本物の動物性食品を、動物を繁殖したり殺したりせずに入手する技術だ。この用語は“クリーン・エナジー”をもじっているが、動物性食品を今の畜産のように資源浪費型で作るのではなく、ずっと少ない資源消費量で得ることに加え、クリーン・ミートやクリーン・ゼラチンは、食べ物の安全性という見地からもずっとクリーンだ。
今日の食肉産業は、つねに病原性大腸菌のリスクにさらされているが、食肉(やゼラチンなどの)の生産を家畜の肥育に依存しないようにすることができれば、真に安全な食品が現実のものになる。また動物から動物性タンパク質を得ることに比べて、それにはありえない、ずっと多様な機能性食品が得られる。
“食べ物のコミュニティとしてのわれわれ人間は今、安易に稼働できるタンパク質製造プラットホームに甘んじている”、とLorestaniは彼の見解を述べる。同社は仲間のスタートアップMemphis Meatsとオフィスを共有しているが、こちらは、屠殺からではなく細胞の培養から本物の食肉を育てようとしている。Lorestaniは、彼のトレードマークであるグレーのフーディーで頭と顔を覆ったまま、話を続ける: “多くの場合それは動物の搾取であるだけでなく、豊富な植物にも危機を及ぼしている。人間は大量の動物を作り出す名人だが、しばらくは、それでもよかった。しかし今日では、動物を作物とする農業はわれわれの文明に大きなストレスをもたらしている。しかも、それよりも良いやり方があるのにね。われわれは、そのことを世の中に示したい”。
絶滅した動物のタンパク質を食べることは、古代食愛好家である/ないを問わず、必ずしも万人にとって魅力的ではないだろう。しかし今日の、動物製品の作り方は、われわれの惑星に現在住んでいる種にとってまったく持続可能性がない。もちろん、人間も含めてだ。食肉や、そのほかの動物製品への高い需要が、今日の野生種絶滅の主な要因であることは、今や周知の事実だ。
Geltorのようなフードテック企業の活躍によりわれわれはもうすぐ、もっと安全でエコフレンドリーで人間的な方法で動物製品を食卓に運ぶことが、できるようになるかもしれない。そしてそれはまた、多くの種がかつてのマストドンの道をたどることを、防ぐ方法でもある。
トップ画像: James St. John/Flickr CC BY 2.0のライセンスによる
[原文へ]
(翻訳:iwatani(a.k.a. hiwa)