
Tandemのアプリを使い始めて間もなく、気づけば私はドミニカ共和国出身で35歳のJuanに、”will”という助動詞の微妙な使い方を説明しようとしていた。
私はその前に彼に対して、スペイン語の過去形の複雑さは、英語を母国語とする人には理解しづらいと伝えていた。すると彼から「私も英語で似たような問題に困っているんです」とすぐに音声メッセージで返事がきて、彼は”will”の理解に苦しんでいることを打ち明けたのだ。
これがTandemの日常だ。Tandemでは、言語を学ぶ世界中の人が集まり、お互いにチャットを交わしている。年齢や顔写真が表示されたプロフィールを眺めながら、誰を選んでどのようにゼロから会話をスタートさせようかと考える様子は、少しTinderを彷彿とさせるが、デート目的でこのアプリを使うことはできない。
赤の他人同士をマッチさせて、お互いが勉強したいと思っている言語の練習を促すというのがこのプラットフォームの目的だ。アプリを開くと、ユーザーが勉強中の言語のネイティブスピーカーで、かつそのユーザーの母国語を勉強しようとしている人がリストアップされるので、お互いの勉強を助け合えるようになっている。
アプリを使い始めるにあたって、ユーザーはプロファイル上に自分の興味があることや、どの言語(もしくはその言語のどういった点)を勉強したいのか、さらに話したい内容(またはどういった相手と話したいか)などを記載し、自分の顔写真もアップロードしなければならない。
つまり簡単に言えば、Tendamは言語を学んでいる人同士を結びつけ、チャット機能という練習の場を提供しているメッセージアプリなのだ。
世の中は言語学習をサポートするアプリやサービスで溢れかえっている。しかしベルリンに拠点を置くTandemは、ユーザー同士が無料でスピーキングの練習ができるプラットフォーム作りにフォーカスすることで、比較的ニッチな市場を築くことができたと考えている。なおTandemアプリはテキストメッセージ以外にも、音声・動画メッセージをサポートしている。
iOSアプリは2015年2月から公開されており、昨年9月にソフトローンチされたAndroidアプリもこの度正式にリリースされた。ちなみにTandem自体の開発は2014年の秋にスタートした。
アクティブユーザー数は120万人(アプリのダウンロード数は150万)で、共同ファウンダーのArnd Aschentrupによれば、現在Tandemは11種類の手話のほか、今までにない(ちょっとふざけた)言語として絵文字、ドスラク語、クリンゴン語を含む合計148言語をサポートしている。
「Duolingo、Memrise、Babbel、Busuuなどは、ビギナーが単語を覚えて言語学習の第一歩を踏み出すには素晴らしいサービスです。しかし実際に言葉を話さずして、新しい言語を習得することはできません。そして無料でスピーキングの練習ができるのはTandemだけです」とAschentrupは主張し、Tandemのアイディアはいわゆるランゲージエクスチェンジに基いていると話す。
「私たちは、興味のあることや学習上のゴールでユーザー同士をつなげたり、会話のきっかけをつくるゲームを準備したりすることで、ユーザーができるだけ簡単に会話をスタートさせて、練習ができるようにアプリを設計しました」
「現在Tandemには1万1026組の言語ペア(ノルウェー語とスウェーデン語など)が存在し、面白いことに、少数派で息の長い言語ペアがアプリの使用率の半分以上を占めています」と彼は付け加える。
私もTandem上で、英語を勉強しているスペイン語のネイティブスピーカー何人かと話をした後、このアプリには何か特別な魅力があると感じるようになった。コミュニティ全体がとても良い雰囲気を醸し出しており、ユーザーはお互いに丁寧で熱心なコメントをレビューとして残している。
一方で、Tandemのコミュニティへアクセスして他のユーザーとやりとりをするためには、プロフィールが承認されなければならない(Tandemは自分たちのことを”言語学習者のための会員制コミュニティ”と呼んでいる)。
さらに承認プロセス中には、不適切な行動をとるとどうなるかということがハッキリと伝えられる。基本的なルールとしては、他のユーザには敬意を持って接する、ナンパは禁止、スパムも禁止、さもなければアクセスを禁じられる(さらにある程度テキストでのやりとりをしないと、音声・動画メッセージは送れないようになっている)。
「私たちは、ユーザーが何か間違っても恥ずかしいと感じないように、フレンドリーで温かいコミュニティーをつくろうとしています」とAschentrupは話す。さらに彼は、17〜35歳のユーザーが全体の80%、女性が全体の60%を占めていると言う。「160ヶ国から集まったユーザーとともに、今後もさまざまな国や地域の人をTandemにむかえたいと思っています」
使い慣れていない言語で赤の他人と会話をはじめるというのは、当然簡単なことではないが、プラットフォーム上にいる全員が新しい言語を学ぼうとしているので、ユーザーは恐れを感じる必要がない。
ユーザーに熱意があるのは素晴らしいことだが、スピーキングというのは言語学習のひとつの要素でしかなく、話しているだけではしっかりとした文法の基礎を身につけることはできないだろう。つまり新しい言語を習得するには、スピーキングの練習と文法に関する学習の両方が必要なのだ。そしてTandemのプロフィールに、私が「スペイン語の過去形を練習したい」と書いたところで、すぐに無料の文法レッスンをたくさん受けられるわけではない。
ここがTandemのビジネスモデルの上手くできたところだ。同社はTandemのコミュニティに対して、本物の講師との有料レッスンを販売し、売上の一部(現状20%)を手数料として受け取っているのだ。私も実際にTandemを使ってみて、有料レッスンを試してみたいと感じた。
プラットフォーム上では、Tandemの審査を通過した約150名の講師が、有料レッスンを提供しているとAschentrupは話す。人数から言ってこの制度はまだはじまったばかりだが、彼によれば、これまでのところ講師全員が「紹介や講師自身からの応募」を経てTandemに登録している。
一方オンラインで言語レッスンを提供するプラットフォームは既にたくさんあるため、Tandemも厳しい競争に直面している。それでは良い講師をTandemにひきつけるために、彼らはどんな戦略をとっているのだろうか?Aschentrupによれば、彼らは講師に出来る限りシームレスでモバイルな環境を提供しようとしている。さらに講師はレッスンの価格を自分で設定することができる(少なくとも今のところは)。
「Tandemは、講師がスマートフォンやタブレット上のアプリだけを使って、自分のレッスンを管理(生徒探し、予約管理、言語学習のための総合コミュニケーションツール、予約ごとの即時支払)できる唯一のプラットフォームです」と彼は話し、さらにTandemのアプローチは「言語を教える上で面倒な部分を全て取り払い、その代わりに心地よく、楽しくて一貫性のあるモバイルエクスペリエンスを提供しています」と言う。
現在Tandemは、系統立った学習環境を提供するための新たな機能を盛り込むといった方法を使い、ユーザー数を増やそうとしている。そしてユーザーコミュニティが大きくなれば、結果的に講師の数も増えてゆくだろう。
「次のステップは、もっと系統立った言語学習環境をユーザーに提供するということです。具体的には、適切なエクササイズを準備して、ユーザーが自分の達成度を確認しながら、学習スピードを加速させられるような仕組みを作っていきたいと考えています」とAschentrupは話し、「ユーザーと講師の数が増えるにつれて、ネットワーク効果が高まっているのを確認できています。つまりコミュニティが成長すればするほど、ユーザーや講師全員にとってのTandemの価値が高まっているんです」と付け加える。
直接的な競合サービスとして、彼は中国のランゲージエクスチェンジアプリHelloTalkを挙げているが、このアプリは「Tandemに比べてコミュニティにあまり力を入れていない」と主張する。その他にも彼は、ウェブベースの言語講師のマーケットプレイスであるiTalkiやVerblingが、Tandemの競合にあたると考えている。
資金面に関し、Tandemは2015年に行われたシードラウンドで60万ユーロを調達したと発表した。またこのラウンドには、エンジェル投資家のAtlantic Labs (Christophe Maire)、Hannover Beteiligungsfonds、Marcus Englert (Rocket Internet会長)、Catagonia、Ludwig zu Salm、Florian Langenscheidt、Heiko Hubertz、Martin Sinner、Zehden Enterprisesらが参加していた。
さらに同社は昨年、Faber VenturesやRubyLight、さらには2015年のラウンドに参加していたHannover Beteiligungsfonds、Atlantic Labs、Zehden Enterprisesから200万ユーロを調達した。
現在のTandemの市場規模トップ5は、アメリカ、中国、ブラジル、イタリア、メキシコだが、ユーザー比率が10%を超える国はひとつもないとAschentrupは話し、以下のように締めくくった。
「引き続きTandemはとてもグローバルなアプリであり続けます」
[原文へ]
(翻訳:Atsushi Yukutake/ Twitter)

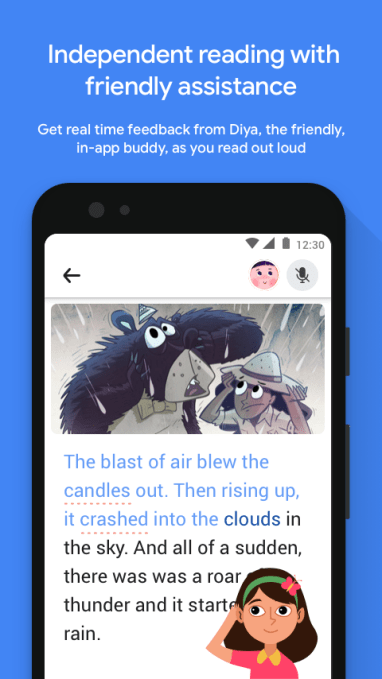 Googleはこのアプリが子供たちのプライバシーに留意し、モバイルやWi-Fiでネットワークに接続している必要がないことを強調している。入力された読み上げ音声はデバイス内でリアルタイムで処理される。Googleその他の外部のサーバーと通信する必要はなく、外部に保存されることも一切ない。Googleによれば、他のアプリでみられるような品質改善のために音声データを利用することもしていないという。
Googleはこのアプリが子供たちのプライバシーに留意し、モバイルやWi-Fiでネットワークに接続している必要がないことを強調している。入力された読み上げ音声はデバイス内でリアルタイムで処理される。Googleその他の外部のサーバーと通信する必要はなく、外部に保存されることも一切ない。Googleによれば、他のアプリでみられるような品質改善のために音声データを利用することもしていないという。

