
Shopify Japan Country Manager マーク・ワング氏
世界175カ国の60万以上の店舗で利用されているカナダ発・世界最大ECプラットフォーム「Shopify」。昨年末に日本市場への参入を果たしてからこの国でも徐々に存在感を高めつつある。現在では靴下専門店「Tabio」や金沢カレーの「ゴーゴーカレー」を含む数千もの国内ショップに利用されるプラットフォームへと成長した同社だが、日本市場のニーズに応えるためのローカライズにはかなり手を焼いていたようだ。
Shopify Japanトップのマーク・ワング氏は「日本は非常に難しいマーケットだ」と述べた一方で「我々をより良いプロダクトへと成長させてくれる」とも語った。日本市場参入後から続けられている徹底したローカライズにより培ったノウハウは、グローバルプロダクトとしての更なる発展にも役立っているのだという。
ワング氏は、J.P. MorganやCitigroup、Global Entrepreneurship Programで企業戦略や起業家支援を担当。2016年にShopifyのHead of Internationalization、2017年に同社のJapan Country Managerに就任した。
TechCrunch Japanはワング氏に、日本市場参入前後からこれまでの経緯や戦略、そして同社が日本EC市場をどう見ているのか、詳しく話を聞いてきたのでその内容を読者の皆さんにも共有したい。
Shopify“日本市場参入”の持つ意味
Shopifyのウリは誰でも「手軽にネットショップをオープンできる利便性」だ。ワング氏はとても丁寧に笑顔で取材に応じてくれた。Shopifyもまた、利用者にとって“技術的に”フレンドリーなプラットフォームだ。
あらゆるショップ運営社がエンジニアやプログラマーを雇わなくても、たとえコードが一行も書けなくてもオンラインストアを開設でき、世界を相手に販売を行える。そのような“簡単さ”は日本市場では特に重宝されるだろう。
総務省が2018年5月25日に発表した「通信利用動向調査」によると、13歳~59歳の年齢層でインターネット利用が9割を超えているが。だが、ワング氏いわく日本貿易振興機構(JETRO)の調査によると、国内リテーラー(小売業者)の若干24%しかオンラインにチャネルを持たない。
だからこそ「日本ではマーチャント(出店者)たちに対し、オンライン販売を開始し利益を向上させるためにサポート・教育の体制を強化する必要がある」とワング氏は語った。

マーク・ワング氏
「(日本では)24%のみがオンライン販売を実施しており、その半分ほどしかグローバルな販売を手がけていない。私たちのプロダクトの特徴は、ショップ開設後すぐにドメスティックおよびグローバルな販売が開始できるという点だ」(ワング氏)
そういった意味で「日本はShopifyにとって重要な市場だ」と同氏は付け加えた。
確かに、Shopifyは150カ国の言語、他国通貨にも対応しているほか、多彩なデザインテンプレートが用意されているので、日本だけでなく海外にも通用するデザインの店舗をすぐに開設することができる。
同社いわく「国内向けと海外向けのECサイトは、偽替・発送・決済の関係から、サイトを個別に構築する必要があった」というが、Shopifyは国内外のECサイトをまとめて管理できる機能を搭載している。
日本市場へ向けた“ローカライズ”
ローカライズと聞くと、言語やカスタマーサービスの対応が真っ先に頭に浮かぶとかもしれない。だが、Shopifyの日本ユーザーに向けたプラットフォームのローカライズについて話を聞いていると、「確かに」と思いクスッとしてしまう細かい部分がいくつかあったので紹介しよう。
日本では海外と違い、会計時に個人情報を入力する際に、ファーストネームではなくラストネームにあたる苗字が先にくる。住所に関しても都道府県、市区町村、町域、丁目番地、建物名、号室、といった順番は海外と逆なので、それに対応する必要があったという。
また、日本ではオンラインショップで会計を済ませている際に郵便番号をもとに住所の大半を自動的に入力してくれるが、これは日本の消費者にとって「必要不可欠なユーザーエクスペリエンスだ」とワング氏は話した。この自動入力は日本に導入後、アメリカでも同じような対応ができるようにしたのだという。細かい部分であるが、こういった部分が世界最大ECプラットフォームをより良いプロダクトへとブラッシュアップしているのだろう。
決済に関しても、日本ではクレジットカードの他にコンビニ決済という独特な方法があるのでそれに対応した。現在、日本でサポートされている主要な決済方法はPayPalやAmazon Pay、コンビニ決済、Shopifyペイメントなど。
2018年5月にローンチしたShopifyペイメントに登録すると、VISA、Mastercard、American Expressからの支払いが直接Shopifyを通して可能となり、他の決済代行のアカウントは不要となる。さらに、Shopify Pay、Google Pay、Apple Payを使用して素早いチェックアウトを顧客に提供できる。ちなみにShopifyペイメントは仲介手数料が0%だ。
ワング氏いわく、今後は「キャリア決済や後払いなどの支払い方法の導入も予定している」とのこと。
ロジスティクスに関しては、2018年7月よりオープンロジとAPI連携。ECサイトと倉庫をシームレスに連携する商品の保管・国内外への発送代⾏サービスを実現した。⽇本国内のみならず海外への発送も取り込みボタン1クリックで簡単に連携できる。

ワング氏いわくShopifyはパートナーやデベロッパーとのコミュニティーやエコシステムの構築を重視しており、「自分たちがベストではない」領域に関してはオープンロジに限らず今後も外部との連携を強化していくという。
また、FacebookやMessengerとの連携に続き、Instagramアプリ内で商品を販売できるように、日本でもニーズが増えているというInstagramショッピング機能との連携を2018年6月にローンチしている。これらのインテグレーションが簡単なのもShopifyの特徴の一つだ。

日本国内競合との差別化、今後の展開
日本には「楽天市場」といったモールがあるほか、ネットショップを無料で簡単に作成でき、ショップ開設数が50万店舗を突破した「BASE」の存在感も増してきている。だが、BASEがフリーミアムモデルを採用している一方、Shopifyはサブスクリプションモデルで利用料金は月額29ドルから。Shopifyには「Basic Shopify」(29ドル)、「Shopify」(79ドル)、「Advanced Shopify」(299ドル)の3つのプランが用意されている。全てのプランにおいて商品数・ファイルストレージは無制限になっている。
米国ではAmazonとも連携をしているということもあり、ワング氏は特に国内の競合を意識していた。Shopifyは利用料金がかかるが「ショップの成長に伴い自由にカスタマイズできる」ことが同プラットフォームの強みだという。Shopifyアプリストアにある2000以上ものアプリを使うことで、ネットショップをさらにカスタマイズすることができる。
「私たちは出店者がまだ規模も小さく苦戦している初期の段階から関係を構築し、カスタマイズが必要となる段階に至るまで共に成長していきたいと考えている」(ワング氏)
また、上でも述べた通り、Shopifyはグローバルなショップ展開をサポートする。ワング氏いわく、ユーザーはそれまでドメスティックな販売に特化していたとしても、Shopifyに登録後「存在するとは想像すらしていなかった」海外需要を開拓したりすることもあるそうだ。
同氏は「以前はローカライズに力を入れていた」が「現在はドメスティック・グローバルのどちらの販売においても最も優れたプラットフォームになることを目標にしている」と語った。
グローバルな販売を目指す日本のショップ・オーナーにとって、Shopifyは今後もますます魅力的なECプラットフォームとなっていくだろう。ワング氏は今年中にも大きなニュースをいくつかアナウンスする予定だ、と話していた。
























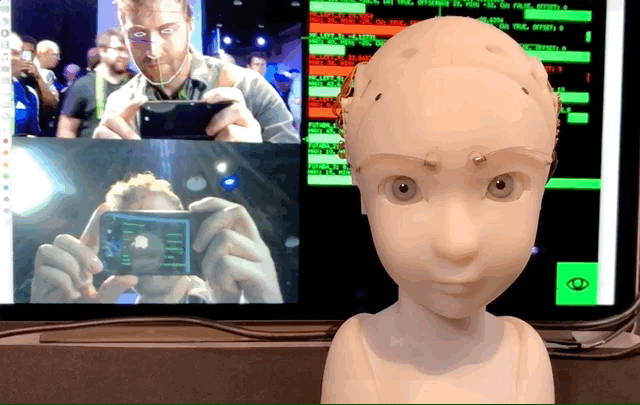









 Green Diningが目指すのは、従来型の「ザ・ケータリング」ではない、と竹内氏。「企業にとって、社員のコミュニケーションやオープンイノベーションを生み出すような、料理と場を提供するのが我々のサービス。商談に使いたい、という企業や、食を使ったビジネス創出についても相談を受けるようになった」と話す。
Green Diningが目指すのは、従来型の「ザ・ケータリング」ではない、と竹内氏。「企業にとって、社員のコミュニケーションやオープンイノベーションを生み出すような、料理と場を提供するのが我々のサービス。商談に使いたい、という企業や、食を使ったビジネス創出についても相談を受けるようになった」と話す。 これまでの約1年半は、市場の需要を見ながらマニュアルで運営されてきたというGreen Dining。竹内氏は「今までは事業のベースづくりのため、いろいろと試しながらやってきた。資金調達を機に、エンジニア増強、プラットフォームシステムの構築を行っていく」と述べている。
これまでの約1年半は、市場の需要を見ながらマニュアルで運営されてきたというGreen Dining。竹内氏は「今までは事業のベースづくりのため、いろいろと試しながらやってきた。資金調達を機に、エンジニア増強、プラットフォームシステムの構築を行っていく」と述べている。














