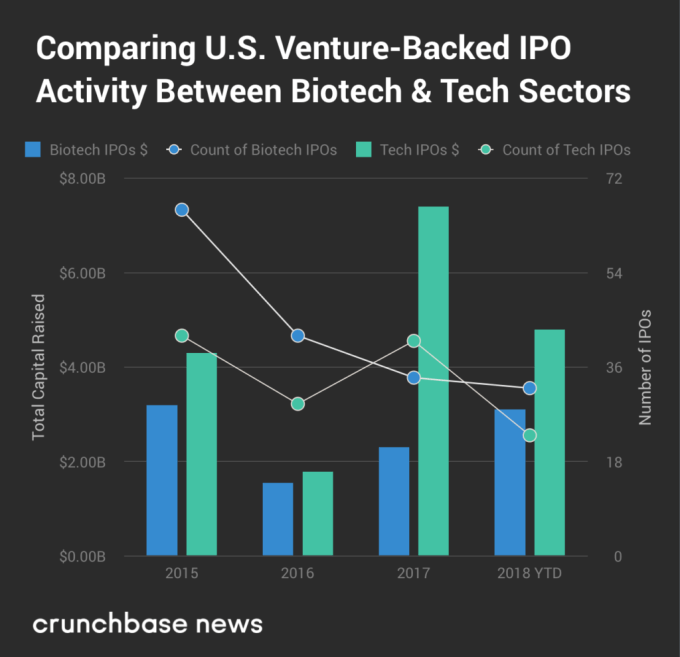コンピュータービジョンと機械学習テクノロジーを活用して迅速な血液検査を行う医療機器を手がけるイスラエルのスタートアップSight Diagnosticsは、医療現場で血液検査ができるシステムを売り出した。
このシステムは、OLOと呼ばれるデスクトップ式のコンパクトマシーンで、患者の血液を使い捨てのカートリッジにセットして分析するというものだ。ごくわずかな血液でラボレベルの全血球検査(CBC)ができるとしている。
患者から採血し、それを分析のためにラボに送るー往々にして数日かかかるーというのではなく、一般的な血液検査をこのマシーンを使って直接クリニックなどの現場で行えるようになるのだ。
また、このマシーンを使ったシステムでは、血液塗抹標本を顕微鏡でみるのではなく、高度なテクニックを使った別の検査方法も提供する。血液検査をする際に使えるテクニックだが、ただしこちらは専従の人を要する。
開発チームはこれまで、資金調達した額を明らかにしていなかった。しかしこのほど、Eric Schmidt(編集部注:Eric SchmidtはGoogleの会長)のInnovation Endeavorsー彼らはこの血液検査システムを米国での臨床試験につなげることを想定しているーを含むVCファームから、株式金融で(シリーズA、B)2500万ドルを調達したことを明らかにした。
Sight Diagnostics は、 OLO は医療機関が長く待ち望んでいた、従来の方式にとって代わる高度な手法だとアピールする。患者の血液数滴を正しくセットすれば、AIを使ってその場で正しく分析するからだ。

CBCテストは健康状態をチェックするのに使う一般的な血液検査で、さまざまな検査で“よく行われる”ルーティーンのようなものだ。この血液検査をスピードアップすることでより早い病気の診断につながる、とSight Diagnostics は指摘する。病気の診断だけでなく、病気ではないと早く安心させることにもなる。
OLO システムは、特許を取得済みの“デジタル化”した血液を顕微鏡イメージ用に特別に色付けするというプロセスを用いている。色付けされた顕微鏡イメージはマシーンビジョンアルゴリズムにかけられ、異なる血球のタイプなどを特定し、算出する。この手法は血液検査にかかる操作をかなり簡単なものにしていて、Sight Diagnosticsは医療従事者でない人でも行えるとしている。
Sight Diagnosticsによると、血液サンプルを使ったこの新たな手法では、わずかな血液をOLO の顕微鏡にセットするだけでいいので、その手法は間違えようがないー使う人にとっては“最小の負荷”となる、と表現している。また診断の精度も高く、これにより血液検査にかかる費用を安く抑えられるとしている。
「血液をデジタル化するという斬新な手法は、人工知能が分析を行うのと同じくらい重要だ」とSight Diagnosticsは指摘する。
もちろん、かなりメリットがある画期的な血液検査テクノロジーといっても、それが実際に従来ラボで行われてきた検査と同じくらい正確であることを証明しなければならない。
人の命がかかっているのだから、当然だ。
スタートアップのディスラプトという面においては、Theranosの壊滅的な一件が尾を引いている(編集部注:Theranosは一時、バイオテックスタートアップとしてかなり注目を集めたが、大規模な詐欺を働いたとして米証券取引委員会に告発された)。
しかし、はっきりさせておくと、Theranos の場合はわずか数的の血液でラボで行うような広汎な検査ができるとうたっていたーOLOが少なくとも最初の狙いとしているCBC 数ではない。さらに言うと、少量の血液サンプルでCBC 検査を行うのは実際のところさほど特異なことではない。
Sight Diagnosticsは「CBC検査は、かなり少量の血液サンプルで行える」とする。「たとえば、いくつかの中央研究室の機器は毛細サンプル(血液200-300uLの中の10uLを実際に数えられる)を扱える。CBCを行う旧マニュアル手法ー顕微鏡のスライドの上に血液塗抹標本をのせるーではトータルで10uLよりも少ない血液を使用する。これは、少量の血液で検査するという我々の手法が、確固とした科学基盤に支えられていることを意味する」と説明している。
Sight DiagnosticsはOLOシステムの開発にこれまで8年以上の歳月を費やしている。
2人の共同創業者、Yossi PollakとDaniel Levner は、マシンビジョンとAIの専門家のコンビだ。Pollakはマシンビジョンを使った高度運転支援システムを手がけるMobileyeで働いていた。一方、Levnerはハーバード・メディカル・スクールのポスドク・フェローシップだった(後にバイオテック企業EmulateでCTOを務めた)。
彼らが前面に出しているのは、OLO では“ラボ品質”のCBC検査ができるということだ。
詳しく言うと、OLO とSysmex XN(“ラボレベルの分析を行うトップレベルマシーン”)を比較する臨床試験を行ったところ、この2つのマシーンは同レベルだった。
同社の科学諮問委員会の議長を務めるLevnerが我々に語った内容は以下の通りだ。
比較する研究には、5つの異なるCBCと、病気診断に使われるたくさんの“重要項目”で構成される19のCBCパラメーターが含まれている。結果は統計学的に分析された。これには2つの機器のパラメーターの相関関係、バイアス(2つの機器でシステマティックなシフトがあったかどうか)、そしてスロープ(2つの機器の結果にシステマティックな計数逓減率がったかどうか)も含まれる。
どのような結果であればOLO がSysmex XNと同レベルであると言えるのかを確かめるために、FDAと3度にわたる事前ミーティングで協議した。EU(欧州連合)の基準適合マークではFDAのような厳しい要件を必要としていないものの、事前協議で得られた品質ターゲットを最近行なった臨床試験に適用したところ、OLOはSysmex XNをしのいでいた。当然のことながら今回の臨床試験結果では、OLOが中央研究室テストと同等であると考えてもいい、と我々は解釈している。精度や分析の深さについて疑念なしに医療現場で血液検査できること、これこそが我々の最終ゴールだ。
Levnerが触れているように、イスラエルのShaare Zedekメディカルセンターで287人を対象に臨床試験を行った。この試験で、OLOのEU基準適合マーク登録がなされた。この基準適合マークというのは、特定の欧州の国で商業販売するのに必須の健康・安全証明となる。
「EU基準適合マークの申告のために、OLOが体外診断用医療機器指令 (Directive 98/79/EC IVD)に適合することを確かめた。当然のことながら、OLO はISO 13485(品質管理システム)や ISO 14971(医療機器リスクマネジメント)、CEN 13612(医療機器パフォーマンス評価)、そのほかさまざまな安全性、安定性、その他の必須項目を含む、同指令が求める全ての基準をクリアしている」とLevnerはさらに述べている。
特記しておきたいのは、Sight Diagnosticsはまだ、OLOの臨床試験についてのピアレビュー結果を公表していないことだ。
しかしLevner は、直近の臨床試験(CBC分析機としてOLOをテストするもの)の結果は、ピアレビュー済みのジャーナルとして公表するために“現在準備中”としている。
「我々はこのような方法でデータを共有することは必要なことだと確信している。しかし残念ながら学術ジャーナルとして公開する手続きには数カ月もかかる傾向にある。このプロセスでは、“内容がスクープされないよう”、秘密保持契約のもとに結果をシェアしている」と語っている。
この研究チームにとって、血液診断の開発はOLOが初めてではない。OLOの前に彼らは、デジタル蛍光性顕微鏡検査やコンピュータービジョンアルゴリズムを使ったマラリアの診断テスト(Parasightと呼ばれている)を開発した。このマラリアテストの臨床試験に関して彼らは3つの学術記事を公開している。
Parasightは2014年に初めて展開され、60万以上のマラリアテストがこれまでに販売されたー25カ国で“正確かつ矛盾点なしに”マラリアを診断している、としている。
Levnerは、“共通サンプル調整手法や顕微鏡デザイン、AIに基づくアルゴリズム”など、新たに展開しようとしているOLOに使われているものと同じテクノロジーがマラリアテストにも使用されている、と話す。
マラリアテストは彼らがフォーカスした最初のものだが、彼らは今OLOでより汎用性の高い医療現場での血液検査ビジネスを築こうとしている。手始めにCBCテストだが、血液検査のポートフォリオを管理する能力のあるプラットフォームのようなシステムを展開するという青写真も描いているようだ。
この点について、Levnerは、“独立した臨床確認”の後は追加のテストが個別に加えられると付け足すのを忘れなかった。
Levnerはまた「OLOは医療機関にとって大事な数々のテストを集約し、クリニックの診断中枢部になるだろう」とTechCrunchに対し述べた。さらに「現在独立した臨床確認が行われているが、我々はこれらの追加テストを一つずつ公開していく」とも付け加えた。
Sight Diagnosticsは、OLOをまず欧州で売り出す。個人のドクターと国家ヘルスサービス向けだ。このマシーンは今後“3カ月以内に”欧州のドクターのオフィスに登場することになる、とのことだーLevnerは、最初の数台の契約が現在最終段階にある、としている。
「究極的には、我々はOLOを全欧州、そして欧州以外でも展開したい。しかしながら、まずは新しいものを取り入れる気質があることで知られる欧州ー単一支払者制度を採用していない国あるいはプライベートマーケットが発達している国ーを優先する」とLevnerは加えた。
彼はまた、 OLO がオランダ拠点のCE認証機関により欧州で登録されたことも認めた。
「我々は、スイスやイスラエルのようにEU基準適合マークを受け入れるか、追加のテストを必要としないいくつかの国での登録も試みている」。
Sight Diagnosticsのチームはまた、FDAテストの一環として米国3カ所で続けている試験による研究調査も行なっている。500人以上を対象に試験を行うことを目的としていて、この試験には8つの異なるOLOマシーンを使用する。
まず取り組むのは、より広域の米国のクリニック(CLIA 認証施設)でOLOが使えるようになるのに必要なFDAの510(k)認可を得ることだ。Levnerはこの認可を“来年半ば”に取得したい、としている。
その後のステップとしては、FDAからCLIA棄権証書を入手することだろう。この棄権証書では機器を小さなクリニックや医師のオフィスに置くことが許可される。これは“医療現場での血液検査を実現する”ゴールのためには必要不可欠だ。この棄権証書を2020年に取得するのが理想だが、しかし言うまでもなく、臨床の規定のハードルを全てクリアするには道のりは長い。
Levnerによると、共同創業者のほかに研究チームには医療、診断、法規の専門家が含まれる。Shai Izraeli博士(血液学ー腫瘍学)、Janice Hogan(血液学的分析の規則戦略を以前扱った)のほか、名前などの情報は明かせないが何人かの診断専門家も含まれる。
Levnerはまた、CBC臨床試験をリードする“有名な血液学の専門家”をリクルートしたとも述べている。その1人が、ボストン子ども病院血液学ラボのディレクター、Carlo Brugnara博士だ。Sight Diagnosticsのプレスリリースで、Brugnara博士は血液検査の結果を待たなければならないことが医師にとってどんなに困難を感じることなのかについて声を大にして語っている。「これまでの現場での血液分析は、臨床的に妥協を伴うものであり、操作やメンテナンスが難しかった。 OLOでは指先を少し刺してとる血液だけで、その場で正確かつ包括的な血液検査を行えるようになる、という可能性をもっている」。
0.5ペタバイト近くの血液イメージデーターSight Diagnosticsが過去4年間の臨床研究で集めたものーがOLOの血液診断システムをサポートするAIを訓練するのに使われている。(Levnerは、このデータは“匿名化されていて、それぞれの臨床機関の倫理的レビューの承認を得て使用されていると明確に述べた”。)
CBCテスト以外にOLOで行えるようにする予定のテストのほとんどでは、CBCテストのように使い捨てモデルを使う見込みだ。その追加予定のテストとしては、デジタル化した情報を他の施設に送ることでメリットを得られるようなものを想定している。

「一つの例として、OLOで患者のCBC検査が行われ、何か重大な発見があったと想像してみてほしい。その後、医師はさらなるテストをオーダーし、すでに手元にあるデジタル化された血液のイメージを専門家にストリームするのではないか」。Levnerはさらに「その専門家は(複数かもしれない)血液イメージをリモートで分析することになるが、これにより患者が再度採血されたり血液検査を受けるために移動したり、といったことをなくすことができる」と話す。
投入してすぐのビジネスモデルは従来型のセールスモデルになる。Sight DiagnosticsはOLOシステムと必要なだけのテストキットを販売する。CBCテストは、デバイスをサーバーにつなげたりすることなく行える。そしてその先にあるのは、SaaSプラットフォームでのふるい分けるためのスコープだ。たとえば、医師がデジタル化された血液イメージを遠隔地の専門家にみてもらい、その上で追加の分析をオーダーしたりといったことだ。
ゆえに、もし彼らのテクノロジーが彼らが言うように本当に正確で信に値するものであれば、わずか数滴のデジタル化された血液で実に多くのことがわかるようになる。
[原文へ]
(翻訳:Mizoguchi)