
AI、IoT、VR/AR、ブロックチェーンなどの技術を組み合わせた人型AIエージェントの開発を行うクーガーは、5月25日、イーサリアム財団(Ethereum Foundation)の援助を受け、日本のエンタープライズブロックチェーン活性化のための活動を開始すると発表した。コミュニティ「ETH Terakoya(イーサテラコヤ)」を展開し、ワーキンググループの開催、アウトプット共有やノウハウ・スキルの提供を、オンライン・オフラインの双方で行っていくという。
エンタープライズユースで注目高まるEthereum
クーガーはホンダへのAI学習シミュレータ提供や、Amazonが主催するロボットコンテストAmazon Robotics Challenge(ARC)上位チームへの技術支援、NEDO次世代AIプロジェクトでのクラウドロボティクス開発統括などで知られ、ゲームAI、画像認識AI、ブロックチェーンの分野に強みがある企業。現在は、これらのテクノロジーを統合する形で、人型AIアシスタント「Connectome(コネクトーム)」の開発を進めている。

ブロックチェーンの領域では、クーガーはこれまでにも大企業との連携による実証実験を行ってきた(関連記事:KDDIとクーガーがブロックチェーン技術Enterprise Ethereumを修理業務に適用する実証実験を開始)。
また2018年には米国のブロックチェーン企業ConsenSysと共催で、日本の大手企業も協賛・後援する形で、インバウンド向けブロックチェーンサービスのハッカソンを実施している。
同社ではほかにも、チーフブロックチェーンアーキテクトの石黒一明氏が2018年、ワールドワイドでブロックチェーンの社会実装を目指す企業連合、Enterprise Ethereum Alliance(EEA)の日本支部代表に就くなど、企業のブロックチェーン活用につながる活動を続けている。
「こうした流れもあり、今回、イーサリアム財団の支援を得て、日本のエンタープライズブロックチェーンの活性化を進めていくことになった」とクーガー代表取締役CEOの石井敦氏は話している。
イーサリアム財団は、Ethereumと関連テクノロジーのサポートに特化した非営利団体だ。非中央集権、分散型のEthereumエコシステムを支える取り組みに対して、助成金などの財政面で支援するほか、エコシステム成立に必要と考えられるアクションへの助言、サポートも行っている。
イーサリアム財団エグゼクティブディレクターの宮口あや氏は、「Ethereumは、企業ではスケーラビリティやプライバシーの面で課題があり、使いやすい状態ではなかった。それが最近では、Etereumプロトコル上で利用できるツールなどの研究・開発が進んだことで、企業でもメインネット、パブリックチェーンを使いやすい環境になり、エンタープライズユースへの注目、ニーズが高まっている」と語る。
「当初は開発に力を入れていた財団メンバーだが、現在はコミュニティのコーディネートや助成金でEthereumをサポートするようになっており、研究・開発支援のほか、教育にはより力を入れるようになっている。日本では特に事業者側が『勉強してからしっかり取り組む』という傾向があるため、教育の仕組みはあった方がいいと考えていた。クーガーのメンバーとは、これまでにもブロックチェーン社会実装への取り組みで面識があった。Ethereumコミュニティとしても、企業のニーズが増える中で、クーガーが日本での教育、勉強する場を展開してくれるというのは、ありがたい」(宮口氏)
技術だけでなくビジネス、法律面でも課題を洗い出し
企業のブロックチェーン活用といえば、暗号通貨取引や証券取引など、フィンテック領域での浸透が最も進んでいるが、GA technologiesが不動産取引にブロックチェーン技術を取り入れるなど、他業種からも注目されるようになっているのが現状だ。日本では、ブロックチェーンを物流やサプライチェーンに織り込む流れも出てきている。
クーガー自身も人型AIエージェントの開発において、エージェントが扱う情報の信頼性を担保し、安全にデータを扱うためにブロックチェーン技術を活用している。また、KDDIとはEnterprise Ethereumを活用したスマートコントラクトの実証実験を実施。携帯電話の修理業務を対象に、ショップでの修理申し込みから修理完了までの情報共有とオペレーション効率化や、他事業とのシステム連携の可能性について、検証を行っている。
石井氏は「企業のブロックチェーン活用においては、技術、ビジネス、法律のそれぞれの面で課題がある。しかも産業によって、その課題は変わる」と述べている。
「ETH Terakoyaでは毎回、テーマを決めてワーキンググループで協議した結果をワークショップで発表していく予定だ。そこで技術的な面だけでなく、ビジネスとして成立するのか、法律的に問題がないのかといったフィードバックが数多く得られるだろうと考えている。場合によってはテーマをさらに深掘りして、続きを協議していくこともあるだろう」(石井氏)

日本の場合は「大企業が集まっており、特に自動車、家電、ゲームやアニメなどのコンテンツ分野では競争力の高い企業も多い」と石井氏。「産業ごとに連携して、業界内で『意味のある課題』を見つけることができるのではないか。また、日本からスタートして世界へ広げていくこともできるのではないかと思う」と期待を寄せている。「イーサリアム財団やコア開発者からのフィードバックや連携も受けながら、ガラパゴス化しないような取り組みも並行していく考えだ」(石井氏)
中国ではBATと呼ばれる3大IT企業、Baidu、Alibaba、Tencentの各社が独自のブロックチェーンサービスを提供し、自らもバックエンド技術として取り入れるという動きがある。
石井氏は「物流やサプライチェーンなど、同じ課題に対して別々の取り組みをするのは効率が悪いと考えている」と話す。「日本では文化的にブロックチェーン技術を取り入れるのは難しいという論もあるが、Linuxの例もある。初めはオープンソース由来のシステムを企業サーバで利用することに躊躇があった日本でも、今やほとんどの大企業でLinuxが使われている。標準化されたものを使った方がよいという流れはあり、今は活用を検討するのには、よいタイミングだと思う」(石井氏)
また、これまで企業ユースではEthereumのようなパブリックチェーンではなく、プライベートチェーンを利用する動きが強かったが、先の宮口氏の発言のとおり、企業でもパブリックチェーンを使いやすい環境が整ってきている。今年3月には大手会計事務所EYと、Consensys、Microsoftが提携し、Ethereumのパブリックメインネットを安全かつプライベートに活用できるプロトコル「Baseline」を発表するなど、メインネット、パブリックチェーンへの大きなトレンドが出てきているところだ。
宮口氏はこの流れを「イントラネットからインターネットへの流れと同じようなことが起きている」として、こう述べている。「(ブロックチェーン活用に際して)長い目で見なければ、ビジネスチャンスとして限界があるのではないかと考える企業が出てきている。Ethereumに限らず、(安全性、スケーラビリティといった)課題さえ解決されれば、パブリックチェーンを使えた方がビジネスチャンスは大きいとして、大企業も早めに取り組もうとしている。現実には(コンソーシアムチェーンなどパブリックとプライベートの)ハイブリッド型が多いし、私もいきなり大きなビジネスコンソーシアムが100%Ethereumでやると言ったら現時点では勧めないと思うが、インターネットの爆発的普及を見てきた事業者なら、誰しも長期的にはパブリックチェーンを取り入れたいと考えるのではないだろうか」(宮口氏)
石井氏は「日本が独自システムでやってこられたのは、企業買収・売却や人が辞めることが少なかったから。開発した人がそのままメンテナンスできてきたので、仕組みとして信頼性が維持されることへの価値にピンと来ていなかったのだろう」と述べ、「今後の人口減少や海外人材の活用、転職者の入れ替わりなどは避けられない。(運用でカバーするだけでなく)仕組みとして安定していることや信頼性は必要になってくる。使う技術やツールも個人に依存しない形にしなければならない」と標準化されたテクノロジーを重視する理由を語る。同時に「ほかの事業者といかに連携するかについても、考えざるを得ないだろう」とも話している。
ワーキンググループ最初のテーマはマイナンバー活用
石井氏は、ETH Terakoya展開に当たって「クーガーとしてのメリットは、あまり考えていない」と話している。
「クーガーでは、もともとAIの信頼性を生み出す手段としてブロックチェーンを使えると考えてきた。このため、ほかの事業者よりは中立的な立場にあると思う。Industry 2.0といわれる流れの中で、今後さまざまなものが自動化していくということが起きていくだろう。コロナ禍でも明確になったが、情報源の信頼性や、その情報を使って自動化したものが信用できるかといった考え方はより加速するだろう。クーガーでは、ブロックチェーンとAIの両方が分かっているチームも抱えており、中立性とあわせて、コミュニティに貢献できるのではないかと考えている」(石井氏)
石黒氏も「クーガーがハブとなってコア開発者による支援やレビューを受け、メインネット、パブリックチェーンを目標に、長期的目線でブロックチェーン活性化につながる活動をETH Terakoyaでは行っていきたい」と述べている。
ワーキンググループが最初にテーマとするのは、ブロックチェーンによるマイナンバー活用だ。「コロナの影響もあり、情報の信頼性や個人が行った行動を証明すること、複製防止などの文脈を考えると、マイナンバーのID特定やブロックチェーンでそれを生かす具体的な課題解決といったテーマも出てきている」と石井氏はいう。
「まず技術的にどう解決するのかを議論した上で、ビジネスにマイナンバーを生かしたときにインパクトがどれくらいあり、何が解決できるのか、今は気づかれていない価値を探る。それらとセットで、技術的に解決できても法律が追いついていないという部分を洗い出し、解決の道筋を考えていく」(石井氏)
ETH Terakoyaのコミュニティ運営を担当する、クーガー プロダクトマーケティングディレクターの田中滋之氏は「新型コロナ感染拡大で話題となっている例では、健康保険証とマイナンバーの関連付けといったものがある」とテーマに関連したトピックを挙げる。
「シンガポールなどの例でも、国は感染者を特定したいはずで、今後日本でも同じ議論が出てくる可能性があるが、一方でプライバシーの問題がある。マイナンバーを活用するときにプライバシーをどうコントロールするのか、これをブロックチェーンを活用することで『いかに個人を特定せず、IDをオープンに活用することができるか』といった、面白い議論ができるのではないかと考えている」(田中氏)
石井氏も「秘匿化と行為の証明を両立することは、これまでは矛盾するものと考えられてきたが、ブロックチェーンを使うことによって両立できる可能性がある。ここを深掘りしたい」と述べている。
また石黒氏は「テーマに関連することでは、ほかにも給付金申請の仕組みなど『どこが問題か分からない』のが問題となっているものがある。ワーキンググループ内の議論でこうした課題も洗い出せるのではないかと考えている。マイナンバーは日本特有のものだが、マイナンバーだけでなく、他の国や似たようなシステムでも使えるよう、議論を続けたい」と話している。


 フレームダブルオーは、オープンソースソフトウェア(OSS)開発者を暗号資産で支援するプロジェクト「Dev」を展開。開発者は、自分のOSSを登録しておくと、同社独自暗号資産「Dev」(イーサリアムのERC-20規格準拠トークン)をダウンロード数に応じ報酬として獲得できる。またユーザーは、登録済みOSSをダウンロードしたり、Devを売買することで開発者をDevで支援できる。
フレームダブルオーは、オープンソースソフトウェア(OSS)開発者を暗号資産で支援するプロジェクト「Dev」を展開。開発者は、自分のOSSを登録しておくと、同社独自暗号資産「Dev」(イーサリアムのERC-20規格準拠トークン)をダウンロード数に応じ報酬として獲得できる。またユーザーは、登録済みOSSをダウンロードしたり、Devを売買することで開発者をDevで支援できる。
 同社の
同社の










 同社は、世界では二酸化炭素が年間約340億トン、日本は世界5位の年間約12億トンの量が排出されており、これらの温室効果ガスの排出が台風などの異常気象の原因の1つとなっていることを問題視。今後も深刻化が予測される中で、CO2排出量ゼロの再生可能エネルギーの普及を目指す。法人向けサービスとなるが、都心だけでなく地方での地産地消を実現する電気を提供できるのも特徴だ。具体的には、ブロックチェーン(イーサリアム)を活用した非改竄性の高い独自のトレーサビリティシステムを用いて、希望する発電所の地域を選ぶことで「地産地消」を実現して地方創生に貢献するとしている。
同社は、世界では二酸化炭素が年間約340億トン、日本は世界5位の年間約12億トンの量が排出されており、これらの温室効果ガスの排出が台風などの異常気象の原因の1つとなっていることを問題視。今後も深刻化が予測される中で、CO2排出量ゼロの再生可能エネルギーの普及を目指す。法人向けサービスとなるが、都心だけでなく地方での地産地消を実現する電気を提供できるのも特徴だ。具体的には、ブロックチェーン(イーサリアム)を活用した非改竄性の高い独自のトレーサビリティシステムを用いて、希望する発電所の地域を選ぶことで「地産地消」を実現して地方創生に貢献するとしている。 こちらも法人向けだが、自社開発「GREEN PLATFORM」で電力使用量、電源、地域、CO2排出削減量などを参照できるサービスを利用できる。電力料金が高い月や時間帯を予測した省エネ通知、最新の環境サービスなどと連携する。また同社は今後、ブロックチェーンや機械学習などを活用して、環境と社会面を重視した電力小売の追加機能の実装を目指すとのこと。
こちらも法人向けだが、自社開発「GREEN PLATFORM」で電力使用量、電源、地域、CO2排出削減量などを参照できるサービスを利用できる。電力料金が高い月や時間帯を予測した省エネ通知、最新の環境サービスなどと連携する。また同社は今後、ブロックチェーンや機械学習などを活用して、環境と社会面を重視した電力小売の追加機能の実装を目指すとのこと。 リフューチャーズは、2019年10月設立のクリーン電力の小売サービス事業、小売プラットフォームSaaS事業を手掛けるスタートアップ。株主には、独立系VCの
リフューチャーズは、2019年10月設立のクリーン電力の小売サービス事業、小売プラットフォームSaaS事業を手掛けるスタートアップ。株主には、独立系VCの



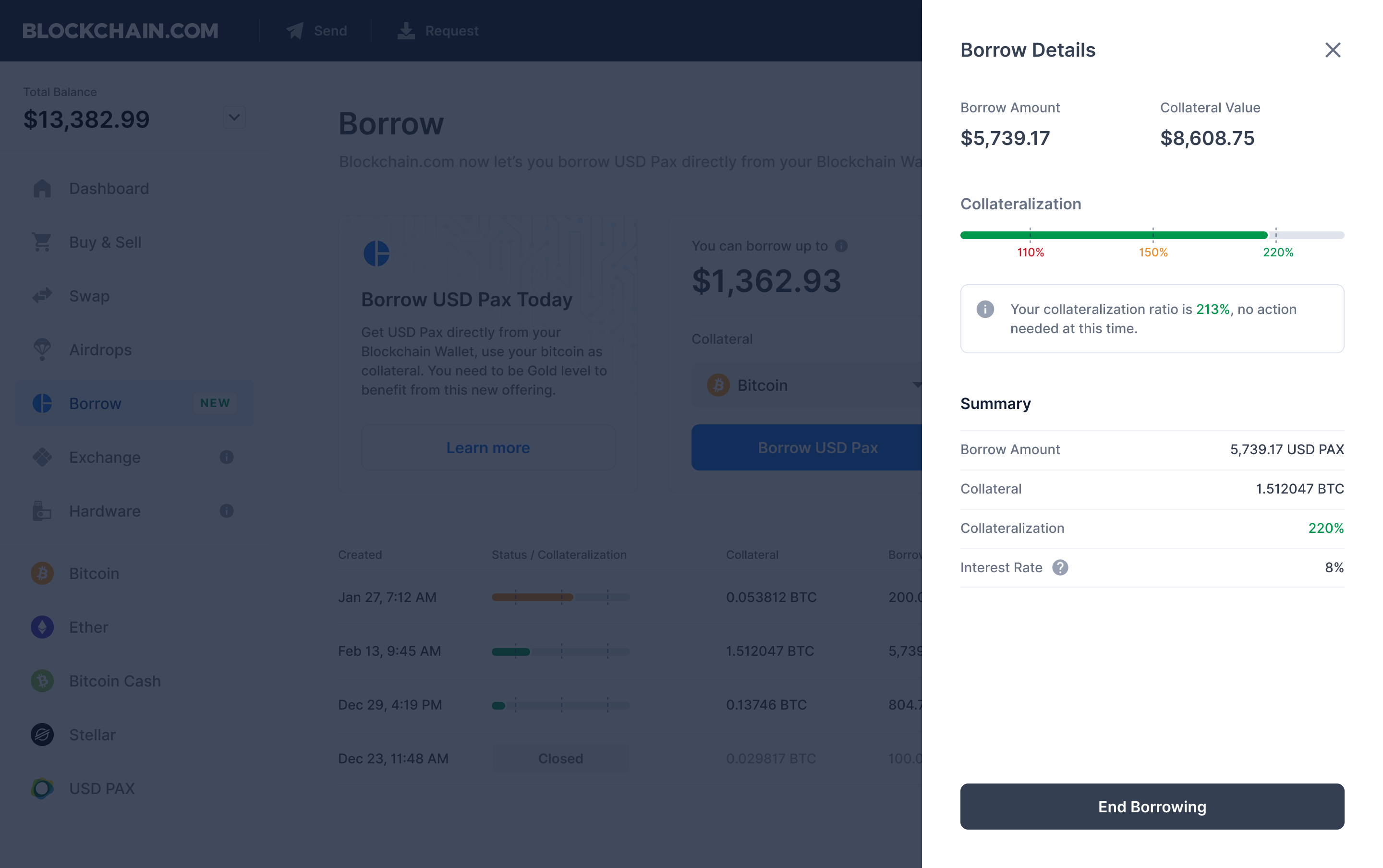


 このサービスを提供するのにZenGoは
このサービスを提供するのにZenGoは








