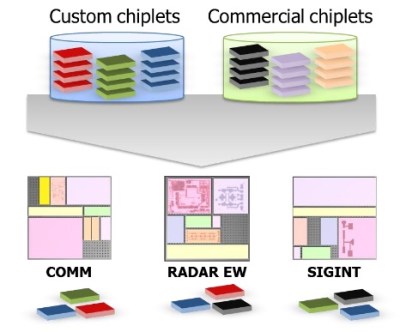私と、私の大学の院生のチームが、最初のメッセージをインターネットで送信したのは、1969年10月のロサンゼルスの暖かな夕方のことだった。それが、世界的規模の革命の始まりだったとは、だれ一人考えてもみなかった。最初の2文字、具体的には「Login」の「Lo」を、UCLAのコンピュータ室でタイプ入力すると、ネットワークはクラッシュしてしまった。
それゆえ、最初のインターネットメッセージは、期せずして「Lo and behold(驚いたことに)」の最初の2文字と同じ「Lo」だったことになる。私たちは簡潔で強力、かつ予言的なメッセージを送信したのだった。
当時はまだARPANETと呼ばれていたが、それは政府、産業界、そして学界によって設計された。科学者や学者が、互いの計算機リソースにアクセスできるようにして、研究に必要な大きなファイルを交換し、時間とお金、行き来する手間を節約するためのものだった。ARPA、つまりAdvanced Research Project Agency(高等研究計画局。現在は先頭にDefense=国防を付けて、DARPAと呼ばれる)は、民間企業のBolt BeranekとNewmanに委託して、そこの科学者にルーター、つまりInterface Message Processorを実装させた。 UCLAは、この芽を出し始めたネットワークの、最初のノードとして選ばれたのだった。
1969年の12月の時点では、ノードは4つだけだった。それらは、UCLA、スタンフォード研究所、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、それにユタ大学だ。このような最初期の段階を経て、このネットワークは指数関数的な成長を遂げた。接続されたホストコンピュータの数は、1977年までで100台、1989年までで10万台、1990年代初頭で100万台、そして2012年には10億台に達した。現在では地球の全人口の半数以上に行き渡っている。
その過程で、われわれは予期していなかったようなアプリケーションの出現に驚かされた。それは突如として現れ、またたく間にインターネット上で広範囲に行き渡った。例えば、電子メール、ワールドワイドウェブ、ピアトゥピアのファイル共有、ユーザー生成コンテンツ、Napster、YouTube、Instagram、その他のソーシャルネットワークなどだ。
こんなことを言うと、夢想家のように思われるかもしれないが、初期の段階では、オープンな雰囲気、コラボレーション、共有、信頼、そして道徳規範、といった素晴らしい文化を楽しんでいた。インターネットは、そのようなものとして構想され、育まれたのだ。その初期には、私はARPANETに参加している人を、全員個人的に知っていた。そしてわれわれは、皆行儀よく振る舞っていた。実際、そうした「ネチケット」へのこだわりは、インターネットの最初の20年間には維持されていた。
今日では、インターネットが異論の余地がないほど素晴らしく、オープンで、協力的で、信頼でき、さらに倫理的であると言う人は、まずいない。データと情報を共有するために生まれたメディアが、どうやって、そのような疑わしい情報が交錯する世界になってしまったのか。共同から競合へ、同意から不和へ、信頼に足るデジタルリソースから疑わしい情報の増幅器へと、いったいどうして変わってしまったのか。

その堕落は、1990年代の初頭に始まった。ちょうどスパムが初めて登場したころ、インターネットが消費者の世界に深く浸透するにつれ、インターネットを収益化しようという激しいまでの機運が高まった。これによって、詐欺、プライバシー侵害、偽ニュース、サービス妨害など、数々のダークサイドの勢力が勃興した。
そうして、インターネット技術の進歩と革新の性質も変化した。リスクを回避するために、「ムーンショット」という言葉に象徴されるような、初期の夢想的な文化がないがしろにされ始めたからだ。われわれは、まだこうした変化に苦しめられている最中だ。インターネットは、共通の価値観と正しい事実に基づいて、情報の分散管理、民主主義、そしてコンセンサスを促進するように設計されている。その生みの親たちが抱いていた大志を完全に達成するという点では、これは失望でしかない。
民間勢力の影響力が増すにつれて、彼らの方針と目標が、インターネットの本質を支配するようになった。商業利用の方針が影響力を持つようになると、企業はドメインの登録に対しても課金できるようになり、クレジットカードの暗号化が電子商取引への扉を開いた。AOL、CompuServe、Earthlinkのような民間企業は、やがてインターネットへのアクセス料として月額を請求するようになり、このサービスを公共財から私財へと転換させた。
インターネットを収益化することが、その景色を変えてしまった。一方では、それは大きな価値のある貴重なサービスを実現した。これには、普及した検索エンジン、広範な情報の宝庫へのアクセス、消費者の助成、娯楽、教育、人間同士のつながりなどを挙げることができる。もう一方では、それはさまざまな領域における濫用と支配につながっている。
その中には、企業や政府によるアクセスの制限、経済的なインセンティブが短期間でも企業の利害と一致しない場合にみられる技術開発の停滞、ソーシャルメディアの過剰使用からくるさまざまな形の影響、などを見て取ることができる。
こうした問題を軽減するために、何かできることがあったのではないかと問われれば、すぐに2つの方策を挙げることができる。まず第1に、厳格なファイル認証機能を提供すべきだった。つまり、私が受け取ったファイルは、私が要求したファイルの改変されていないコピーであることを保証する機能だ。そして第2に、厳格なユーザー認証機能も用意すべきだった。つまりユーザーが、自分がそうだと主張する人物であることを証明する機能だ。
そうした機能を準備だけしておいて、初期の段階では無効にしておくべきだった。その時点では、偽のファイルが送信されることもなく、ユーザーが身分を偽ることもなかったのだから。そして、ダークサイドが顕在し始めたときに、そうした保護機能を徐々に有効にして、悪用の程度に見合うレベルまで引き上げることで、悪用に対抗することができたはずだ。そうした機能を最初から提供するための簡便な方法を用意しておかなかったために、今さらそうすることは厄介だという事実に苦しんでいる。その相手は、この広範に拡がったレガシーシステム、インターネットなのだ。

誕生から50年が経過した今、インターネットはこれからの50年でどのように進化するだろうか? それはどのようなものになるのだろうか?
その未来を映し出す水晶玉は曇っている。しかし、私が50年前にも予測したように、それが急速に「見えない」ものになっていくことだけは見通せる。つまり、インフラとして目につかないものになるだろうし、そうなるべきものでもある。
電気と同じくらいシンプルで、使いやすいものになるはずだ。電気は壁のコンセントに差し込むという、拍子抜けするほど簡単なインターフェースで、直感的に利用できる。どのようにしてそこに届くのか、どこから来るのか、知る必要もないし、興味もないだろう。それでも、必要なときにいつでも使えるのだ。
残念ながら、インターネットへのアクセスは、それよりはるかに複雑だ。私がある部屋に入ったとする。その部屋は私がそこにいることを知るべきだ。そして、サービスとアプリケーションを、私のプロフィール、アクセス権、さらに好みに応じて私に提供するべきなのだ。私は、普通の人間とのコミュニケーションと同じように、話したり、手を動かしたり、触れたりすることで、システムと対話できるようになるべきだ。
われわれは、そのようなことが可能な未来に向かって急速に進んでいる。モノのインターネットにより、ロジック、メモリ、プロセッサ、カメラ、マイク、スピーカー、ディスプレイ、ホログラム、センサーを備えた環境インフラが整備されるからだ。そうした目に見えないインフラを、インターネットに埋め込まれた知性を持ったソフトウェアエージェントと組み合わせることで、上で述べたようなサービスがシームレスに提供されるようになる。一言で言えば、インターネットは基本的に、世界中に張り巡らされた神経系のような役割を果たすようになる。
これが、私が考える将来のインフラの真髄だ。しかし、すでに述べたように、アプリケーションやサービスを予測するのは非常に困難だ。まったく予期しなかったものが、爆発的な驚きとともに、忽然と現れることがある。何ともはや、頻繁に刺激的な驚きをもたらす世界規模のシステムを、われわれは作ってしまった。なんて面白い世の中なんだ!
[原文へ]
(翻訳:Fumihiko Shibata)














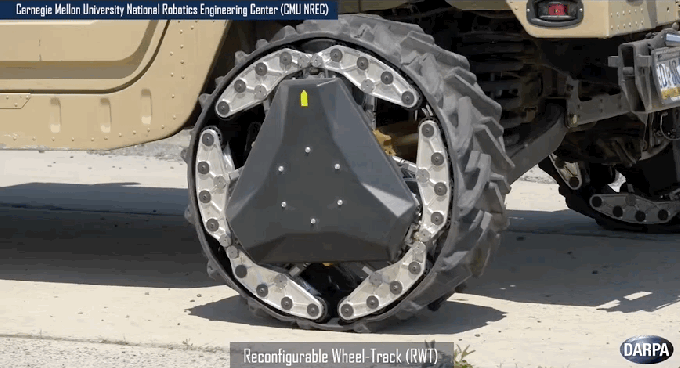


 あるいは、単にコンパクトな地上の
あるいは、単にコンパクトな地上の