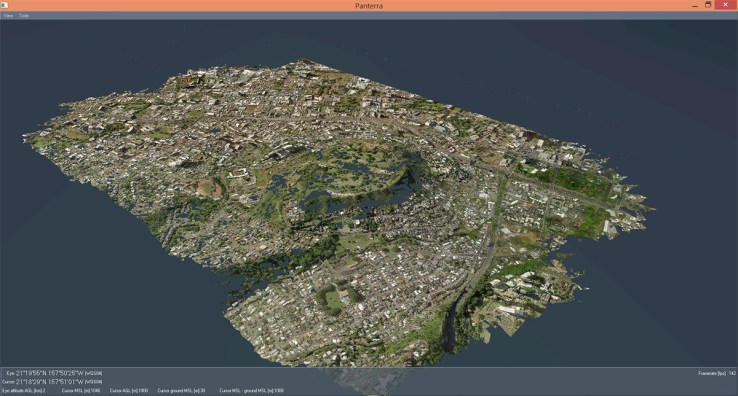Virgin Galactic(バージン・ギャラクティック)は、米国時間5月5日にNASAとの新しい提携契約を公表した。地球上の2点間移動のための高速航空機の開発が目的だ。NASAはこれまでも、超音速航空機の開発を独自に行ってきた。Lockheed Martin(ロッキード・マーティン)が製造した低衝撃波の超音速試験機X-59はその1つだが、今回のVirgin Galacticとその子会社The Spaceship Company(ザ・スペースシップ・カンパニー)との新たな提携契約では、特に持続可能な高速移動技術を民間および商用航空に適用する道を探る。
Virgin Galacticは、このプロジェクトで幸先のいいスタートが切れると確信している。その理由の筆頭に挙げられるのが、現在が保有している航空機の開発、エンジニアリング、試験飛行を行ってきた実績だ。同社にはWhiteKnightTwo(ホワイトナイトトゥー)母機や、その母機から発射されて大気圏と宇宙の境目まで到達できる有翼宇宙船SpaceShipTwo(スペースシップトゥー)がある。Virgin Galacticのシステムは、通常の滑走路から離陸しまたそこへ着陸できるように構成されている。ロケット推進式のSpaceShipTwoは、地球の大気圏と宇宙との境目をかすめて飛行でき、商用宇宙観光として客を乗せ、感動的な眺めや短時間の無重力体験を提供することになっている。
実際、Virgin Galacticの技術は2点間高速移動に最適なように思える。おそらくSpaceX(スペースエックス)とその建造中のStarship(スターシップ)を使った野心的な計画の数々によって一般に認知されるようになった2点間移動は、超高速で地球上の2点をつなぐという考え方だが、大気圏の非常に高い(現在の民間航空路線の高度よりもずっと高い)ところか、もしかしたら宇宙空間を通ることになる。高高度を飛行するのは、空気が薄く空気抵抗も低いために超高速で飛行できるからだ。例えば国際宇宙ステーションは、地球の周回軌道を90分で1周している。
SpaceXによると、Starshipならニューヨークから上海までの移動はわずか40分だという。今の飛行機なら16時間かかる。Virgin GalacticもNASAも、まだまだ所要時間を語れるような段階には至っていないが、単純に比較するならばSpaceShipTwoの最高速度はおよそ時速4000kmなのに対して、ボーイング747はおよそ988kmだ。
Virgin GalacticとNASAのこの新しい提携は、米国Space Act Agreement(宇宙法協定)に基づくものだ。これはそのさまざまな目標、ミッション、計画指令の達成に役立つとNASAが判断した団体の協力を得るためにNASAが利用するという形の協定だ。具体的にどんなものになるかを想像するのは時期尚早だが、Virgin Galacticはその広報資料の中で「乗客の満足度と環境への責任にを重視した、次世代の安全で効率的な高速航空移動のための航空機の開発を目指す」と述べている。そしてそれは「業界のパートナーたち」との共同で行われるとのことだ。
画像クレジット:Mark Greenberg / Virgin Galactic / Getty Images
[原文へ]
(翻訳:金井哲夫)