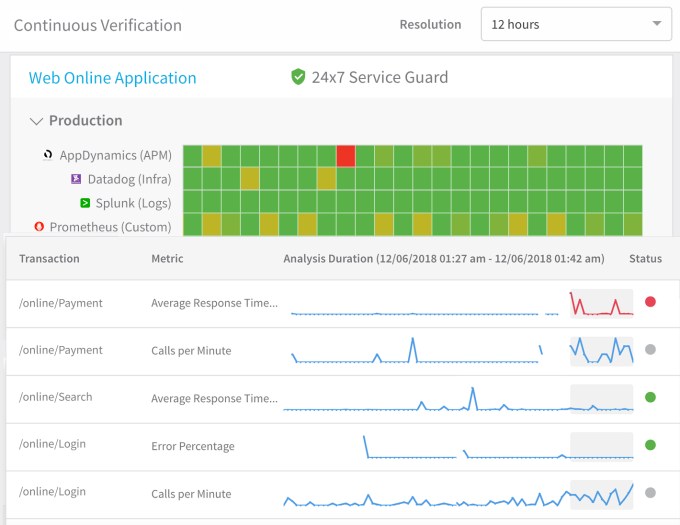DMM.comは12月13日、クイズ買い取りサイト「AQUIZ(アクイズ)」を運営するレイヴンから同サービスの事業譲渡を受けたと発表した。特徴的なのはその金額。DMM.comが支払ったのはたったの1円だ。
レイヴン代表取締役の飯野太治朗氏を含むメンバーである3人は今後DMM.comにジョイン。引き続きAQUIZの運営を続けるとともに、新サービスの創出に取り組む。TechCrunch Japanは飯野氏にインタビューを実施。「1円事業譲渡」の背景を聞いた。
事業の創出と売却を繰り返す
飯野氏はレイヴン創業以前から、新規事業の創出と売却を繰り返してきた。彼が最初に事業を立ち上げたのは19歳のときだ。
それは、業務スーパーで1つ30円のコーヒーを買い、それを喫煙所にいる人々に100円で売るというビジネス。当時大学生だった飯野氏は「バイトのような感覚」としてその事業を始め、1日1時間ほどの労働で月5万円の売上を立てていたという。
「いつか起業家になりたい、特に不動産をやりたい、とは思っていたが実際に行動してはいなかった。ミュージシャンを目指していた友人に『行動に移したら』と指摘したが、それがきっかけで自分の状況を見直し、その足で業務スーパーに行ってコーヒーを買いに行ったのが始まりだった」と飯野氏は語る。
その翌年の2011年、飯野氏は自費で移動販売車を買い、そこでタピオカドリンクを売るというビジネスを始めた。その事業も軌道に乗せることができたが、しばらくするとその移動販売車のビジネスも売却。売却代金を元手にWebサービスの受託開発を手がける企業を設立。
受託開発で稼いだお金で、彼らは2014年11月に現在のレイヴンを設立。フードデリバリー事業やウェディングメディアの「DIAER(ディアー)」を立ち上げる。この2つのサービスは両方ともすでに事業譲渡済みだ。
そして、その後2018年5月にリリースしたのが、今回DMM.comに売却することになった「AQUIZ(アクイズ)」である。
当初、AQUIZはクイズ特化型SNSとしてスタートしたが、2018年7月に現在のクイズ買い取りサイトへとサービスをリニューアル。現在のAQUIZは、ユーザーがPCかスマホでクイズを作成すると、レイヴンがそれを1問10円程度で買い取るというサービス内容になっている。また、運営やスポンサーが用意したクイズに解答することでお金を受け取ることもできる。

1円事業譲渡
移動販売車、フードデリバリー、ウェディングメディアとこれまで何度も事業を作っては売却するということを繰り返してきた飯野氏。しかし、今回の事業譲渡はそれらとはまったく違う性質を持つ。
これまでは事業の価値に対して相応の対価を受け取ってきた飯野氏だが、今回レイヴンが受け取るのはたったの1円。その代わり、レイヴンのチームはDMM.comにジョインし、AQUIZの成長、そしてDMM.com社内における新規事業の創出などの成果に応じて報酬を受け取るという条件になっている。
DMM.com COOの村中悠介氏は、「AQUIZがもつポテンシャルはもちろんだが、レイヴンのチームがもつ新規事業をつくる力と『事業をやり抜く力』を評価した。DMM.comはこれから、そういった人材の層を増やそうとしているところだ」と話す。
この1円譲渡の話を持ちかけたのは、DMMではなく飯野氏だった。その飯野氏は、この1円事業譲渡で起業家にとっての新しいバイアウトの形を示したいと話す。まず“ゼロイチ”で新しい事業を作り、その事業をリソースのある企業に対して“チームと一緒に売却”し、大きなリソースを武器に一気に加速するというやり方だ。その事業の「種」に対する報酬は、最初は1円でもいい。それが育つにつれて後から成果に応じた報酬を受け取れさえすればいい、という考え方だ。
「自力で新規事業の立ち上げを繰り返すうちに、“最強”なのは大きな会社のなかでゼロイチを行うことだと痛感した。DMMの事業マネージャークラスの人たちには、普通の起業家より経験値をもつ人たちがたくさんいる。DMMがもつ経験や、リソースを使えば、僕らがゼロイチでつくった事業を伸ばしていくことができる」(飯野氏)
ただ、この飯野氏がいう新しいバイアウトの形は、VCマネーを軸にした従来のスタートアップが容易に追随できるものではない。レイヴンはこれまで外部資本を受け入れていなかったが、もし外部資本を受け入れていれば、企業そのものや核となる事業を1円で売却することなど許されないだろう。それに、DMMのような、ある意味特殊な企業が“受け皿”として存在している必要がある。
しかし、飯野氏はその条件さえ整えば、「ゼロイチを連続でやりたい、そしてなによりプロダクトを成長させたいと願う起業家には最適な方法だ」と語る。「もちろん、お金のことだけを考えれば、大きく調達して大きく売るという方がいい。しかし、本当にプロダクトを成長させるには外部から得られるお金だけでなく、1を10にしたり、100にするというノウハウも必要になる。その点で、リソースとノウハウの2つをもつDMMは最適な売り先だと思った」(飯野氏)
今回の事業譲渡は、外部資金をこれまで受け入れず、ただゼロイチを連続的に続けていきたいと願う飯野氏と、巨大な非公開企業という立場で大小さまざまなサービスに対するノウハウを蓄積し、社員にも成果に応じた報酬を支払うことができるDMMという「2つの変わり者」がいるからこそ成り立った特殊な例なのかもしれない。
しかし、今後このような新しいバイアウトの形が日本のスタートアップ業界に根付く可能性はゼロではない。個人的には、従来のエグジットのあり方になんの文句もない。ただ、DMMのような企業の存在により、「VCから調達した資金をもとに事業を拡大させ、M&AかIPOでエグジットをする」というスタートアップのエグジットのあり方が「唯一無二のもの」ではなくなる日も来るかもしれない。