
FinTechスタートアップのFinatext(フィナテキスト)は7月30日、総額60億円の資金調達実施を発表した。第三者割当の引受先はKDDI、ジャフコ、未来創生ファンド。また、同時にFinatextでは、KDDIとの業務提携についても明らかにしている。
2013年12月設立、創業5年のFinatextは、金融サービス提供、ビッグデータ解析、証券サービス提供を3柱に、「金融を“サービス”として再発明する」というビジョンを掲げる。
今回の調達について、今朝の速報に続き、Finatext代表取締役CEOの林良太氏と取締役CFOの伊藤祐一郎氏への取材で詳しい話を聞けたので、お伝えしたい。
ユーザー視点サービスで金融の変革を目指す
今回の資金調達のリードインベスターはKDDI。持分法は適用されないが、60億円の出資の大半をKDDIが引き受けるという。創業5年以内の独立した企業としては、Prefered Networksに次ぐ規模の評価額となるのではないかと推測される。
その調達資金は、今年1月に証券業参入を発表した子会社スマートプラスへの投資に充てるという。
スマートプラスが提供する株取引アプリ「STREAM」は、コミュニティ機能と株取引機能がひとつになったプロダクト。4月にSNS機能限定版をローンチし、7月18日から現物取引サービスをスタートした。
STREAMは“従来型”の株式委託手数料が無料、というかなり振り切ったサービスだ。従来型は無料、というからには新方式の取引もある。東京証券取引所(東証)の立会外取引で、東証の株価気配値よりも有利に約定できた場合に、気配値と実際の約定価格の差額の50%を手数料とする「SMART取引」だ。つまり「お得に取引できた分だけ、手数料を払えばいい」という仕組みである。
林氏は「近年、FinTechスタートアップ各社は、これまで投資をしなかった層の人たちにアプローチしてさまざまなサービスを提供してきている。だが、各社の打ち出すサービスは手数料が高い」と話す。
「ある意味、投資したことがない人に高い手数料でサービスを提供するのは、よいのだろうかと。今まで投資しなかった人たちにこそ、障壁を下げて、より安いフィーでサービスを提供しようと、他社よりもう一歩踏み込んだ取り組みが、STREAMだ」(林氏)
ユーザーに寄り添う、という観点から、よりよいUI/UXやコミュニティ機能、加えて手数料0円という施策を打ち出すスマートプラス。その「ユーザーに寄り添う」発想は、そもそも金融サービスの参入障壁の高さから来る、ユーザーの利便性をないがしろにしてきた状況から生まれたと伊藤氏は説明する。
金融業界の近年の動向としては、ベンチャーによるテーマを絞ったニッチなサービス(ロボアドバイザーやテーマ投資など)への進出と、既にほかの顧客基盤を持つ非金融会社(LINEやNTTドコモなど)による参入の2つが挙げられる。「共通するのはユーザーを起点としたサービス設計と、データとテクノロジーの活用だ」と伊藤氏は言う。

「規制への対応やインフラに多額の費用がかかることから、これまでの金融サービスは、ユーザーが接する画面やサービスを高めることができずにいた。Finatextでは、モバイルサービスの設計力とグループ会社のナウキャストが持つビッグデータ解析技術などのテクノロジーを生かして、サービスをユーザー目線から見直す。それを『金融を“サービス”として再発明する』という言葉で表現している」(伊藤氏)
日本の株取引をゼロから変えたい、と話す林氏と伊藤氏。米国で先行する手数料0円の株取引アプリ「Robinhood」を引き合いに、今後のSTREAMの展開について、こう説明する。
「Robinhoodにはコミュニティ機能はなく、投資が初めての人でも使いやすいシンプルさがウリだが、非常にうまくいっている。5年弱で400万以上の口座数を獲得しているが、これは米国No.1のネット証券e-tradeと同水準。評価額も約6000億円と成長している。STREAMはコミュニティ型という違いはあるが、これから5年以内にミレニアル世代で市場シェアNo.1の地位を確立したい」(伊藤氏)
またKDDIとの提携については、スマートプラスだけでなく、グループ全体で取り組んでいく予定だ、と林氏は述べている。「Finatextグループの持つ、UI/UXデザインとサービス構築力、データ解析力と、KDDIグループが提供する幅広い金融サービスラインアップ、顧客基盤やデータとを活用することで、ユーザーへの新しい情報・サービス提供を共同で行っていく」(林氏)



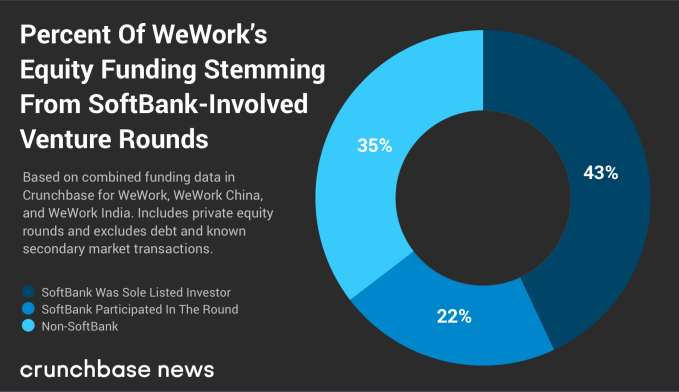
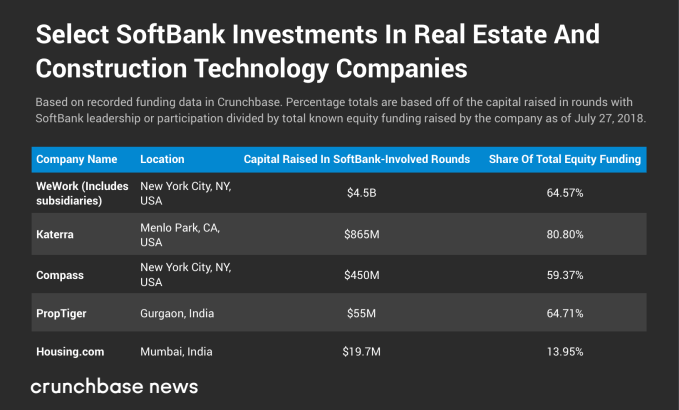






























 「21世紀、最も読まれる物語を生み出す」ことをミッションとしている同社のアプリ、peepは、チャット型UIを使用することで、スマホを使う特に若い世代にとって読みやすい形でコンテンツを提供している。画面をタッチするごとにセリフが出てくるので、ストーリーを目で追うのが非常に簡単だ。僕もかつては文学少年だったが、今の時代、なにも縦読みにこだわる必要はないのだな、と痛感させられた。
「21世紀、最も読まれる物語を生み出す」ことをミッションとしている同社のアプリ、peepは、チャット型UIを使用することで、スマホを使う特に若い世代にとって読みやすい形でコンテンツを提供している。画面をタッチするごとにセリフが出てくるので、ストーリーを目で追うのが非常に簡単だ。僕もかつては文学少年だったが、今の時代、なにも縦読みにこだわる必要はないのだな、と痛感させられた。






