
Switchオンデマンドワーキングブース(画像クレジット:REinvent)
不動産業界は、他の多くの分野に比べて、テクノロジーの採用が遅れている。そこで、2020年春WeWork中国のイノベーションならびにテクノロジー責任者の職を離れたDominic Penaloza(ドミニク・ペナロザ)氏は、アジアの不動産業テックに注力することを決心した。
ペナロザ氏はスタートアップを自分で創業したり、投資するのではなく、その両方の目的を合わせ持つ「スタートアップスタジオ」を開設した。スタジオの名前はREinvent(リインベント)だ(REは「real estate」(不動産)の略。英単語の「reinvent」は「再発明」という意味)。この用語は、社内チームでスタートアップを生み出す組織を指していて、「スタートアップファクトリー」または「ベンチャービルダー」とも呼ばれている。有名な例は、東南アジアのLazada(ラザダ)、アフリカのJumia(ジュミア)の立ち上げで知られるRocket Internet(ロケットインターネット)である。
2018年に自分自身のコワーキングスタートアップであるNaked Hub(ネイキッド・ハブ)をWeWork中国に売却した(未訳記事)連続起業家のペナロザ氏は 、現在、上海、台北、シンガポールで45名のチームを率いている。そのほとんどがWeWorkとNaked Hubで一緒に働いていたメンバーだ。同スタジオは、CEOのペナロザ氏が「squads(分隊)」と呼ぶ単位に組織化されていて、各分隊はプロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニア、AI専門家などで構成されている。また各分隊は同時に4つのプロジェクトに取り組む能力を持っている。
創業者はまた、既存の業者で深く凝り固まった分野に、自身のスタートアップスタジオが取り組めるように、重量級の投資家も招き入れた。REinventの支援者として並んでいるのは、アジア太平洋の大手コワーキング企業であるJustCo (同社はアジア最大の不動産オーナー、例えばシンガポールのソブリンウェルスファンドであるGIC に支援されている)、 多国籍不動産開発業者Frasers Property(フレイザーズ・プロパティ)、日本有数の不動産会社大東建託だ。
REinventは、それが立ち上げる各ベンチャーの完全な所有権を持っているが、投資家3社はそれぞれREinventの株式を所有している。同社は、これまで投資家たちからどれくらいの額を調達額を明らかにするのを拒んでいる。
投資家たちはまた、重要な戦略的リソースに対して貢献してくれていると、ペナロザ氏はTechCrunchとのインタビューで答えている。5月にスタートしたREinventは、すでに2つのベンチャーを立ち上げている。その1つが、自転車シェアと同等の仕組みを使って、個人や企業はワークスペースを予約し、分単位で仕払うことができるSwitch(スイッチ)というベンチャーだ。自転車シェアとの違いは、SwitchがJustCoやFrasersのような第三者の地主と協力する市場であるのに対して、自転車シェア企業はしばしば自転車を自社で供給し運営しているということだ。

Switchアプリのスクリーンショット
現在、その市場はシンガポールの20カ所以上に、2500個以上のデスクネットワークを拡大している。その中には、たくさんのショッピングモールに散在する小規模なオフィスブースも含まれている。新型コロナウイルスのパンデミックによって全世界が物理的に働く場所を再考するように強制されている現在、同社はオンデマンドワークスペースを提案している。
「不動産会社はみな、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)にどのように対応すべきか、各組織が新型コロナを生き延びるにはどうすればよいのか、そして今回のような大きなインパクトを受けなくてもよいようにどのように次のパンデミックに備えれば良いかを検討しています」とペナロザ氏は語る。
一方、設置に柔軟性のあるワークブース(トップ写真)は、モールの所有者、特にeコマースによるオフライン小売が広がる中で、新しいテナントを探している中国のモール所有者たちには魅力的な提案だ。
「eコマースは、新型コロナ以前の段階でも、伝統的な小売モデルを食い尽くしつつありました。中国の不動産開発業者は、ショッピングモールの一部を別目的で再利用しようとしています。【略】 いまではモールの中に、多くの飲食店、体験型店舗、カフェ、コワーキングスペースさえあります」とペナロザ氏はいう。
ペナロザ氏は、自身のオンデマンドワークスペース構想に関する早期バージョンの実験を、WeWork中国で行っていた。店舗のパブリックスペースをメンバーショップなしで使えるようにして、ミーティングやリモートワークにスターバックスを使用するプロフェッショナルたちに、より静かな環境とより良いWi-Fiを提供して、その心を掴んだのだ。
REinventがローンチしたもう1つのプロダクトは、空間分析とソーシャルディスタンス検出のためのソフトウェアであるSixSense(シックスセンス)だ。
「不動産は多くの人が考えているものではありませんが、それは地球上で最大の産業の1つです」とペナロザ氏は語る。「アジアと中国の不動産テックはきわめて初期段階ですが、それは成長しています」。
関連記事:WeWorkが中国国内で提供する新しいサービスは、スターバックスの良きライバル?
カテゴリー:VC / エンジェル
タグ:REinvent、不動産テック
[原文へ]
(翻訳:sako)








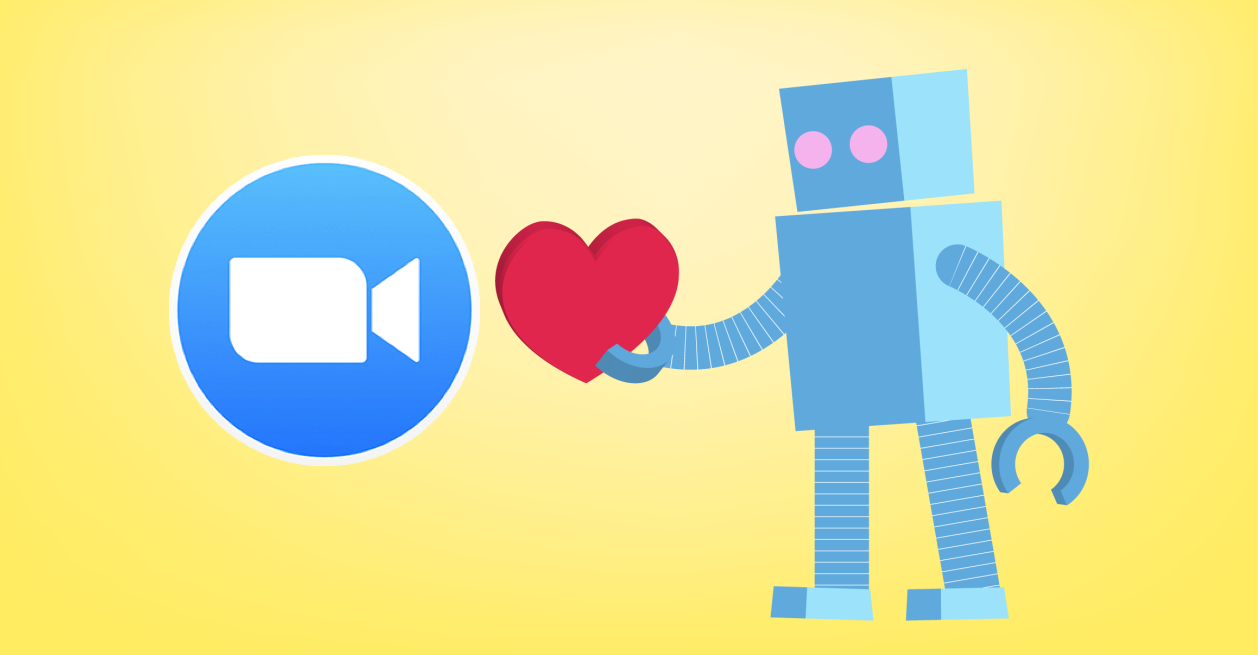




































 加盟する不動産会社は東京23区で約150社、登録エージェントは170名ほどになっている。EQON代表取締役の三井將義氏によると、リニューアル前と同様「担当者はかなり厳選している」とのこと。「実務経験で平均15年、年間の売買件数は担当者全体で延べ4000件ほどと、実績のあるエージェントがそろっている。担当者のハズレはない、という水準が維持できている」(三井氏)
加盟する不動産会社は東京23区で約150社、登録エージェントは170名ほどになっている。EQON代表取締役の三井將義氏によると、リニューアル前と同様「担当者はかなり厳選している」とのこと。「実務経験で平均15年、年間の売買件数は担当者全体で延べ4000件ほどと、実績のあるエージェントがそろっている。担当者のハズレはない、という水準が維持できている」(三井氏) 三井氏によれば、AI査定サービスは2015年以降、日本で20弱ほど存在しているとのこと。最近では5月に、GA technologiesが運営する「RENOSY」でAI価格査定などを提供する中古マンション売却サービス「
三井氏によれば、AI査定サービスは2015年以降、日本で20弱ほど存在しているとのこと。最近では5月に、GA technologiesが運営する「RENOSY」でAI価格査定などを提供する中古マンション売却サービス「






 東京都内を中心に中古マンションの買い取り、販売を手がける「
東京都内を中心に中古マンションの買い取り、販売を手がける「
 すむたす代表取締役を務める角 高広氏(写真左)によると「売却査定を受けた時点から、司法書士が必要な書類の作成などを同時並行で進めるため最短2日間というスピードでの売却を実現できた」とのこと。司法書士事務所とは特別な契約を結んでおり、実際に売却に至らなかった場合は全額ではなく進捗度合いによる歩合で事務所に作業料が支払われるという。
すむたす代表取締役を務める角 高広氏(写真左)によると「売却査定を受けた時点から、司法書士が必要な書類の作成などを同時並行で進めるため最短2日間というスピードでの売却を実現できた」とのこと。司法書士事務所とは特別な契約を結んでおり、実際に売却に至らなかった場合は全額ではなく進捗度合いによる歩合で事務所に作業料が支払われるという。


