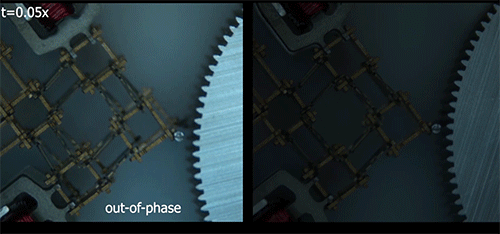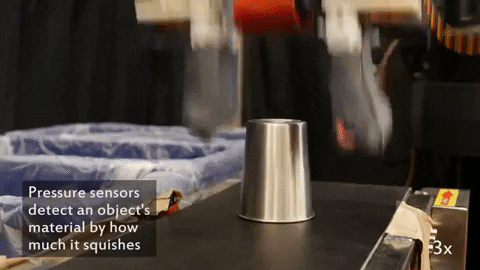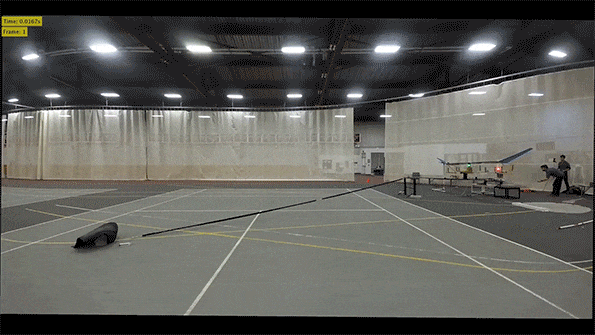25年間におよぶ研究の末、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちは、核融合商用化への扉の鍵を手に入れたようだ。
Commonwealth Fusion Systemsは、その研究の成果だ。消費者にクリーンで安定した電力を届けるために太陽のパワーを制御するという、数十年間にわたる研究開発の上にこのスタートアップは成り立っている。彼らはこのほど、米国で最も資金力のある民間投資家たちから、商用化を推し進めるための5000万ドル(約54億円)の追加投資を受けた。
同社はその技術を発表し、イタリアのエネルギー企業Eni、世界でもっとも裕福な男女によって設立された投資コンソーシアムであるBreakthrough Energy Ventures、そしてMIT自身の未開拓分野の技術を対象とした投資手段The Engineから、最初に6400万ドルの資金を集めている。
今回は、Steve Jurvetsonが創設した投資企業Future Ventures、Khosla Ventures、Chris SaccaのLowercase Capital、Moore Strategic Ventures、Safar Partners、Schooner Capital、 Starlight Venturesが参加している。
Commonwealth Fusion Systemsは2014年、核融合の経費削減を目指す学生の課題として始まった。このクラスは、当時MITのPlasma Science and Fusion Center(プラズマ科学および融合センター)主任だったDennis Whyteが教鞭を執っていたのだが、そこでARC(Affordable、Robust、Compact:手頃な価格で頑丈でコンパクトの略)と彼らが呼ぶ新しい融合炉技術が考案された。それでも数十億ドルという値札が付く、投資家も尻込みしたくなる規模の技術だった。
そこで彼らは製図台に戻り、エネルギー利得を生む(投入したエネルギーより出力されるエネルギーが上回る)必要最低限の核融合炉の検討を始めた。
エネルギー利得は、ほとんどの核融合炉技術において、もっとも難しい課題となっている。核融合を成功させた研究所やプロジェクトはいくつかあるが、それを維持しつつ、投入エネルギーよりも多くのエネルギーを引き出すことは、難題のまま残されている。
欧州のITER核融合炉は、200億ドル(約2兆1500億円)をかけた多国籍プロジェクトだが、2045年に達成予定の発電量の、いまだ60パーセントのあたりに留まっている。北米に目を戻すと、TAE TechnologiesとGeneral Fusionの2社が核融合パワーを安価に生み出す研究を行っている。イギリスでは、First Light FusionとTokamak Energyがそれぞれ独自の方法で核融合発電に取り組んでいる。
Commonwealth Fusion Systems(CFS)の最高責任者であるBob Mumgaard(ボブ・マムガード)氏の目からはかは、すべてが計画通りに進んでいるように見えている。順調だ。「CFSは民間核融合を実現させ、本質的に安全で、世界的にスケーラブルで、カーボンフリーで、無限のエネルギー源を供給するための軌道に乗っています」と彼は声明の中で述べている。
CFSの専門家たちは、可能なかぎり小型の核融合炉を2025年までに完成させることにしてるが、それは核融合反応を閉じ込めておくためのMITが独自に行ってきた磁石技術の研究によるところが大きい。実際、資金の大半は、CFSが核融合反応を閉じ込める完全な磁石技術の構築に向けられている。最終目標は、熱として、または蒸気でタービンを回して発電して、50メガワットを生み出させることだ。
環境に多大なリスクのある原子炉と違い、核融合発電所は、通常の工業施設とほぼ同じ区分になるだろうとMumgaardは言う。「核融合度のハザードプロファイルは、これからも工業施設(のカテゴリー)に留まります。法律はありますが、核融合炉を実際に作った人がまだいないので、前例がないのです」
マムガード氏は、200メガワット級の融合炉も思い描いている。それなら、風力発電ファームや太陽光発電所に置き換えることができる。
「前進と、何を目指すのかの両方を対比させて、常に監視しておく必要があります」と彼はいう。「電力網において二酸化炭素排出量を劇的に減らせる手段をまだ手にしていないというのが、一般の人々のほぼ一致した意見です。再生可能エネルギーも含め、最大の利得を生むものとは、実用規模で最も利得の高いものとは、1カ所につき数百メガワットの電力を生み出せる方式を意味します」。
マムガード氏によれば、再生可能エネルギーだけでは現代の大都市圏の需要を満たすことはできないという。「現代のライフスタイルを支えるための電力として、凝縮されたエネルギー源を求める声が強いのです」。
この問題に対する人々の意見は、次第に分かれつつある。とりわけ、エネルギー政策を考える団体の中で噂されていたグリーン・ニューディール政策を支持するサンライズ・ムーブメントの賛同者で、核エネルギーに反対する人たちの間にも分裂が起きている。しかし、エネルギーの専門家の大半は、混合型のアプローチを提唱し、ゼロエミッションを実現するためには(それが科学コミュニティの最終ゴールでもあるが)、核エネルギーをそこに加える必要があると指摘している。
「私たちは、この20年間、核融合に適切なクリーンエネルギーへの投資機会を探ってきました」と、Future Venturesの最高責任者であるSteve Jurvetson(スティーブ・ジャーベンソン)氏は声明の中で述べている。「核融合をビジネスに転換できる企業を求めいましたが、ついにCommonwealth Fusion Systemsと出会いました。彼らのアプローチを支えるハードサイエンスは、彼ら自身と加えてこの分野の世界中のリーダーたちによって実証されています。高度なエンジニアリングによって、CFSは太陽周期のパワーを制御する力を得ようとしています。それは世界を変え、あらゆる問題が改善されるクリーンなベースロード電力の時代を招くものです」
[原文へ]
(翻訳:金井哲夫)