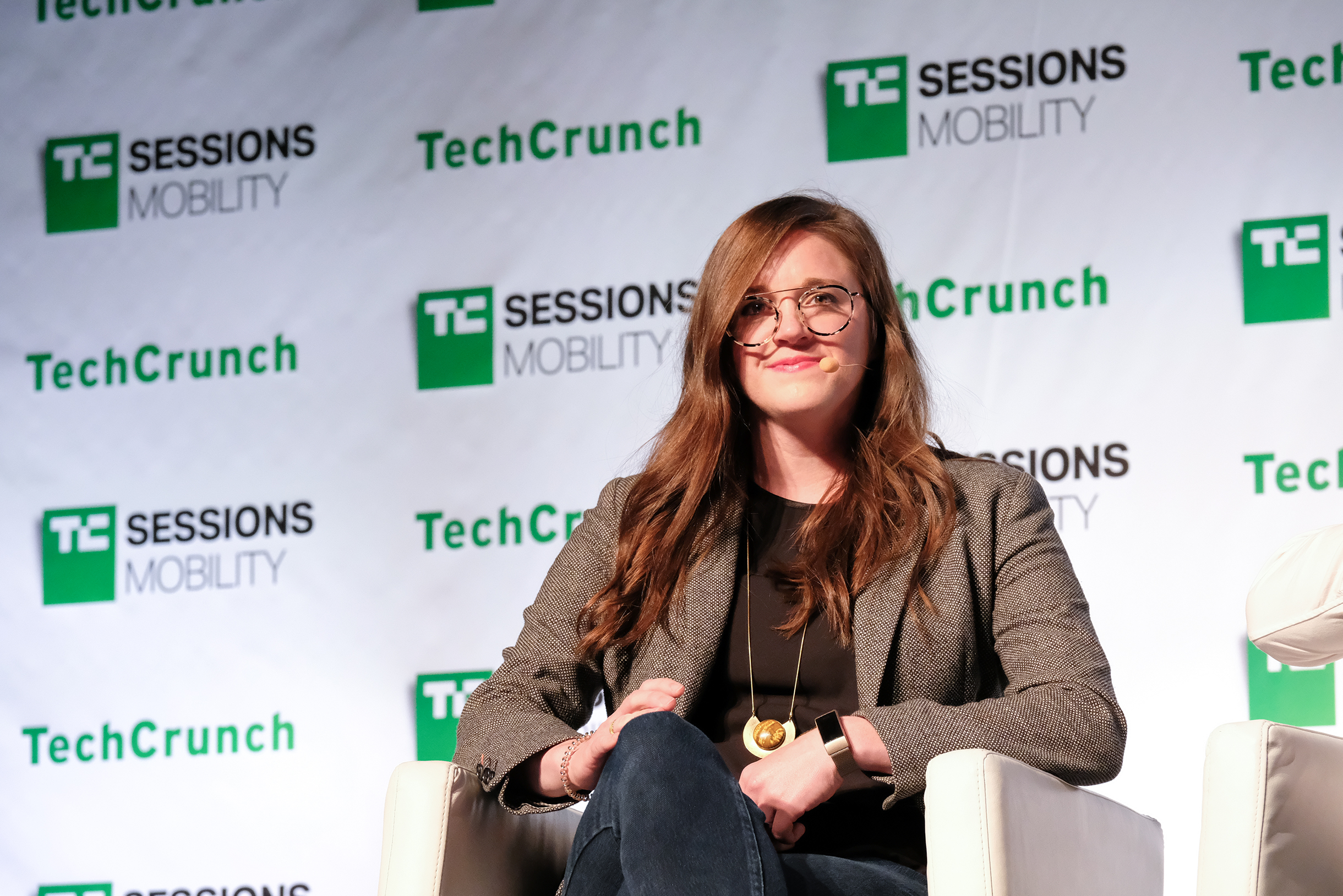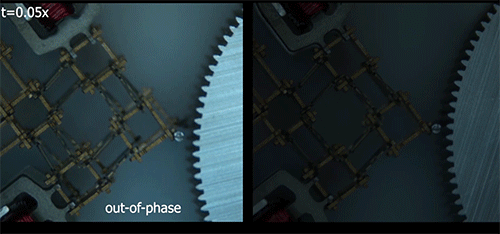科学はエキサイティングなはずだが、実際にはおそろしく退屈なこともある。何千回も同じことを繰り返す実験もあるが、そんなものは自動化してほしいところだ。そこでMITの科学者が作ったロボットは、ある種の実験の結果を観察し、フォローアップを計画する。このロボットは、最初の1年で10万回の実験を行った。
流体力学という分野は、大量の複雑で予測不可能な力を扱い、それらを理解する最良の方法が同じことを何度も繰り返して一定のパターンを見つけることだったりする。これはあまりにも単純化した言い方だが、ここでは流体力学の詳しい説明はやめておこう。
繰り返して観察することを要する現象のひとつが、渦励振動(Vortex-Induced Vibration)だ。この一種の撹乱現象は、たとえば水上をより滑らかに効率的に航行する船を設計するときなどに重要になる。そのためには、船が水の上を進む様子を何度も何度も観察しなければならない(自動車のボディーの空気抵抗を減らすためにも、同種の実験を行う)。
でもこれは、ロボットにぴったりの仕事だ。しかもMITの科学者がIntelligent Tow Tank(インテリジェントな曳航水槽、ITT)と名付けた実験用ロボットは、水上で何かを引っ張るという物理的な仕事をするだけでなく、結果を知的に観察し、ほかの情報も得るためにセットアップを変え、価値ある報告が得られるまでそれを繰り返す。
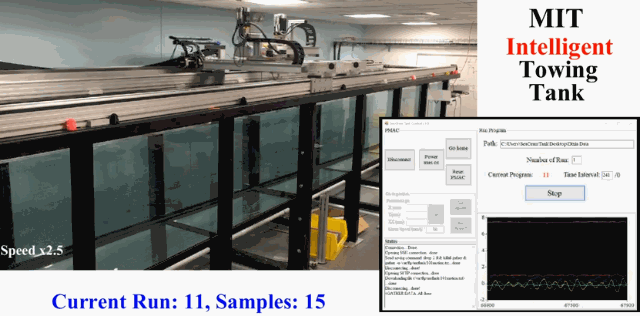
今日Science Robotics誌に掲載された彼らの研究論文には「ITTはすでに約10万回の実験を済ませており、本質的には博士課程の学生が在学中に2週間ごと実施する実験を完了しています」と書かれている。
ロボット本体の設計よりも難しかったのは、流体系の表面の水流を観察して理解し、より有益な結果を得るためにフォローアップを実行する部分のロジックだ。通常は人間(院生など)が毎回の実行を観察してランダムに変わるパラメータを計り、次にどうするかを決める。でもその退屈でかったるい仕事は、優秀な科学者に向いているとは言えない。
だからそんな機械的な繰り返し作業はロボットにやらせて、人間は高レベルの概念や理念にフォーカスすべきだ。彼らの研究論文は、同じように実験を自動化するCMU(カーネギーメロン大学)などのロボットを紹介している。
彼らの研究論文では「これによって、実験を伴う研究にパラダイムシフトがもたらされ、ロボットとコンピューターと人間がコラボレーションして発見を加速し、これまでのやり方では無理だったような大きなパラメータ空間でも迅速かつ効果的に探索できるようになるだろう」と書かれている。インテリジェントな曳航水槽を記述している研究論文はここで読める。
[原文へ]
(翻訳:iwatani、a.k.a. hiwa)


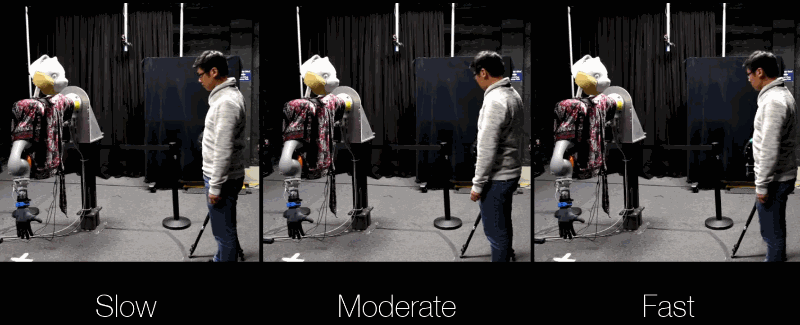




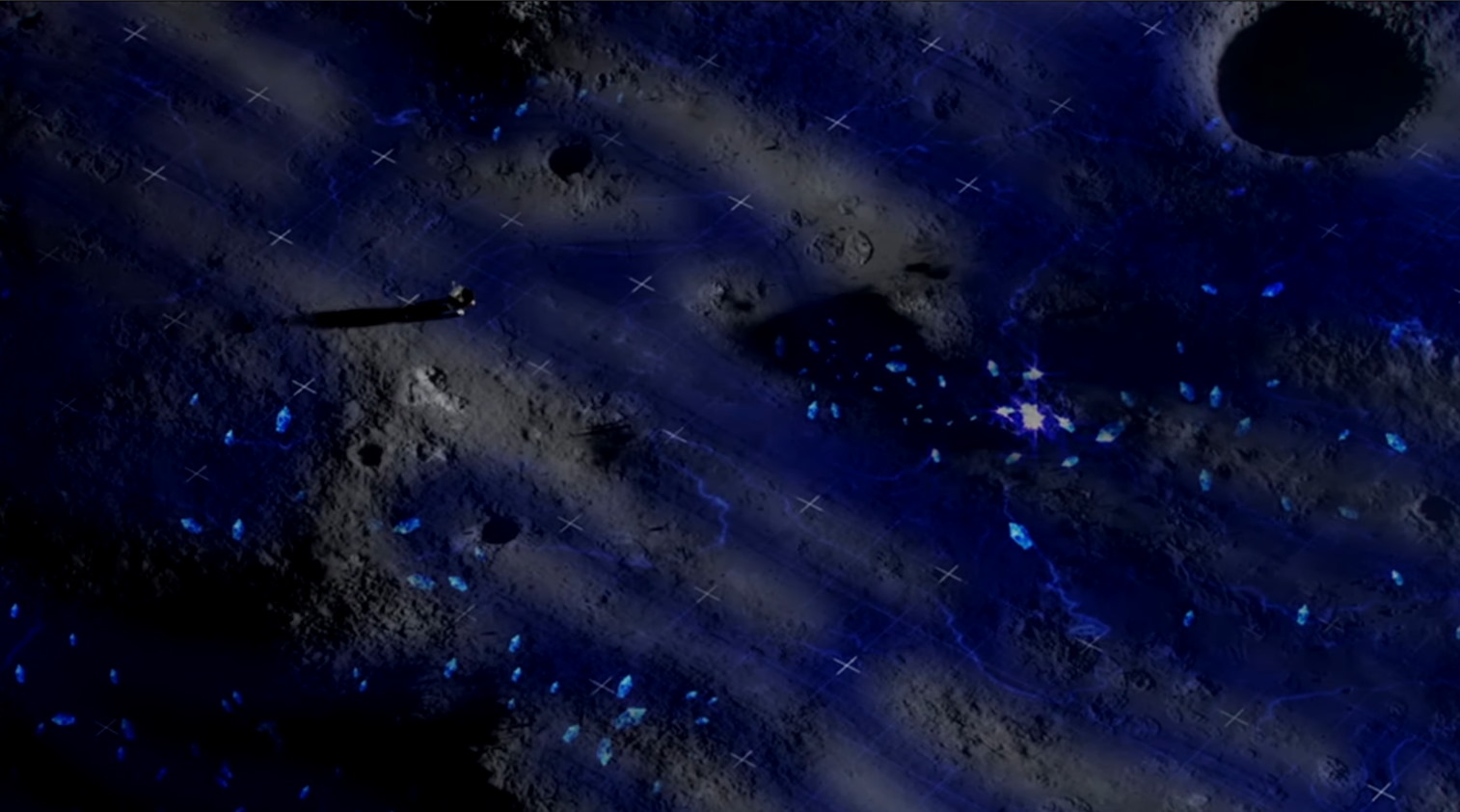











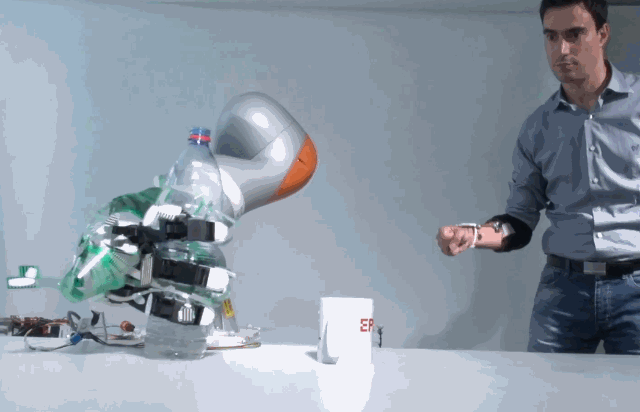



 トヨタはPreferred Networksのために数十台のHSRユニットを貸与し、今後3年間にわたり研究成果と知的財産を共有しながら、成果の活用に制限をもうけずに研究開発を進める。
トヨタはPreferred Networksのために数十台のHSRユニットを貸与し、今後3年間にわたり研究成果と知的財産を共有しながら、成果の活用に制限をもうけずに研究開発を進める。