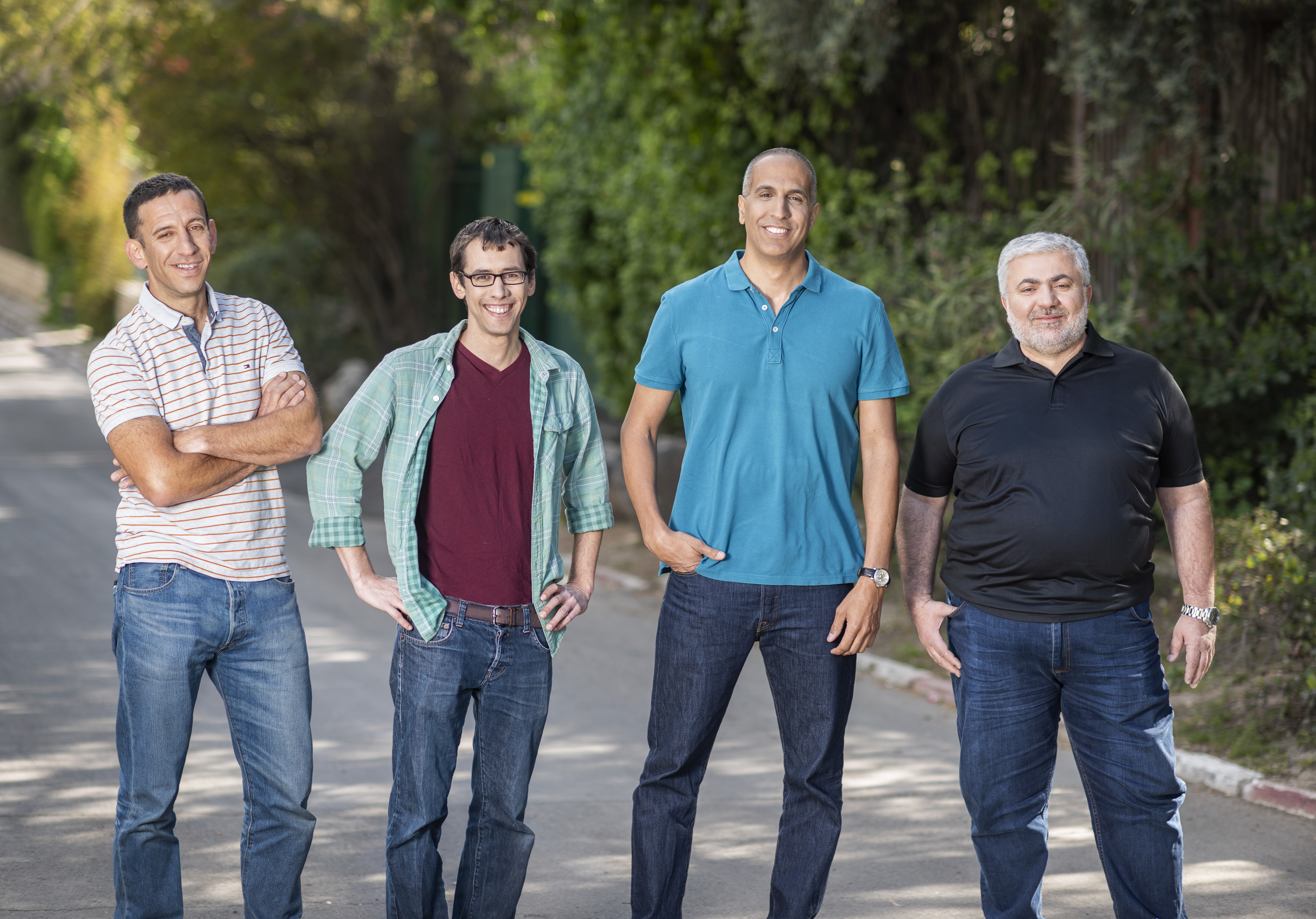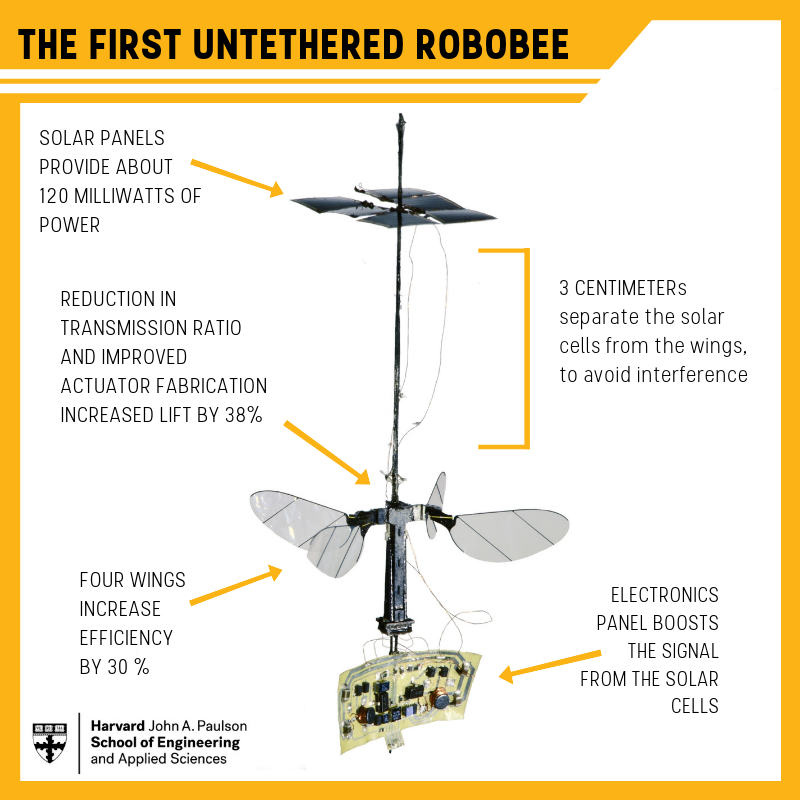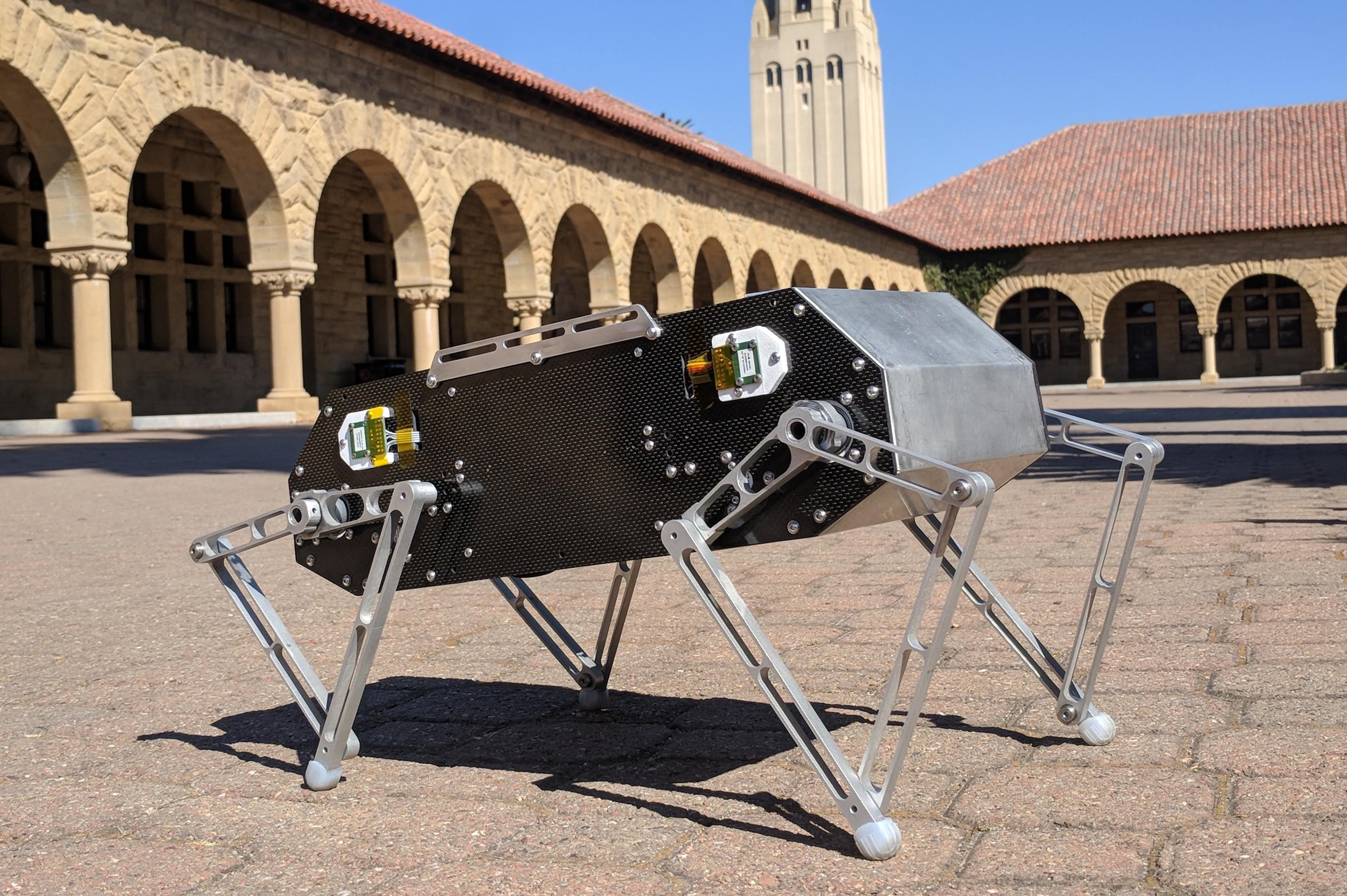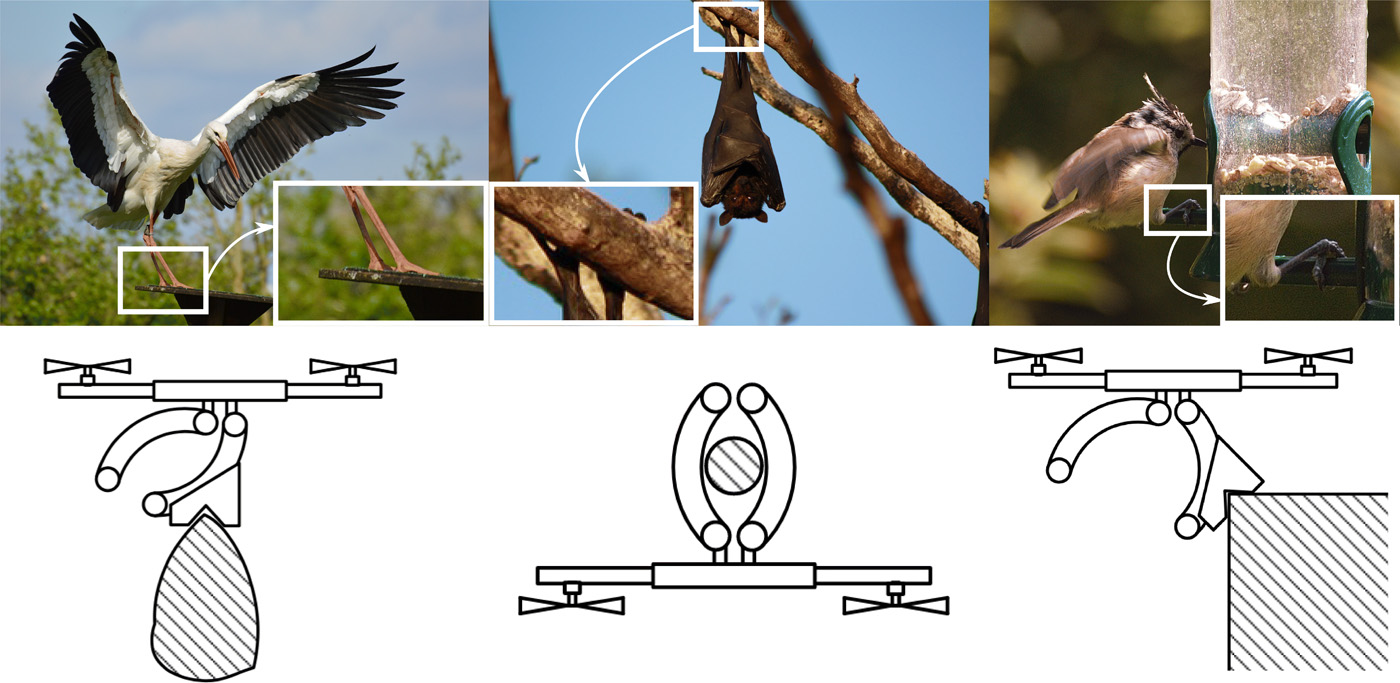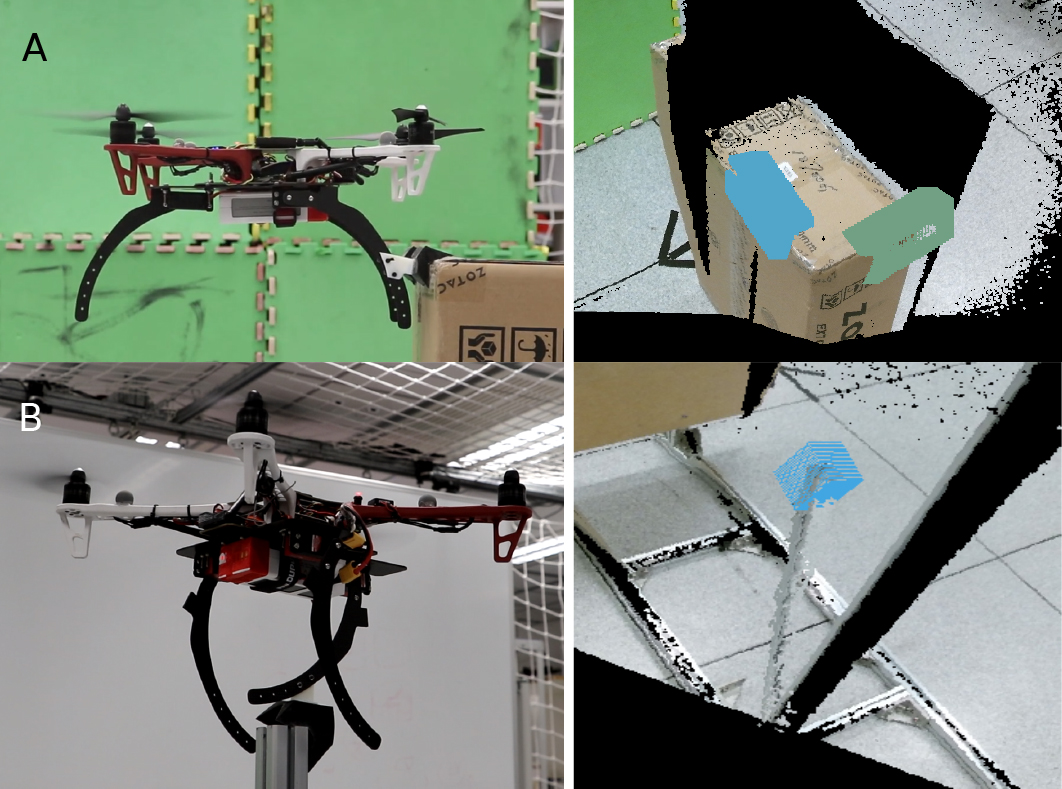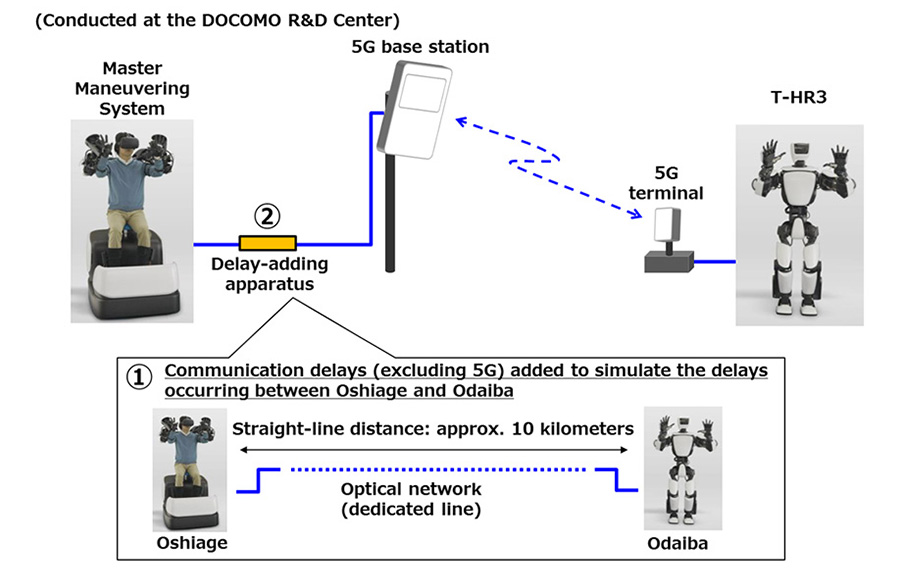オートメーションへの地殻変動的な移行を、失職について語らずに議論することは不可能だ。テクノロジーに反対する人びとは、「熟練技能を必要としない」職業分野で大規模な失業が起きることをおそれて批判する。一方テクノロジー肯定派の人たちは、その種の記事は大げさになりがちだと言う。でも労働力のシフトは、太古の昔からそうであったように今も起きている。
しかし今週行われたSXSWで、ニューヨーク州出身の女性下院議員アレクサンドリア・オカシオ=コルテス(Alexandria Ocasio-Cortez)氏は、まったく違う見解を述べた。
The Vergeによると、彼女はある質問への答でこう述べている。「自動化で仕事を失うという妖怪を怖がるべきではない。自動化は、むしろ喜ぶべきだ。でも、それを喜べないのは、私たちが、仕事がなければ死ぬという社会に生きているからだ。そして、そのことの中核にあるものこそが、私たちの本当の問題だ」。
聴衆からの質問に対するこの答は、オートメーションに関するこれまでのさまざまな会話の中で、あまり聞かれない見方だ。いちばん多いのは、業界を代弁するような人びとが、テクノロジーがこれまでの「退屈で汚くて危険な」仕事を置換すると主張する説。多くのロボット賛美派が言うには、それらは本当は誰もがやりたがらない汚れ仕事だ。
【ウィリアム・ギブスン「これは政治家が言う言葉としては衝撃的に知的だ」】
一方オカシオ=コルテス氏の答は、彼女の民主社会主義者としての見解を述べている。それは、正しく実装されたテクノロジーは労働者を資本家のシステムから解放できる、今は労働者が、自分の存在と生計をそのシステムに冷酷に縛り付けられている、と見る議論だ。
この新人女性議員は、オートメーションが社会にもたらす利益を指摘して、自分の立場を明らかにしようとする。
The Vergeの引用によると、オカシオ=コルテス氏の発言はこうだ。「オートメーションに関して、私たちは喜ぶべきだ。それによって、可能性としては、自分自身を教育する時間が増えるし、アートを創る時間や、科学にお金をかけて研究する時間、発明に集中する時間、宇宙に行く時間、自分たちが今住んでる世界をエンジョイする時間も増える。必ずしもすべての創造性が賃金に結びついていなくてもよいのだから」。
オカシオ=コルテス氏は、ビル・ゲイツ氏がQuartz誌のインタビューで語っていることを引用して、このビジョンを実現するためにはロボットに課税することもひとつの方法だ、と言う。彼女はこう言ったそうだ。「ゲイツ氏が本当に言ったのは企業に課税することだけど、『ロボットに課税する』のほうが言いやすいから」。
オートメーションに関する質問への彼女の答は、未来に関してとりわけ楽観的な一部のライターたちの喝采を浴びた。
小説家のウィリアム・ギブスンは、「これは政治家が言う言葉としては衝撃的なほど知的だ」とツイートした。それは少なくとも、今や陳腐化している話題への新鮮な観点であり、われわれ全員が共有するテクノロジーの未来をめぐる重要な会話に、生命(いのち)を吹き込むものだ。
オートメーションが向こう数十年で雇用に大きな影響をもたらすことは、疑問の余地がない。倉庫などの業種では、その多くをすでに目にしてきた。この主題に関するすべての研究が認めているのは「破壊される」雇用の数は数千万以上だが、新たに“創られる”数はその膨大な数の小部分にすぎないことだ。
でも、この女性下院議員のコメントはそれらの具体的な数とは関係なく、たぶん我々がこれまでずっと間違った問いを尋ねていたのではないかということを示唆している。
[原文へ]
(翻訳:iwatani、a.k.a. hiwa)