
テクノロジー業界において、この10年はスマートフォンの時代だった。2009年時点では、Symbian OSがまだ支配的な「スマートフォン」のOSだったが、2010年にはiPhone 4、Samsung Galaxy S、Nexus Oneが発売され、現在、AndroidとiOSがアクティブなデバイス数で合計40億台を誇る。スマートフォンとアプリは、もはや破壊的な新しいプラットフォームではなく成熟した市場だ。次は何がくるのだろうか。
その問いは、次に必ず何かがくることが自然の法則であることを前提としている。この前提が正しそうに見える理由は簡単だ。過去30年以上にわたり、それぞれの分野が重なっている、世界を変える3つの大きなテクノロジープラットフォームへのシフトを我々は経験してきた。3つの分野とはコンピューター、インターネット、スマートフォンのこと。いずれ4つめが地平線のかなたに現れることは避けられないように思える。
AR/VR、ブロックチェーン、チャットボット、IoT、ドローン、自動運転車(自動運転車はプラットフォームだ。まったく新しい周辺産業が爆発的に生まれる)と、過去数年間、次の候補に事欠くはなかった。しかし、いずれも楽観的な予測をはるかに下回っていることに気づくだろう。何が起こっているのだろうか。
PC、インターネット、スマートフォンの成長の勢いが、これまで揺らいだりつまづくようなことはなかったように思える。ここに、インターネットのユーザー数の推移がある。1995年の1600万人から1998年には1億4700万人に増えた。2009年以降のスマートフォンの販売推移はこのとおりだ。Androidはわずか3年で100万台未満から8000万台以上になった。これが、主要なプラットフォームへのシフトだ。
PC、インターネット、スマートフォンの成長をAR/VR、ブロックチェーンといった候補のそれを比べてみよう。不公平な比較だとは思わない。それぞれの分野が「大きな何か」になると主張する事情通がいる。もっと手堅い予測をする人々でさえ、ピークの水準は小さいかもしれないが、少なくともスマートフォンやインターネットと同じ成長の軌道を描くといういう。だが実際のところ、どうだろうか。
AR / VR:2015年にさかのぼるが、筆者は非常に有名なVCと話をした。そのVCは自信満々に、2020年までに最低でも年間1000万台のデバイスが出回ると予想した。実際どうなったか。2017年から2019年までにかけて370万台、470万台、600万台と推移し、Oculusは再編中だ。年間27%の成長率は確かに悪くない。だが「一貫して27%」という成長率は、次の大きな何かになると主張するには、少し心配になるといったどころではない。「3年で10倍」からはさらに遠い。2020年までにMagic Leapが深刻な状況になると予想した人はほとんどいなかった。やれやれ。他のAR / VRスタートアップは「残念な」状況だというのが最も的確な説明だ。
ブロックチェーン:ビットコインは正常に機能していて、2010年代にテクノロジーに起こった最も奇妙で興味深いことだと思う。しかし残りのブロックチェーンはどうだろうか。筆者は広い意味で仮想通貨の信奉者だ。だが、2017年半ばに仮想通貨の敬虔な信者に対して、2019年末までに企業向けブロックチェーンが実質的に死んでしまうとか、分散型アプリケーションの使用が依然として数千台に留まっているとか、スモールビジネスへの担保付き貸し付け以外に本当の新しい利用事例は発生しなかったなどと言おうものなら、彼らを怒らせることになったはずだ。そして、まだその段階にとどまっている。
チャットボット:真面目な話、チャットボットはついこの間まで未来のプラットフォームとしてもてはやされていた(Alexaは、端的に言うとチャットボットではない)。「世界は書き直されようとしており、ボットは将来大きな存在になる」。これは実際の発言からの引用だ。Facebook Mは未来のものだったが、もはや存在しない。マイクロソフトのTayも未来のものだったが、もはや存在しない。Zoに取って代わられた。ご存知でしたか。筆者は知らなかった。そして今やそのZoも存在しない。
IoT:最近の記事のタイトルをいくつか見てみたい。「なぜIoTが一貫して予測を下回っているのか」「IoTは死んだのか」「IoT:昨日の予測と今日の現実」。ネタバラしをすると、最後のタイトルは、現実が予測を超えて成長したことについての記事ではない。むしろ「現実は予想を超えてバラ色ではないことが判明した」といったものだ。
ドローン:現在、ドローンの領域では本当にクールなことがたくさん起こっている。筆者は何でも最初に試したい人間だ。しかし、ドローンによる物理的な荷物配送ネットワークを形成の実現には程遠い。Amazonは2015年にPrime Airの計画をもったいぶってチラ見せし、2016年に最初のドローンによる配送を開発した。世の中はすばらしい出来事が起こることを期待していた。そしてまだすばらしい出来事を期待しているが、少し期待しすぎている部分はあると思う。
自動運転車:我々にはもっと多くのことが約束されていた。Elon Musk(イーロン・マスク)氏の誇張についてだけ言っているのではない。2016年からこういうタイトルの記事が出始めた。「2020年までに1000万台の自動運転車が路上に」「5年後に真の自動運転車が登場、フォードが発表」。一応、Waymoの好意で、フェニックスでクローズドパイロットプロジェクトが実施されているが、それはフォードが話していたものではない。フォードは「ハンドル、ブレーキ、アクセルペダルがない自動運転フォード車が、5年以内に大量生産される予定だ」と言っていた。それは、今から18カ月後のことになる。「1000万台」の予測に至っては12カ月しかない。筆者が多少の懐疑論を展開しても許してもらえると思う。
もちろん、これらは成功していないようだということを意味しているのではない。AirPods、Apple Watch、Amazon Echoファミリーなど、多くの新製品がヒットした。ただし、これら3つはすべて、新しいプラットフォームというよりも新しいインターフェイスだ。ゴールドラッシュなどではなく、1つの銀の鉱脈にすぎない。
機械学習やAIをリストから外したことに気づいているかもしれない。実際には定性的な飛躍が確かにあったが、a) 急成長が続くというよりは、Sカーブの平坦部分に突入してしまったという一般的な懸念がある b)いずれにしろ、AIはプラットフォームではない。さらに、ドローンと自動運転車はいずれも汎用自動化という名の壁に直面している。つまりAIの壁だ。AIは多くの驚くべきことが行えるが、2020年に1000万台の自動運転車が走る、というかつての予想は、AIがあれば自動運転は十分に可能だと予測したことを意味しているが、実際のところ予想よりもずっと遅れている。
いずれのテクノロジーも、次の10年を決定づける存在になり得る。ただし、考慮しておくべきもう1つの点として、いずれもそうはならないかもしれないという可能性があることだ。あるテクノロジープラットフォームが成熟し始めると同時に、別のプラットフォームが必然的に台頭し始めるというのは、反論の余地がない法則ではない。「次の大きな何か」の前に、長い空白があるのではないか。その後、2、3つのことが同時に発生するかもしれない。もしあなたが、今度こそその店に入ろうとしていると公言しているなら、筆者は警告したい。店の前で長い間待つかもしれないということを。
画像クレジット:Robert Basic / Wikimedia Commons under a CC BY-SA 2.0 license.
[原文へ]
(翻訳:Mizoguchi)


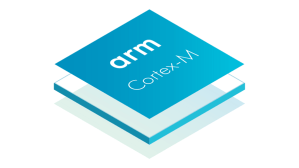



 モッチッチ ステーションで食べられるのは、その名のとおりモチモチした食感が特徴のインスタント食品「モッチッチ」シリーズの焼きそばとラーメン(ワンタン麺)。店内には立食用のテーブルが5席用意されており、5人が入店して満員になると自動ドアが開かなくなる仕組みだ。店内の客が誰か一人退店しないと、6人目の客は店内に入れない。
モッチッチ ステーションで食べられるのは、その名のとおりモチモチした食感が特徴のインスタント食品「モッチッチ」シリーズの焼きそばとラーメン(ワンタン麺)。店内には立食用のテーブルが5席用意されており、5人が入店して満員になると自動ドアが開かなくなる仕組みだ。店内の客が誰か一人退店しないと、6人目の客は店内に入れない。 モッチッチの貯蔵庫は計量器メーカーであるイシダの計測器を内蔵しており、客が商品を手に取って貯蔵庫の扉を閉めると、全体の重量から減少したぶんを計算して、客が手に取ったモッチッチの個数を算出する。
モッチッチの貯蔵庫は計量器メーカーであるイシダの計測器を内蔵しており、客が商品を手に取って貯蔵庫の扉を閉めると、全体の重量から減少したぶんを計算して、客が手に取ったモッチッチの個数を算出する。

 価格はいずれも212円で、交通系ICカードもしくはクレジットカードで決済する。内蔵の液晶パネルに決済金額が表示されたら決済方法を選んで、決済端末にICカードをかざせばいい。クレジットカードの場合は残念ながらタッチ決済(コンタクトレス決済)には対応しておらず、決済端末の下部に備わっているカードリーダーにクレジットカードを差し込んで暗証番号を入力する必要がある。ちなみに、決済端末はCoiny(コイニー)製。Coinyは決済サービスを提供するスタートアップで、現在は事業持株会社であるヘイの傘下企業だ。
価格はいずれも212円で、交通系ICカードもしくはクレジットカードで決済する。内蔵の液晶パネルに決済金額が表示されたら決済方法を選んで、決済端末にICカードをかざせばいい。クレジットカードの場合は残念ながらタッチ決済(コンタクトレス決済)には対応しておらず、決済端末の下部に備わっているカードリーダーにクレジットカードを差し込んで暗証番号を入力する必要がある。ちなみに、決済端末はCoiny(コイニー)製。Coinyは決済サービスを提供するスタートアップで、現在は事業持株会社であるヘイの傘下企業だ。 決済終了後は、モッチッチ貯蔵庫の左側のテーブルに設置されている、電気ポットもしくはウォーターサーバーからモッチッチのカップにセルフサービスでお湯を入れる。割り箸などもこちらに用意されている。このテーブルを注意深く見ると、それぞれの置き場がテーブルとは独立していることがわかる。
決済終了後は、モッチッチ貯蔵庫の左側のテーブルに設置されている、電気ポットもしくはウォーターサーバーからモッチッチのカップにセルフサービスでお湯を入れる。割り箸などもこちらに用意されている。このテーブルを注意深く見ると、それぞれの置き場がテーブルとは独立していることがわかる。 実はここにもイシダの計量器が仕込まれており、モッチッチの調理に必要なお湯の量である320mlを計測している。具体的には、お湯が減ったぶんの総重量の変化を認識する。計測器が320mlのお湯が注がれたと判断すると、自動的にモッチッチの標準調理時間である5分のタイマーがスタートする仕組みだ。なお割り箸置き場の計測器は、補充の目安を判断するためのもの。
実はここにもイシダの計量器が仕込まれており、モッチッチの調理に必要なお湯の量である320mlを計測している。具体的には、お湯が減ったぶんの総重量の変化を認識する。計測器が320mlのお湯が注がれたと判断すると、自動的にモッチッチの標準調理時間である5分のタイマーがスタートする仕組みだ。なお割り箸置き場の計測器は、補充の目安を判断するためのもの。 あとは、お湯を投入したモッチッチを持って5席ある立食スペースのいずれかに移動すると、各スペースに設置されている液晶パネルに先ほどの5分のカウントダウンタイマーが表示される。
あとは、お湯を投入したモッチッチを持って5席ある立食スペースのいずれかに移動すると、各スペースに設置されている液晶パネルに先ほどの5分のカウントダウンタイマーが表示される。 出来上がったらモッチッチを味わい、食べ終わったら返却口にカップを返すとともに、液晶パネルに表示される掃除ボタンをタップすることで、立ち食いスペース奥に設置されているiRobotの床拭き掃除ロボットのブラーバジェットm6が自動起動し、テーブルをまんべんなく拭いてくれる。
出来上がったらモッチッチを味わい、食べ終わったら返却口にカップを返すとともに、液晶パネルに表示される掃除ボタンをタップすることで、立ち食いスペース奥に設置されているiRobotの床拭き掃除ロボットのブラーバジェットm6が自動起動し、テーブルをまんべんなく拭いてくれる。 入店から退店までは以上のような流れになる。この店舗でAzureのSmart Storeがなにをやってるかというと、来店直後に客がモッチッチ貯蔵庫の前に立つと、設置されているカメラで性別や年齢を判別。
入店から退店までは以上のような流れになる。この店舗でAzureのSmart Storeがなにをやってるかというと、来店直後に客がモッチッチ貯蔵庫の前に立つと、設置されているカメラで性別や年齢を判別。 上部に設置されている超指向性スピーカーからモッチッチ貯蔵庫の前に立っている客だけに聞こえる音声で店内システムを解説してくれる。
上部に設置されている超指向性スピーカーからモッチッチ貯蔵庫の前に立っている客だけに聞こえる音声で店内システムを解説してくれる。 店内に入って天井をを見上げると、モッチッチ貯蔵庫以外にもさまざまな場所にカメラが取り付けられていることがわかる。これらは来店者の移動経路を追跡・分析しており、お湯を入れて客がどの立食テーブルに移動するかをSmart Storeが判別し、その客が選んだテーブルの液晶パネルにモッチッチにお湯を入れてからの正確な時間を表示する仕組みだ。前述のように320mlのお湯を入れた直後からカウントダウンは始まっているので、席に着いたタイミングで表示される残り時間は数秒経過した4分55秒や4分50秒などになっている。
店内に入って天井をを見上げると、モッチッチ貯蔵庫以外にもさまざまな場所にカメラが取り付けられていることがわかる。これらは来店者の移動経路を追跡・分析しており、お湯を入れて客がどの立食テーブルに移動するかをSmart Storeが判別し、その客が選んだテーブルの液晶パネルにモッチッチにお湯を入れてからの正確な時間を表示する仕組みだ。前述のように320mlのお湯を入れた直後からカウントダウンは始まっているので、席に着いたタイミングで表示される残り時間は数秒経過した4分55秒や4分50秒などになっている。 もちろんAzureのSmart Storeは、専用端末を使った決済処理も担っている。さらには冒頭で紹介した自動ドア制御による入店人数の制限もSmart Storeの役回りだ。
もちろんAzureのSmart Storeは、専用端末を使った決済処理も担っている。さらには冒頭で紹介した自動ドア制御による入店人数の制限もSmart Storeの役回りだ。 今回は試験店舗なので、モッチッチ貯蔵庫に異物が入ったり、モッチッチがスペースに正しく並べられていないと正確な計算処理ができない、自動ドア制御による入店制限を周知するために人員が必要など、完全な無人化とは言えない。しかし、飲食業界の人手不足を解消するソリューションとして進化する期待感は高い。
今回は試験店舗なので、モッチッチ貯蔵庫に異物が入ったり、モッチッチがスペースに正しく並べられていないと正確な計算処理ができない、自動ドア制御による入店制限を周知するために人員が必要など、完全な無人化とは言えない。しかし、飲食業界の人手不足を解消するソリューションとして進化する期待感は高い。

 2頭目以降は月額料金が半額。サブスクリプションサービスには、年2回の訪問健康診断がない月額1111円のベーシックプランもある。
2頭目以降は月額料金が半額。サブスクリプションサービスには、年2回の訪問健康診断がない月額1111円のベーシックプランもある。 toletta(トレッタ)は、猫がトイレに入ってから用を足して出るまでを動画で撮影しつつ、体重や尿量、尿回数、滞在時間などを自動的に記録できるIoT猫トイレ。動画で猫の様子を観察できるほか、体重減少はトイレの頻度などを参照できるので、飼い主が猫の状態変化を常に把握できる。同社ではこれまで約2000頭の猫の約100万件のデータを保有している。tolettaの本体価格は3万2780円でAmazonなどで入手可能。利用するには家庭内に2.4GHzのWi-Fi環境が必要だ。
toletta(トレッタ)は、猫がトイレに入ってから用を足して出るまでを動画で撮影しつつ、体重や尿量、尿回数、滞在時間などを自動的に記録できるIoT猫トイレ。動画で猫の様子を観察できるほか、体重減少はトイレの頻度などを参照できるので、飼い主が猫の状態変化を常に把握できる。同社ではこれまで約2000頭の猫の約100万件のデータを保有している。tolettaの本体価格は3万2780円でAmazonなどで入手可能。利用するには家庭内に2.4GHzのWi-Fi環境が必要だ。 「
「 「
「 上記2製品を含めて+Styleのオリジナル製品は、専用アプリ「+Style」でオン/オフなどの操作を一元管理できるのも特徴だ。具体的には、シーリングライトやLED電球、超音波加湿器、ロボット掃除機などを制御可能だ。さらに同社ではスマートリモコンも販売しているので、赤外線リモコンを使うエアコンやテレビ、レコーダーなどもコントロールできる。なお、ライトや掃除機、スマートリモコンなどは、GoogleアシスタントやAmazon Alexaを内蔵するスマートスピーカーからの音声操作にも対応している。
上記2製品を含めて+Styleのオリジナル製品は、専用アプリ「+Style」でオン/オフなどの操作を一元管理できるのも特徴だ。具体的には、シーリングライトやLED電球、超音波加湿器、ロボット掃除機などを制御可能だ。さらに同社ではスマートリモコンも販売しているので、赤外線リモコンを使うエアコンやテレビ、レコーダーなどもコントロールできる。なお、ライトや掃除機、スマートリモコンなどは、GoogleアシスタントやAmazon Alexaを内蔵するスマートスピーカーからの音声操作にも対応している。 また、トグル式の電源スイッチを採用するテレビなどの場合は、壁の電源コンセントとテレビの間に「
また、トグル式の電源スイッチを採用するテレビなどの場合は、壁の電源コンセントとテレビの間に「 そのほか同社では、人感センサーやドアや窓の開閉センサー、漏水センサーなどラインアップしており、人が通過した、ドアが空いた、水が漏れたなどの状況変化を感知して、各種家電のオン/オフや設定変更が可能だ。セキュリティー関連では、屋外用の「スマートセキュリティカメラ」や「スマートビデオドアフォン」、屋内用の「スマートホームカメラ」などもある。
そのほか同社では、人感センサーやドアや窓の開閉センサー、漏水センサーなどラインアップしており、人が通過した、ドアが空いた、水が漏れたなどの状況変化を感知して、各種家電のオン/オフや設定変更が可能だ。セキュリティー関連では、屋外用の「スマートセキュリティカメラ」や「スマートビデオドアフォン」、屋内用の「スマートホームカメラ」などもある。 発表会では「+Style」アプリの新機能についても明らかにされた。現在はβ版だが、GPSによる家電制御機能が加わっている。具体的には、スマートフォンが内蔵するGPSなどの現在位置捕捉機能と連動して、自宅から100m程度離れると自宅内の家電をすべてオフ、逆に100m以内に近づくとすべてオンにするといった制御が可能になる。ほかのスマートリモコンではすでにおなじみの機能だ。2月末には正式版として搭載予定とのこと。
発表会では「+Style」アプリの新機能についても明らかにされた。現在はβ版だが、GPSによる家電制御機能が加わっている。具体的には、スマートフォンが内蔵するGPSなどの現在位置捕捉機能と連動して、自宅から100m程度離れると自宅内の家電をすべてオフ、逆に100m以内に近づくとすべてオンにするといった制御が可能になる。ほかのスマートリモコンではすでにおなじみの機能だ。2月末には正式版として搭載予定とのこと。
 なお同社では、新製品の発売を記念して、最大4000円の値引きとなるキャンペーンを2月20日まで実施する。
なお同社では、新製品の発売を記念して、最大4000円の値引きとなるキャンペーンを2月20日まで実施する。
 近藤氏は「今後は+Styleオリジナル製品だけでなく、+Styleで取り扱っているすべてのIoT機器を1つのアプリで制御できるようにしたい」とコメントし、将来的には他社製品との連携も視野に入れていることを明らかにした。
近藤氏は「今後は+Styleオリジナル製品だけでなく、+Styleで取り扱っているすべてのIoT機器を1つのアプリで制御できるようにしたい」とコメントし、将来的には他社製品との連携も視野に入れていることを明らかにした。


 そのほかの機能としては、アップルのHome Padのように2台設置することでステレオサウンドを構築できる。複数のスピーカーをグループ化して同じ曲を流したり、別々の曲を流したりすることも可能だ。音量などの各種操作は専用のスマートフォンアプリを利用できる。対応する音楽ストリーミングサービスは、Amazon Music、Spotify、Apple Music、Google Musicをはじめ50種類以上。ただし、dヒッツやLINE MUSIC、うたパスなどローカルなストリーミングサービスには対応していない。これらのサービスを使っている場合は、AirPlay 2経由でiPhoneなどからSYMFONISKに音楽を飛ばす必要がある。
そのほかの機能としては、アップルのHome Padのように2台設置することでステレオサウンドを構築できる。複数のスピーカーをグループ化して同じ曲を流したり、別々の曲を流したりすることも可能だ。音量などの各種操作は専用のスマートフォンアプリを利用できる。対応する音楽ストリーミングサービスは、Amazon Music、Spotify、Apple Music、Google Musicをはじめ50種類以上。ただし、dヒッツやLINE MUSIC、うたパスなどローカルなストリーミングサービスには対応していない。これらのサービスを使っている場合は、AirPlay 2経由でiPhoneなどからSYMFONISKに音楽を飛ばす必要がある。





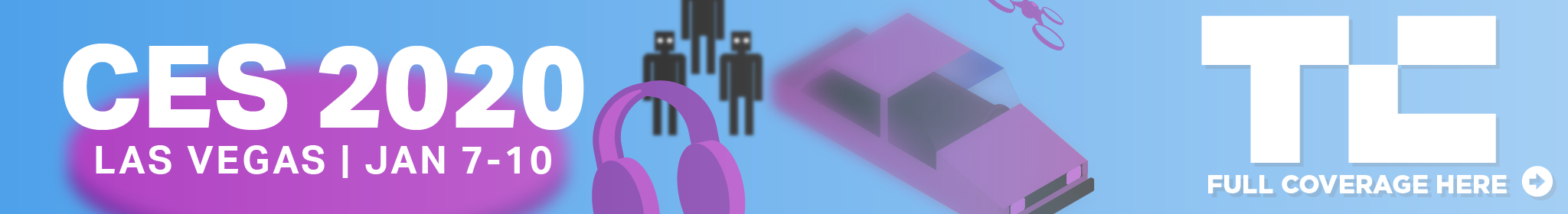

 まごチャンネル with SECOMは、セコムの環境センサー「みまもりアンテナ」をまごチャンネルに搭載したデバイス。昨年12月10日から先行体験キャンペーンを実施していたもので、今回正式に販売開始となる。
まごチャンネル with SECOMは、セコムの環境センサー「みまもりアンテナ」をまごチャンネルに搭載したデバイス。昨年12月10日から先行体験キャンペーンを実施していたもので、今回正式に販売開始となる。



 マネックスベンチャーズなどを引き受け先とする第三者割当増資で累計調達額は4億円となる。主な引き受け先は以下のとおり。
マネックスベンチャーズなどを引き受け先とする第三者割当増資で累計調達額は4億円となる。主な引き受け先は以下のとおり。
 今後開発を強化する猫の健康状態を自動判定するアルゴリズムについて同社は、正社員として勤務している獣医師の知見と、toletta2で記録できる、猫のトイレ動画や尿量、体重などデータを分析して異変を知らせるアルゴリズムを開発するとのこと。膀胱炎など猫が罹患しやすい泌尿器科系の疾患の早期発見に役立てたいとしている。同機能は2020年2月末のリリースを予定している。
今後開発を強化する猫の健康状態を自動判定するアルゴリズムについて同社は、正社員として勤務している獣医師の知見と、toletta2で記録できる、猫のトイレ動画や尿量、体重などデータを分析して異変を知らせるアルゴリズムを開発するとのこと。膀胱炎など猫が罹患しやすい泌尿器科系の疾患の早期発見に役立てたいとしている。同機能は2020年2月末のリリースを予定している。 獣医師連携システムについては、現在一部のユーザーがテスト中の獣医師とのLINE相談サービスを拡充・強化する計画だ。現在、toletta2で取得したデータを基に、猫を見守るためのコンサルティング業務を進めており、前述の健康状態の自動判定機能と併せて、猫の健康状態を飼い主と獣医師でしっかり見守る体制を整える。
獣医師連携システムについては、現在一部のユーザーがテスト中の獣医師とのLINE相談サービスを拡充・強化する計画だ。現在、toletta2で取得したデータを基に、猫を見守るためのコンサルティング業務を進めており、前述の健康状態の自動判定機能と併せて、猫の健康状態を飼い主と獣医師でしっかり見守る体制を整える。
