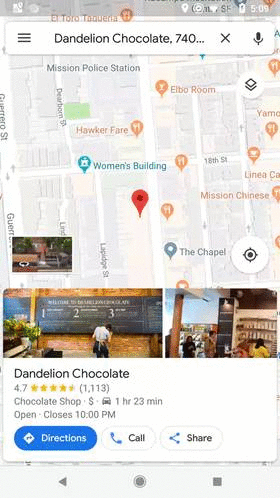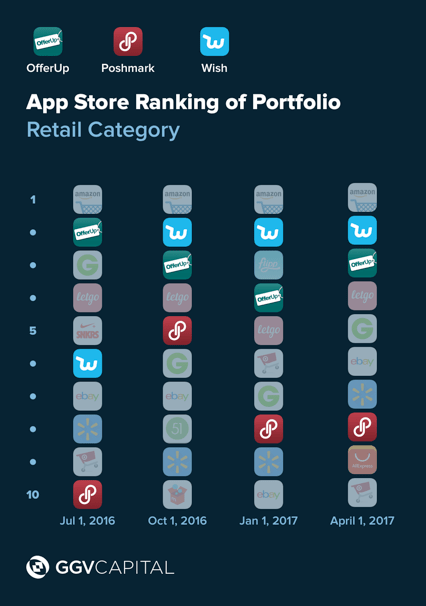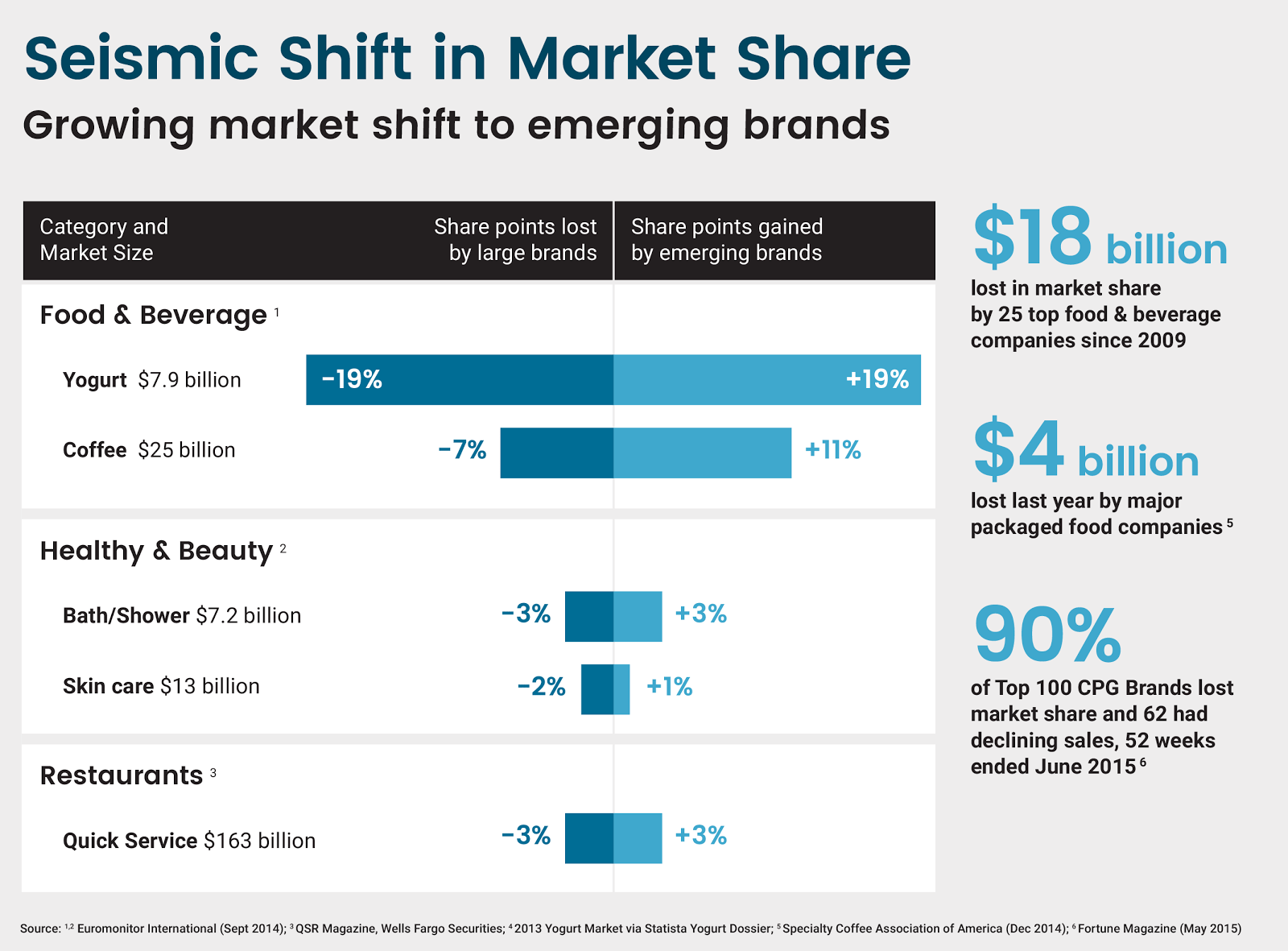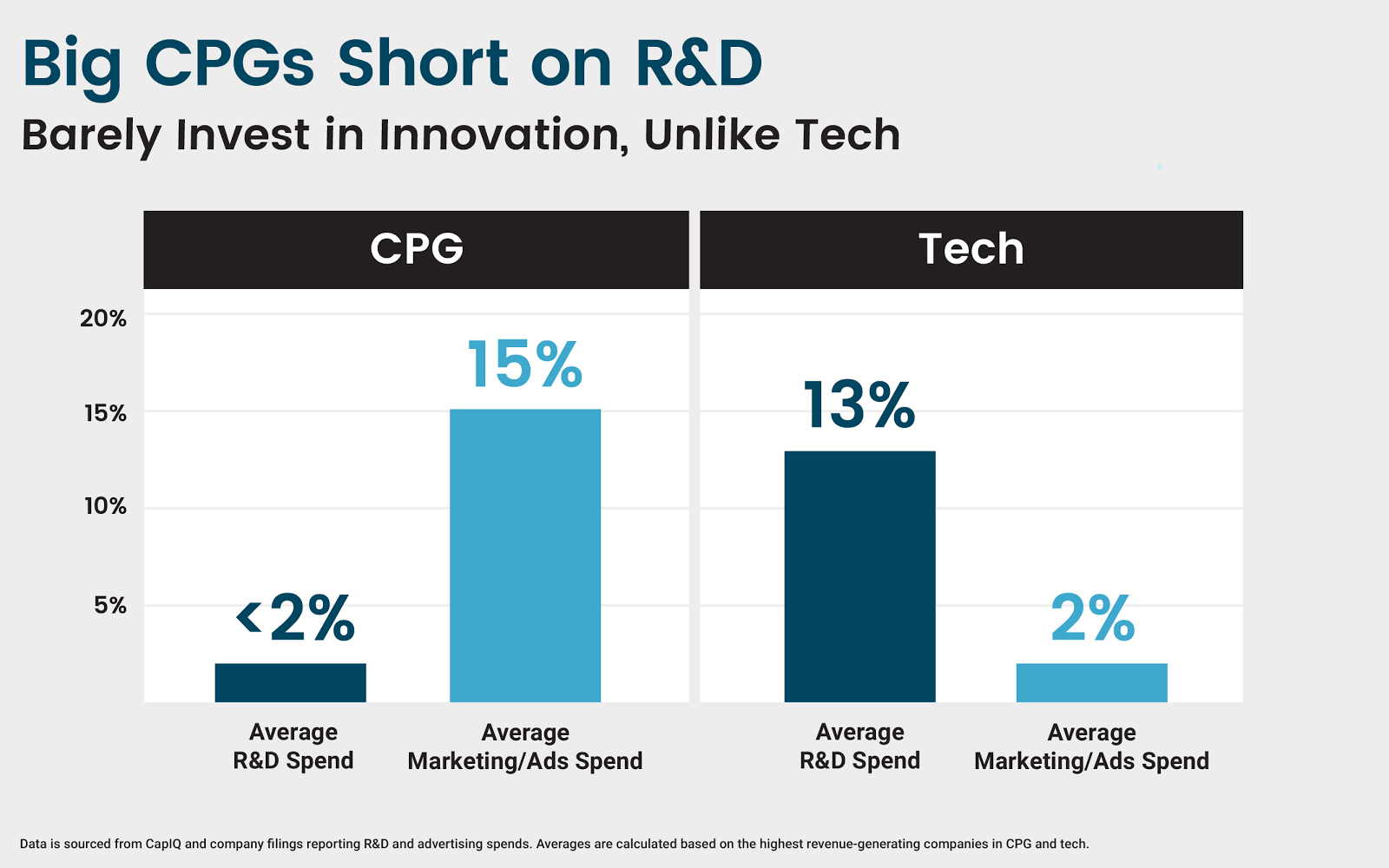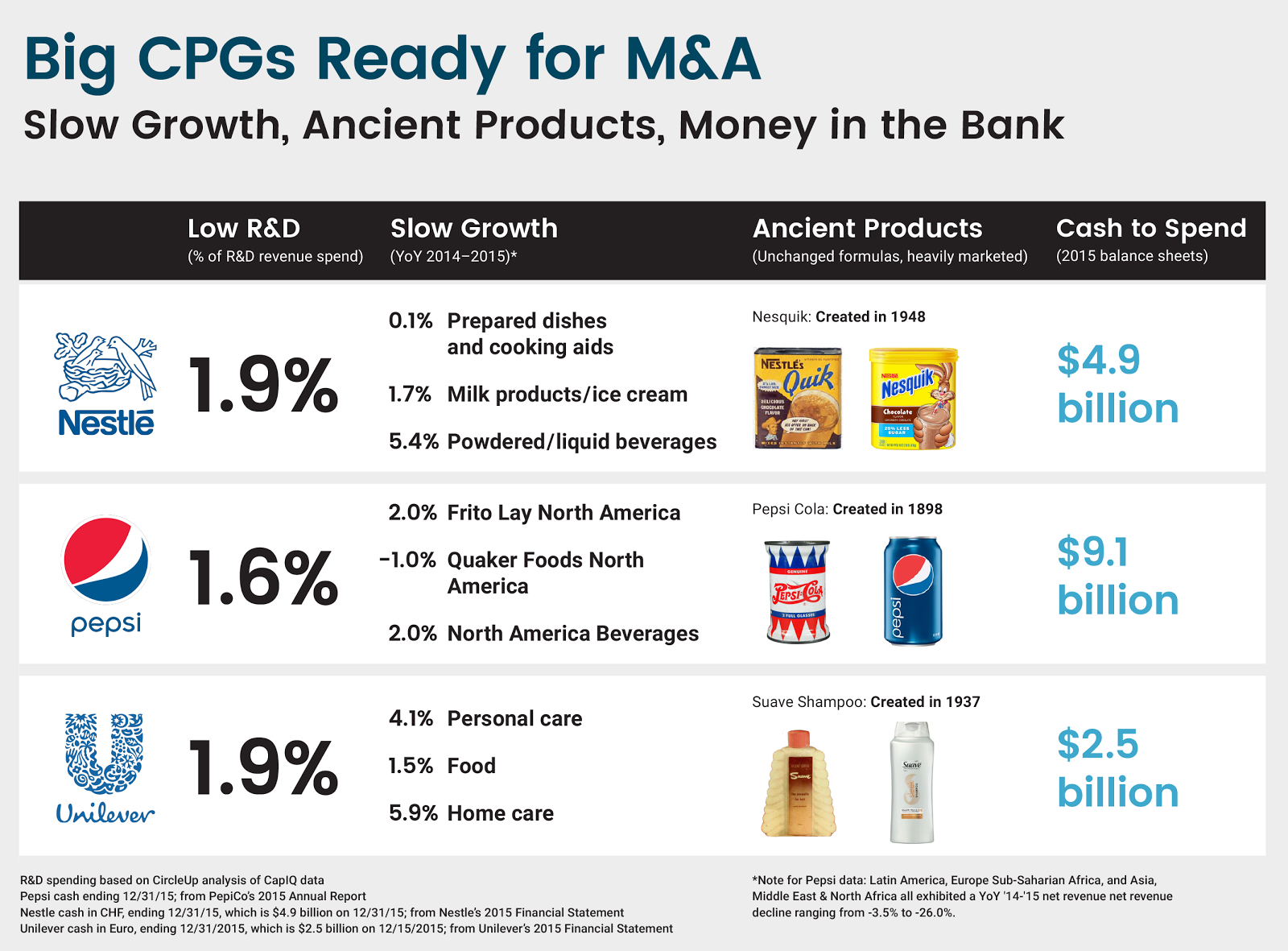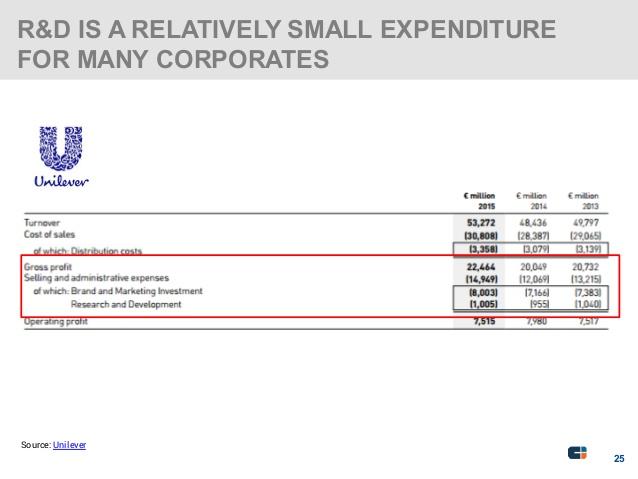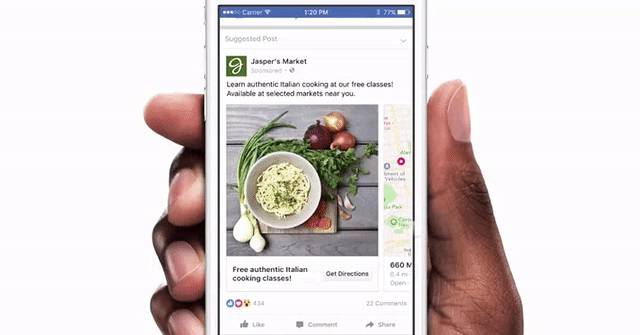店舗がもっと自由に商品を仕入れられるプロダクトを作ることからスタートし、ゆくゆくは小売全体をアップデートしたい——。今回紹介するのはそんな目標の下、テクノロジーを活用して小売業界の課題解決に取り組むスタートアップ「パークアンドポート」だ。
同社は10月8日、店舗向け仕入れプラットフォーム「PORTUS(ポルタス)」をローンチした。
PORTUSは「店舗が抱える『仕入れの壁』を取っ払い、幅広い商品を仕入れられるようにする」ことを目指したサービス。商品を扱うメーカーやブランドといったサプライヤーと店舗を適切につなぐことで、受発注の工数や与信を始めたとした既存の商流における課題を解決する。
メーカーと店舗が抱える受発注の課題をITで解決
これまで店舗が商品を仕入れようと考えた場合、電話やFAXでメーカーにアポイントをとった後、店舗の規模や与信などの基準をクリアして初めて取引が始まるという流れが一般的だった。その工程は時間と手間がかかるだけでなく、結果的にメーカー側の判断でNGになることも多々ある。
反対にサプライヤー側はどうか。こちらも取引方法がアナログな形式のため、1人の営業担当者が対応できる件数が限られ、なかなか取引の幅を広げられないという課題を抱えている。そこに上述した与信の問題も加わり、第三者機関の与信点数が低ければ面白そうな店舗であっても商品を提供できないことがあるそうだ。
パークアンドポート代表取締役の櫟山敦彦氏は新卒で入社した繊維商社時代にブランドビジネスに携わっていたこともあり、特に店舗側の課題を自身でも感じていたそう。ただヒアリングを重ねていくとサプラヤー側も大きな悩みを持っていることに気づいた。
「決して売りたくないわけではないのに、売れない状況に陥っている。与信がないとそもそも商品を提供できず、その解決策として先払いという手段もあるがお店側に負担がかかり導入しにくい。また『最低でも一定の数量以上は仕入れてください』という形で、店舗側がリスクを取る必要があることも多く、新しいブランドや商品に手を出しにくいとう課題もある。サプライヤーとしては営業効率なども考えると、小規模の店舗にごくわずかな商品を提供するメリットが少ないからだ」(櫟山氏)
両者を仲介する存在として問屋やBtoB仕入れサービスが存在するが、問屋の場合は結局与信の問題が付きまとう。また櫟山氏の話では既存の仕入れサービスはマッチングのみを担うプラットフォーム型が多く、結局担当者が自分で相手を見つけて交渉する必要があることも多いという。
そこでPORTUSの登場だ。このサービスは独自のバイイングサポートシステムとトライアルオーダー機能を軸に「サプライヤーの営業業務と与信の部分を巻き取って、自分たちが代行する」(櫟山氏)ことで、サプライヤーの営業クオリティを落とさずに今まで以上に多くの店舗へと商品を提供できるようにする。
バイイングサポートシステムは、簡単に言うと店舗の特性に合った商品をPORTUSがレコメンドする仕組みだ。店舗登録時に入力した店舗画像、取扱ブランド、商材の売上構成比などから店舗の特徴量を抽出し、特性にあった商品やブランドを提案するというもの。これをオンライン上で行うことで、従来の電話・FAXによる受発注業務や配送確認作業を効率化する。
櫟山氏の話では当初はサクセスチームによる人力のコミュニケーションを通じた提案がメインになるが、取引回数が増えていけば徐々にデータに基づいて機械的にレコメンドすることにも取り組むそう。
「同じような商品を扱っている店舗では、Aという商品がよく売れている」「その商品と一緒にBという商品が購入されている」といったようなデータから、各店舗に対して商品・ブランドを紹介するイメージだ(店舗は登録されているブランドから自身で商品を選ぶことも可能)。
さらにもう1つのトライアルオーダー機能で店舗側の仕入れのリスクを削減する。同機能はその名の通り、ブランドから商品を仕入れる前に「一定期間店頭に商品を置いて、顧客の反応を確かめた上で実際の発注を行える仕組み」だ。
従来の「買取中心の商流」では店舗側がリスクをとって一定の数量以上を買い取る必要があったことに加えて、既存のBtoB仕入れサービスでは事前に商品をチェックできないことが多く、アパレル商材のようにオンライン上のみで判断が難しい商品は発注しづらかった。
要は「売れるかわからない商品」をいきなり仕入れるのではなく、試験的に店頭に置いて顧客のフィードバックを得られるようにすることで、より多くの商品にチャレンジしやすくなる。Webサービスを作っている会社がα版やテスト版を作って周囲の人に試してもらう感覚に近いかもしれない。
「(バイイングサポートで)この商品どうですか?と提案しても、見たことがない商品をいきなり仕入れるのは少しハードルが高い。トライアルで実際に顧客の反応を確かめた上であれば仕入れやすいと考えた」(パークアンドポート共同創業者でCOOの近藤俊氏)
これらのシステムによって店舗とサプライヤー双方の負担を減らしつつ、実際に正式な発注に至った際にはサプライヤー側から10〜15%ほどの手数料を得るのがPORTUSのビジネスモデルだ。
目標は小売のアップデート、事業拡大へ資金調達も実施
PORTUSでは9月からユーザーの事前登録を始めていて、現在30以上のブランドと複数の小売店(数は非公開)がすでに集まっている。ブランド側はライフスタイル全般に及び、中には造花店や額縁店などからの問い合わせもあるそう。またCAMPFIREで累計数千万円の支援を獲得している「ALL YOURS」のような新興ブランドがリアルな商圏を広げていく目的で参画しているケースもある。
櫟山氏によると、ある店舗では実験的に「店舗スタッフが選んだ商品」と「PORTUSメンバーが選んだ商品」を置いてみたところ後者の方が売れたそう。そこからスタッフが顧客にどんなものが欲しいかを自ら聞き、PDCAを回していくような流れに繋がりつつあるようだ。
「今までは仕入れ先が限られていたので、顧客のニーズを聞いても仕入れに反映できないこともあった。PORTUSを通じてリアルな小売においてもどんどんPDCAを回せるような環境が作れれば、バイイングサポートの精度も上がってより面白い商品を提案することにも繋がるし、顧客のニーズに応えることもできる」(櫟山氏)
もともとパークアンドポートは「リアルな店舗における購買体験をもっと楽しくするにはどうしたらいいか」という思いから始まったスタートアップ。「店舗側が自由に仕入れができないこと」が原因で商品のバラエティが限定されたり、画一的な店舗が増えてしまうのではと考え、現在手がけるプロダクトからスタートすることを決めたという。
学生時代からかなりのファッション好き、ショッピング好きだったという代表の櫟山氏は新卒でブランドビジネスに携わっていたほか、前職のエアークローゼットでは対アパレルとの交渉やMDの統括、改善、複数の新規事業の立ち上げなどを担当していた人物。COOの近藤氏も楽天時代にEC事業に携わるなど、ITと小売の経験があるメンバーが中心だ。
パークアンドポートでは今回プレシードラウンドとして、インキュベイトファンド及び他1社のベンチャーキャピタルを引受先とした第三者割当増資を実施したことも明かしている。
今回のラウンドでは金融機関からの融資も含めて総額3000万円を調達する予定。冒頭でも触れた通り「小売のアップデート」を目標に、各機能の強化やサービス認知獲得から事業拡大を目指す。