
これまで、次世代のコンピューティングプラットフォームとしてのAR(拡張現実)について多くの話題が出されてきたが、Apple(アップル)は、これまで予想されていたものよりもさらに強く、仮想現実に興味を持っているのかもしれない。
9to5macによる4月のレポートに続き、米国時間5月14日に同社は、Bloomberg(ブルームバーグ)の取材に対して、VR配信のスタートアップであるNextVRの買収を認めた。現在NextVRのウェブサイト上では、同社が「新しい方向に進んでいる」との知らせが強調されている。
表面的には、この買収はアップルにとって少し奇妙なものに思える。同社はこれまで、モバイルARに全力を注いでいた。そしてVRの世界に対する公の活動や関心の表明を控えており、その領域を完全にFacebookの手に委ねてきた。昨年末にThe Informationは、アップルが従業員に対して、2022年にARとVR機能を組み合わせたデバイスを、Oculus Questと同様のフォームファクターで出荷する可能性があると伝えたことを報告した。この件と今回の買収を合わせて考えると、同社がこれまで示してきたものよりもVRについてより深い計画を持っている可能性があることが伺える。

数年に渡るiOSでの提供を通して、優れたARがどのように見えるものかについて、アップルが素晴らしい結果を残せたのかどうかはあまりはっきりしていない。そのため、数年以内にMR(混合現実)ヘッドセットを発売し、ユーザーが満足するVRコンテンツの裾野を広げながら、ARコンテンツに対する開発者のイノベーションを推し進めていくことは、第1世代のARデバイスとしては現実的な意味を持っている。
9to5macはNextVRの買収額を約1億ドル(約107億円)と特定していた、この金額はこれまで合計で1億1500万ドル(約123億円)を投入してきた投資家にとっては、まったく満足できるものではないが、現在のVRコンテンツ市場の様子から考えると驚くほど真っ当なイグジットだと言えるだろう。ただし、この取引をもって終了と考えているなら、アップルにとっては具体的な計画を持たずに、ただ大枚をはたいただけいうことになる。
NextVRの最大の強みの1つは、長年にわたってスポーツリーグとの間に築いてきたパートナーシップだ。アップルは、そのパートナーシップに最適化されたデバイスを売り出すまでは、そのパートナーシップを積極的に保つことにはあまり関心を向けないだろうと私は推測しているが、VRコンテンツを配信するためのNextVRの技術は、将来のアップルコンテンツ操作像を描き出す可能性がある。

アップルは、Apple TV+のような取り組みを中心にコンテンツ分野で組織的な影響力を発揮してきたが、この先彼らがリリースを考えている新しいデバイス向けに、コンテンツネットワークを広げていく際に好スタートを切るには、今回のような買収を活用したいと考えることはあり得る話だ。
こうしたことに関わる主要な問題は、VRに最適化されたコンテンツはARにうまく変換されないということだ。NextVRのソリューションは、既存のVRヘッドセットの全視野を活用してユーザーを完全な3D環境の中に没入させる。ARヘッドセットのユーザーが最終的に同じ方法でこのコンテンツを体験できなないという技術的な理由はないが、このタイプのコンテンツを活用できる性能を備えるARヘッドセットは存在せず、ここでの進歩はかなり遅いものだった。既存のARデバイスはおそらくVR用には最適化されていないし、またその逆も真である。しかしアップルはすでに、それは長期的には解消されるという前提で組織を動かしていると思われる。
FacebookはOculusハードウェアを活用するために、意味のあるVRコンテンツネットワークを構築しようと何年にも渡って苦労している。ユーザーにとって十分なコンテンツが存在せず、そして一方コンテンツ開発者を引きつけるには十分なユーザーがいないという「鶏と卵問題」を解決しようとする試みは、Facebookに対して、VR開発に対する一方的な出資を何年も強いることになった。アップルにも、ARで似たような運命が待ち受けているかもしれない。
Magic Leapが徐々に影をひそめる中で、アップルは最終的にARデバイスを発表した際に、非商業的な開発が散発的に行われるだけの死んだセクターに到着してしまったことに気がつくことになるのかもしれない。同社は長い間、新しいプラットフォームに対して早い段階での関心を集めるために、開発者との関係に頼ってきたが、これまでのところARKitに対する消費者の関心の構築には大枠では失敗している。このため多くの開発者が野心的なARに対して様子見アプローチを取るだろうと予想するのは当然だ。このことはアップルにとって、ARローンチコンテンツの確保に重い負担を残すことになるだろう。

これまでのところ、ARKitに対するアップルの最大の失敗は、モバイルデバイス上でのARプラットフォームの可能性をわかりやすく提示できていないことだ。AR開発プラットフォームを何度か改訂するうちに、同社は代表的な使用例を紹介することに対して、これまで以上に保守的になってきた。最も注目を集めているのは、ダウンロード可能な3D測定アプリだ。その一方で、空間プラットフォームを独自に活用するヒット作品はほとんど生まれなかった。
というわけで、VRはアップルにとってしばらくの間は投資するためのより安全な場所なのかもしれない。優れたバーチャルリアリティコンテンツは一般に作りやすい。現実世界とのやり取りに依存することが少なく、開発者はエクスペリエンスをエンドツーエンドでより多く制御できるからだ。
NextVRの技術を活用することで、アップルはより幅広いVRコンテンツに向かうスムーズなパイプラインにアクセスすることが可能になる。そうしたコンテンツは登場が予定される「MR」デバイスや、将来的にはより技術的に進歩したARメガネで楽しむことができるだろう。
アップルのCEOであるTim Cook(ティム・クック)氏をはじめとする多くの同社のリーダーがARの可能性に興奮していることを率直に公言してきたが、開発者がその可能性を見出すのに苦労し続けている中で、VRの魅力が長期的な戦略にとってより重要になってきているのかもしれない。
[原文へ]
(翻訳:sako)









 いちからは、国内最大級のバーチャルアーティストグループ「
いちからは、国内最大級のバーチャルアーティストグループ「
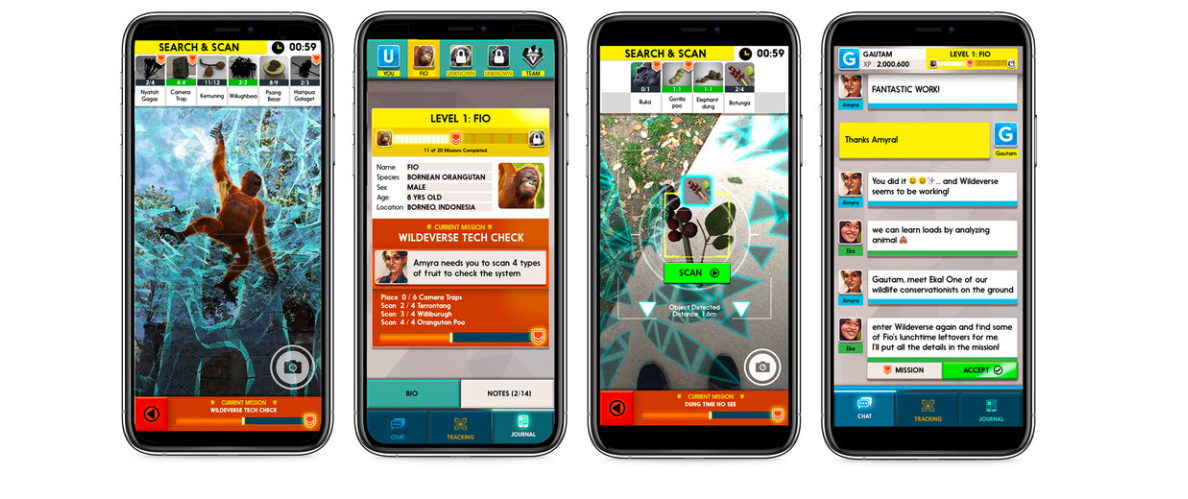



 xR関連のイベントの企画・運営などを手掛ける
xR関連のイベントの企画・運営などを手掛ける 具体的には、東急レクリエーションが首都圏を中心に全国19カ所で展開しているシネマコンプレックスチェーン「
具体的には、東急レクリエーションが首都圏を中心に全国19カ所で展開しているシネマコンプレックスチェーン「


 スタートアップは上場する時に、バリュエーションを「細切れ」にされる。そして経済全体が新型コロナウイルスっで弱っている。ARは公共の場を避ける人々にとってVRよりもそう面白くは映っていないようだ。中古のARヘッドセットをデモで人々の顔に装着してもらうのは、未来が見通せない中で難しいことだろう。
スタートアップは上場する時に、バリュエーションを「細切れ」にされる。そして経済全体が新型コロナウイルスっで弱っている。ARは公共の場を避ける人々にとってVRよりもそう面白くは映っていないようだ。中古のARヘッドセットをデモで人々の顔に装着してもらうのは、未来が見通せない中で難しいことだろう。
 ARアイウェアは未来の一部なのだろうか? おそらくそうだろう。そしてMagic Leapは価値があるのか? おそらく、幾分そうだろう。効率に執着するマーケットに何億ドルもの金をつぎ込むというのは同社にとって早すぎた。そして額としては少なすぎた。100億ドルという売却価格をつけるには、遠い将来の成功につながる、他社が真似できないような才能とテクノロジーをMagic Leapが持っていると、世界でも有数の大企業に確信させる必要がある。
ARアイウェアは未来の一部なのだろうか? おそらくそうだろう。そしてMagic Leapは価値があるのか? おそらく、幾分そうだろう。効率に執着するマーケットに何億ドルもの金をつぎ込むというのは同社にとって早すぎた。そして額としては少なすぎた。100億ドルという売却価格をつけるには、遠い将来の成功につながる、他社が真似できないような才能とテクノロジーをMagic Leapが持っていると、世界でも有数の大企業に確信させる必要がある。





 謎解きキットは、
謎解きキットは、 ポップアップストアは、2月16日まではラゾーナ川崎プラザの2FのPLAZA East、2月17日〜3月1日までは同じくラゾーナ川崎プラザの5Fにある109シネマズ川崎に設置される。謎解きに登場するのは、バルスに所属するバーチャルアーティストである、風宮 祭、夜子・バーバンク、銀河アリス、MonsterZ MATEのコーサカとアンジョーの4組。
ポップアップストアは、2月16日まではラゾーナ川崎プラザの2FのPLAZA East、2月17日〜3月1日までは同じくラゾーナ川崎プラザの5Fにある109シネマズ川崎に設置される。謎解きに登場するのは、バルスに所属するバーチャルアーティストである、風宮 祭、夜子・バーバンク、銀河アリス、MonsterZ MATEのコーサカとアンジョーの4組。 キットには、暗号(ナゾ)を解くためのキーワードを書き込む用紙などが入っており、暗号がわかったらバルスが無償配布している「SPWN AR」アプリにそのキーワードを入力すると、次の暗号の手がかりとなる動画を見られる。キーワードがわからない場合に備えて、ヒント動画も用意されている。
キットには、暗号(ナゾ)を解くためのキーワードを書き込む用紙などが入っており、暗号がわかったらバルスが無償配布している「SPWN AR」アプリにそのキーワードを入力すると、次の暗号の手がかりとなる動画を見られる。キーワードがわからない場合に備えて、ヒント動画も用意されている。 暗号を解く手がかりは、ラゾーナ川崎プラザ内のほか、VTuberの知識を動画で理解、SPWN AR内の動画を見るといった3つ方法がある。暗号は全部で5つあり、すべてを解き明かすっとエンディングのキーワードをわかるようになっている。なお、クリア画面をポップアップストアのスタッフに見せると、クリア特典として特別なARマーカーがもらえるほか、特典動画を見られるようになる。
暗号を解く手がかりは、ラゾーナ川崎プラザ内のほか、VTuberの知識を動画で理解、SPWN AR内の動画を見るといった3つ方法がある。暗号は全部で5つあり、すべてを解き明かすっとエンディングのキーワードをわかるようになっている。なお、クリア画面をポップアップストアのスタッフに見せると、クリア特典として特別なARマーカーがもらえるほか、特典動画を見られるようになる。
