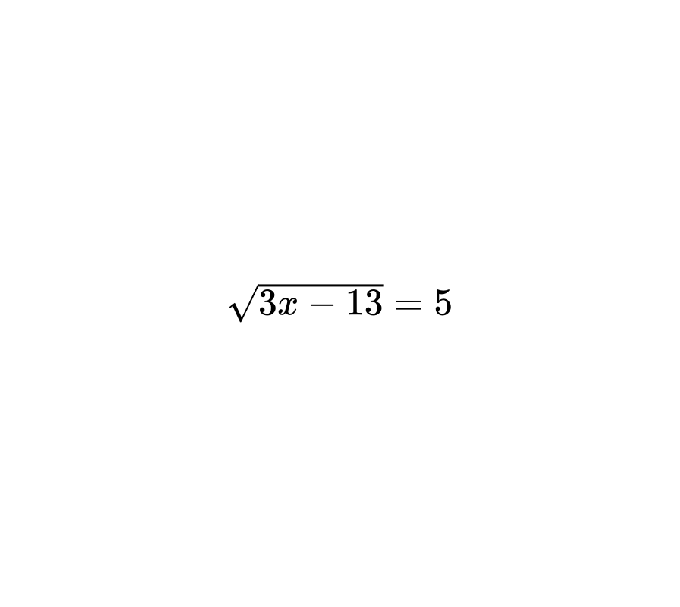写真左からグロービス・キャピタル・パートナーズ 福島智史氏(シリーズBラウンドリード投資家)、AIメディカルサービス 代表取締役CEO多田智裕氏、代表取締役COO山内善行氏、インキュベイトファンド 村田祐介氏(シリーズAラウンドリード投資家)
近年日本でも医師が立ち上げたヘルステックスタートアップや弁護士が創業したリーガルテックスタートアップを始め、さまざまな業界の専門家がテクノロジーを活用して「現場に新しい風を吹き込む」ような事例が増えているように思う。
今回紹介するAIメディカルサービス (以下AIM)もまさにその1社。約20年にわたり内視鏡医を務めてきた多田智裕医師が、“現場の困りごと”をAI技術を用いて解決しようと創業したスタートアップだ。
そのAIMは10月4日、グロービス・キャピタル・パートナーズなど複数の投資家を引受先とした第三者割当増資により約46億円を調達したことを明らかにした。今回は同社にとってシリーズBラウンドの調達。投資家陣は以下の通りだ。
Globis Fund VI, L.P.およびグロービス6号ファンド投資事業有限責任組合(グロービス・キャピタル・パートナーズ)
WiL Fund II, L.P.(WiL)
未来創生2号投資事業有限責任組合(スパークス・グループ)
Sony Innovation Fund by IGV(ソニーと大和キャピタルホールディングスが創設したInnovation Growth Ventures)
日本ライフライン
日本郵政キャピタル
Aflac Ventures
菱洋エレクトロ
次世代企業成長支援2号投資事業有限責任組合(SMBCベンチャーキャピタル)
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合(大和企業投資)
その他個人投資家1名
現在AIMが研究開発を進めているのは胃や食道、大腸、小腸といった消化器に対する内視鏡検査を支援するAIプロダクトだ。「AIを用いた医療画像診断」と言うとピンとくる人も多いかもしれないけれど、内視鏡で撮影した静止画や動画から病変の検出や状態の判別、範囲表示までを一貫してサポートする。
これまでは学習データの整備や研究開発を中心に取り組んできた同社だが、今回の調達を機に日本発のリアルタイム内視鏡AIの製品化を見据えて、薬事承認に向けた準備なども加速させていく計画だ。
多い時には「1時間で3000枚もの画像」をチェック
「1番の課題は現場の仕事量が医師の処理能力を大幅に超えているということ。アナログからデジタルフィルムの時代へと進化した結果、内視鏡で撮影される画像の量が爆発的に増え、目視でチェックすることに限界を感じていた」
多田氏は内視鏡医の現状についてそう話す。東京大学医学部付属病院や虎ノ門病院など複数の病院を経て、2006年にただともひろ胃腸科肛門科を開業。自身が院長を務めるこのクリニックでは年間約9000件の内視鏡検査を行う。
多田氏が所属する医師会では月に数回専門医によるダブルチェックを実施するそうなのだけど、多い時には1人の医師が1時間で3000枚もの内視鏡画像をチェックしなければならない。
アナログフィルムだった時代に比べると画像の量は約3倍。専門医の数はほぼ横ばいのため、1人当たりの負担がそのまま3倍に膨らんだようなものだ。しかも日中は通常通り診療を行なっているから、チェックをするのはもっぱら業務終了後の夜。多田氏自身、数年前からこの働き方は厳しいと限界を感じていたという。
とは言えこの仕事はその道のプロである専門医以外が担うことはできない。これまでは特に革新的な解決策も生まれてこなかったので、現場で医師がひたすら頑張るしかなかった。
そんな時に多田氏が“たまたま”出会ったのがAIテクノロジーだ。2016年にAIの研究者として有名な東京大学の松尾豊氏の講演会で、AIによる画像認識能力の進歩と現状を知り「画像診断が得意なAIなら自分たちの課題を解決できる」と感じた。
そこで松尾氏に内視鏡にもAIの力を使えるか尋ねたところ「CTやMRIの領域ではそのような研究事例があるが、内視鏡に関しては国内外でやっている人を知らない」という旨の答えが返ってきたという。
「誰もやっていないなら自分でやってみよう」。そう考えた多田氏は後輩から紹介してもらったAIエンジニア、繋がりのある医師や地元のクリニックなどと一緒に内視鏡AIのPoC(概念実証)に自ら取りかかる。
最初に研究開発を進めていたのは、内視鏡で撮影した画像から胃がんの原因である「ピロリ菌」の有無を区別するAI。約4〜5ヶ月にわたる研究の末に開発した製品の実力は、医師の平均値を上回った。正答率は約9割、人間の医師も含めたテストでは23人中4位の結果だったという。
そうは言ってもピロリ菌の診断だけでは十分ではない。PoCを通じて手応えを掴んだ多田氏が次に取り組んだのは胃がんを診断するAIの開発だ。
当時はまだ個人で取り組むプロジェクトでしかなかったが、より本格的に研究開発を進めるべく2017年9月にAIMを創業。そこから正式に会社としての挑戦がスタートした。
研究では6mm以上の胃がん検出感度約98%を実現
AIMが開発する内視鏡AIでは撮影された画像において「何が」「どこに」あるのかを識別したり、「その画像が何なのか」のカテゴリ分けを行う。たとえば同社は「早期の胃がん」に対応したAIを最初の製品にしようと考えているが、このAIでは胃の写真からどこに病変があるかをあっという間に検出する。
2018年1月には研究結果として静止画から6mm以上の胃がんを98%の精度で
発見(検出感度約98%)できたことを発表。ちなみに画像1枚あたり0.02秒で診断するというスピード感だ。
現在は静止画に加えて動画からリアルタイムで胃がんを検出するAIの開発にも着手。こちらは静止画に比べて難易度が上がるため少し精度は落ちるものの、それでも検出感度は約92%ほどを誇る。
研究としてはすでに食道がんや大腸がんにも取り組んでいるが、製品化の第一弾は胃がんの計画。なぜ胃がんが最初なのか、多田氏にその理由を聞いてみたところ「専門医でも見分けるのが難しい場合も多く、現場のニーズが最も大きいから」だという。
実際に「胃がんは1割程度が見逃されている」と推定されているそう。仮に内視鏡AIを使うことで早い段階から胃がんの可能性に気づけるようになれば、医療の質も上がりインパクトは大きい。もちろん技術的なハードルは上がるが、現場を経験しているからこそ、胃がんから始めることにはこだわった。
「イメージとしては優秀なアシスタントがついてくれるようなもの。今までは見逃してしまっていたような病変に気づけるようになれば、より良い医療が実現できる。患者さんは今よりも高精度の検査が受けられるようになり、医師側の検査の負荷も減らせる」(多田氏)
VIDEO
今は消化器内視鏡分野で日本を代表する医療機関約80施設と共同で研究開発を進めている。当初こそプロダクトの構想を知った人から「医者がいらなくなるのでは?」という声も多かったそうだが、時間が経つに連れて便利だねという声が増えた。
「あくまでAIは診断の補助となる確率を示すだけであり、確定診断を下すわけではない。そういう意味で医師とAIは対立するのではなく、医師プラスAIという構造で良い医療を実現するために協力する関係になる」(多田氏)
内視鏡AIなら世界で戦えるチャンスがある
多田氏が内視鏡AIに可能性を感じてから約3年。現在までの間にこの領域で徐々に新たなプロジェクトも立ち上がり始めている。
日本国内でもNECが国立がん研究センターとともに、AIを活用したリアルタイム内視鏡診断サポートシステムの実用化に向けた取り組みを発表 。オリンパスは今年3月にAIを搭載した内視鏡画像診断支援ソフトウェアを発売した。ちなみに同社は2018年10月にエルピクセルへ出資 もしている。
一口に内視鏡AIと言っても対応している症例やフォーマットが異なるので単純には比べられないが、この領域でもAIの活用が進み始めているのは間違いないだろう(今の所は「大腸ポリープ」「静止画」に関する取り組みが多い一方で、AIMでは「早期の胃がん」を最初のターゲットとし、「動画」対応も進めているという)。
画像診断AI系のプロダクトにおいて、1つのポイントになるのが学習させる教師データの質と量だ。内視鏡AIの判断精度を高めていく上では、簡単には見分けがつかないような画像に対しても正しい情報を与えることのできる専門医の協力が不可欠。このアノテーションを支える仕組みが、実はAIMの大きな特徴と言えるかもしれない。
上述したように同社は現在約80施設の医療機関とタッグを組んでいる。がん研究会有明病院や大阪国際がんセンター、東大病院などに所属する世界的に有名な医師たちとのネットワークはなかなかすぐに真似できるものではないだろう。多田氏自身も約20年間にわたって複数の病院や自身のクリニックで内視鏡医を続けてきた、この分野のエキスパートだ。
AIM代表取締役COOの山内善行氏(過去に自身で創業したQLifeをエムスリーに売却した経験を持つシリアルアントレプレナー)の言葉を借りれば、病院や大学の垣根を超えて「オールジャパンに近いような、強力な体制で取り組めている」状況。すでに数万枚に及ぶ診断済みの内視鏡画像をAIに学習させてきた。
世界最大の消化器系学会とされるDDW(Digestive Disease Week)では、12本もの演題が採択。そのうち1題は「Best of DDW」にも選ばれた。今後はこの技術の実用化に向けて取り組むフェーズになる
そもそも内視鏡は日本で開発された医療機器。現在も日本製の内視鏡が多くのシェアを獲得していて、世界でブランドも確立されている。この分野において優れた専門医が集まっているのも日本だ。
近年AIの研究開発や社会実装においては中国やアメリカが最先端を走っている印象が強いが、内視鏡AIに関しては日本初のスタートアップが世界で戦っていけるチャンスもある。
「一矢報いたい気持ちはあるし、その基盤もある。データがあって、現場で内視鏡を使いこなしている専門医もたくさんいる。 日本が1番ノウハウを貯めているので開発にあたってのアドバンテージは大きいし、しっかり活かさないといけない。それができれば『日本の内視鏡は質が高い』というブランドがすでに確立されているので、その上に乗っかることでスピーディーに拡販できる可能性がある」(山内氏)
多田氏によると「世界で見てもまだ類似製品がない状態と考えている」ので、当然AIMでは最初からグローバル展開も視野に入れながら事業を進めていく方針だ。
現場感を基に研究開発、薬事承認に向けた取り組みも加速
冒頭で触れたように今回AIMは複数の投資家から約46億円を調達した。同社では2018年8月にインキュベイトファンドから約10億円を調達しているほか、経営陣の出資や国の助成などを含めると創業2年で累計62億円近い資金を集めたことになる。
前回調達からの約1年は学習データを集める部分に特に力を入れていたが、ここからは製品化を見据えた取り組みを本格化する。臨床試験の推進やパイプラインの拡充、優秀な人材の獲得、設備投資などに投資をして、日本発のリアルタイム内視鏡AIの開発および薬事承認を目指していく。
多田氏と山内氏に今後のAIMの事業におけるカギとなる要素を聞いたところ、まさにこの「薬事承認」がネックになるとのことだった。
内視鏡AIは薬機法の規制を受けるので、まずは認可承認を得なければ実際に製品化することはできない。薬事承認に入ると2年ほどの審査の間はプロダクトのバージョンアップもできなくなるので、どのタイミングで、どのような製品として薬事承認を迎えるかという薬事戦略は非常に重要だ。
逆にこの薬事承認の壁を乗り越えられれば、一気に事業がスケールするイメージもあるそう。「今までいろんな医療機器がでてきたが、(内視鏡AIは)患者さんにとって追加の負担がない。医師にとっても通常の業務フローを大きく変えずに利用できるのは大きな特徴」(多田氏)だという。
創業以来スタートアップとしてハイスピードで研究開発を進めてきたAIMだが、多田氏はそんな今でも同社の代表を勤めながら、内視鏡医として現場にも立ち続けている。
「(この領域は)内視鏡の医療現場を深く知っている人じゃないと、現場の人にとって本当に使い勝手の良い本質的な製品は作れないと思っているので、医療現場にも立ち続けていく」(多田氏)。そこまでしてチャレンジを続けるのは何より自分自身がペインを大きく感じていて、このプロダクトを欲しているからだ。
「よく技術先行の知財ベンチャーだと思われがちだけど、自分たちはそうじゃない。先に現場の課題があって創業者の多田自身がそれを体感して、それを何とか解決できないかという思いから始まった。その過程で偶然AIに出会い、技術者を誘ってきて今がある。完全に現場のニーズから生まれた事業であり、その考え方は今も大事にしている」(多田氏)
だからこそAIMでは内視鏡の分野以外に事業を広げるつもりはない。海外には出ていくが、調達した資金も含めてリソースは全て内視鏡につぎ込む。
日本から生まれた内視鏡という発明。その内視鏡をテクノロジーを用いてアップデートするAIMの挑戦はまだまだ始まったばかり。実際に製品を世に出すまで、そして出して以降も様々な壁はあると思うけれど、スタートアップとしてこの領域でチャレンジする同社の今後に注目だ。